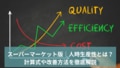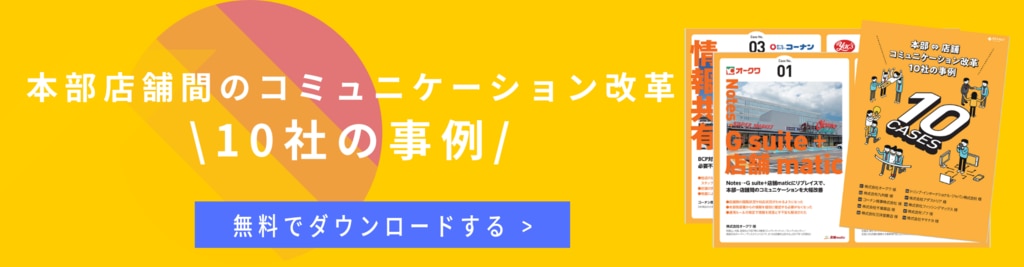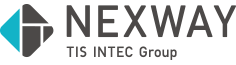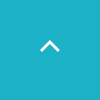店舗コミュニケーションツール店舗maticの機能とは。事例や料金を紹介
店舗を増やすにつれて、店舗と本部間のコミュニケーションの取り方に難しさを感じる企業が多くなります。この記事では、小売店舗をチェーン展開で経営している企業の本部勤務、経営企画、店舗運営、販売部の方に向けて、コミュニケーションにズレが生じる要因や解決策を解説します。今後の効果的なコミュニケーションのために役立ててください。
目次[非表示]
- 1.小売店舗がコミュニケーションにおいて抱えている課題
- 1.1.【本部側】店舗が指示を実施しているかわからない
- 1.2.【本部側】連絡が再度必要で手間がかかる
- 1.3.【本部側】資料の確認や集計作業に時間がかかる
- 1.4.【店舗側】指示が多すぎて業務の妨げになる
- 1.5.【店舗側】連絡手段がバラバラで内容の管理が大変
- 1.6.【店舗側】すべての従業員が指示を確認できているか把握しにくい
- 2.店舗とのコミュニケーションのズレを解消する方法
- 2.1.企業としての方針を明確化する
- 2.2.情報共有のためのルールを策定する
- 2.3.店舗スタッフが使いやすいツールを用いる
- 3.店舗コミュニケーションツール「店舗matic」の特徴
- 4.店舗コミュニケーションツール「店舗matic」の主な機能
- 4.1.業務管理機能
- 4.2.情報共有機能
- 4.3.コミュニケーション機能
- 5.小売店舗でのコミュニケーションツール活用事例
- 5.1.株式会社大創産業様の事例
- 5.2.イオン東北株式会社様の事例
- 5.3.株式会社チュチュアンナ様の事例
- 6.店舗コミュニケーションツール「店舗matic」の料金プラン
- 7.店舗コミュニケーションツールを導入するなら「店舗matic」
- 8.まとめ
小売店舗がコミュニケーションにおいて抱えている課題
小売店舗を多店舗展開する場合、本部は店舗に販売戦略や販促施策を伝え、進捗の確認などを行います。一方、店舗は本部に売上の報告や指示された作業の実施報告などを行います。売上アップや品質向上を目指すには、本部と店舗間での円滑なコミュニケーションが欠かせません。
しかし、本部と店舗間で円滑なコミュニケーションを取ることは、店舗数が増えるほど難しくなり課題を感じる企業様が多くなります。
ここからは、小売業でのコミュニケーションにおいて発生しやすい課題を、本部と店舗に分けて解説します。
【本部側】店舗が指示を実施しているかわからない
本部から現場へ伝えた指示が、実際に実行されているかを把握するのは、多店舗展開をしている企業では課題になりがちです。特に、商品のレイアウト変更やキャンペーンの展開など、各店舗で状況が異なる業務では、実施内容やタイミングに差が出ることがあります。
従来のようにメールや電話を活用して確認しようとすると、やり取りの手間が増え、かえって業務が非効率になる恐れもあるでしょう。さらに、伝え方や解釈に違いがあると、意図していた通りの成果が得られないことも考えられます。
また、指示が誤解されたり、従業員に正確に伝わらなかったりすることで、意図した成果が得られないリスクもあります。本部としては、各店舗の実行状況を把握するだけでなく、店舗スタッフに対しても正確かつ効果的なコミュニケーションが求められます。
本部と店舗間のコミュニケーション課題についてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。
【本部側】連絡が再度必要で手間がかかる
一度伝えた内容でも、現場で十分に理解されていなかったり、確認の行き違いがあったりすることで、再度連絡を行う必要が出てきます。例えば、新商品の情報やプロモーションの詳細を何度も店舗側に問い合わせる必要があると、結果的に双方にとって時間と労力が浪費されます。
特に、店舗数が増加するにつれて、このような無駄な確認作業はさらに増加し、他の重要な業務に影響を与えることになります。
また、コミュニケーションの方法が統一されていない場合、一部の店舗ではメールを、他の店舗では電話やチャットツールを使うといった状況が発生し、情報が混乱する原因にもなります。これにより、迅速な意思決定が困難になり、結果として販売戦略の実行に遅れが生じることもあります。
【本部側】資料の確認や集計作業に時間がかかる
多店舗展開をしている小売店舗では、本部は全体の状況を把握するための、報告を集約した資料作成が必要です。しかし、店舗からの報告がフォーマットや媒体でバラバラであったり、手書きの報告書をスキャンして送っていたりなどの手間が発生すると、資料の確認や集計作業が非常に時間のかかる作業となります。
このような手作業が多い場合、本部スタッフの労働時間が増加し、他の重要な業務に割く時間が減少します。また、手作業での集計作業では、ヒューマンエラーのリスクが高くなり、報告データの正確性が担保されないことも問題です。データの不正確さは、経営判断のミスにつながる可能性があるため、情報の一元管理と効率化が急務です。
また、教育面でも課題は顕在化しています。たとえば、新人スタッフ向けの業務マニュアルが整理されていなかったり、共有がバラバラであったりすると、各店舗で指導内容に差が出てしまいます。その結果、スタッフの習熟度にばらつきが生まれ、サービス品質の統一が難しくなるといった問題が発生します。統一されたマニュアルの整備と効率的な情報共有は、教育コストの最適化にも直結する重要なポイントです。
続いて、店舗側の課題についても解説します。
【店舗側】指示が多すぎて業務の妨げになる
店舗側から見た場合、日々の業務に加え、本部からの指示や依頼が多すぎることが大きな課題です。例えば、新商品の陳列方法、プロモーションの実施内容、売上目標の達成に向けたアクションプランなど、本部からの指示は多岐にわたります。これらの指示が頻繁に変わったり、追加されたりすることで、現場の従業員は通常業務に集中できず、業務の効率が低下することがあります。
また、指示の優先順位が明確でない場合、現場のスタッフはどの指示に従うべきか判断に迷い、結果的に重要な業務が後回しになることもあります。
このような状況は、スタッフのモチベーション低下を招き、顧客対応の質や店舗全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
【店舗側】連絡手段がバラバラで内容の管理が大変
本部からの連絡手段が統一されていない場合、店舗では情報の管理が煩雑になりやすいです。メールやチャット、電話、グループウェアなど複数の手段が混在していると、必要な情報を探すのに時間がかかってしまいます。
特にシフト制で働くスタッフにとっては、勤務時間外に届いた連絡を確認しそびれるケースも少なくありません。その結果、重要な通達を見逃してしまい、業務に支障が出る事態も考えられます。
また、複数のツールに情報が分散していると、過去のやり取りを振り返る際にも手間がかかります。指示内容の確認や報告書の提出状況など、業務に必要な情報がすぐに見つからない状態では、スムーズな店舗運営は実現できません。
【店舗側】すべての従業員が指示を確認できているか把握しにくい
店舗では多くのスタッフが交代で勤務しているため、本部からの指示が全員に確実に伝わっているかを把握するのが難しいという課題があります。特に、紙の掲示や口頭での伝達に頼っている場合、シフト外の従業員に情報が行き渡らず、対応漏れが発生することもあるでしょう。
さらに、従業員ごとに情報の確認方法や習慣が異なるため、誰がどの情報を確認したのかを追跡することが困難です。このような状況では、全員が最新の指示に基づいて動けていないことがあり、店舗全体の統制が取れなくなります。結果として、店舗内での作業ミスや対応の遅れが発生し、顧客満足度の低下や売上への悪影響が懸念されます。
次は、このような課題が生まれる原因について紹介いたします。
◆本部・店舗間のコミュニケーションに課題をお感じの方にはこちらの記事もおすすめです。
◆チェーンストアでのコミュニケーションの課題タイプ診断で、課題を可視化することができます。以下のリンクから、診断のための資料をダウンロード可能です。
チェーンストア 本部店舗間コミュニケーション 課題タイプ診断
店舗とのコミュニケーションのズレを解消する方法
本部と店舗間におけるコミュニケーションのズレは、情報の伝え方や受け取り方に原因があることが少なくありません。
ですが、いくつかの工夫や取り組みを通じて、そうしたギャップは解消できます。
ここでは、効果的なコミュニケーションを実現するために、企業として意識すべきポイントをご紹介します。
企業としての方針を明確化する
本部から指示を出す際には、なぜその施策を行うのかといった背景や目的まで含めて丁寧に伝えることが重要です。ただ数字や実施内容を伝えるだけでは、現場での理解や納得感を得ることは難しくなります。
たとえば、売上目標が設定された理由や、その達成によって得られる店舗のメリットなどを明確に示すことで、スタッフ一人ひとりの責任感やモチベーションを引き出すことができるでしょう。目標に向かって店舗全体が一丸となって取り組むには、全従業員に企業の方針をしっかり共有し、共通認識を持ってもらうことが不可欠です。
企業としての方針は店長など一部の従業員だけでなく、店舗内全体に伝えることもポイントです。一人ひとりの意識が高まれば、「みんなで目標を達成しよう」という団結力が生まれて店舗全体のクオリティアップが見込めます。
情報共有のためのルールを策定する
円滑な情報伝達を実現するには、ルールの整備が不可欠です。たとえば、連絡の手段を統一したり、連絡するタイミングや頻度をあらかじめ決めておくことで、無用な混乱や作業の中断を防ぐことができます。
また、どのスタッフでも理解できるよう、共通の言葉や表現を用いることも大切です。動画や画像を活用して、視覚的に情報を補足すれば、言葉だけでは伝わりづらい内容もより明確になります。
緊急の連絡を除き、日常業務の妨げにならない時間帯に情報を共有するなど、配慮ある運用も従業員満足度の向上につながります。こうした情報共有のルールを明文化し、社内で徹底することが、組織全体の効率化を支える土台となるでしょう。
店舗スタッフが使いやすいツールを用いる
情報伝達の手段は、本部の視点だけでなく、実際に現場で働くスタッフの使いやすさを重視して選定する必要があります。特にITリテラシーに差がある現場では、直感的に操作できるインターフェースや、重要な情報をぱっと見で把握できるツールを使うことで、店長や店舗スタッフの負担も減りコミュニケーションもより円滑になります。
また、言葉だけで伝えづらい作業内容については、動画や画像を添えて共有できる機能があると便利です。たとえば、棚のレイアウト変更や設備の修理依頼などは、視覚的な情報の方が正確に伝わります。
このように、スタッフが無理なく情報を受け取り、すぐに行動に移せる環境を整えることで、本部と店舗間のコミュニケーションはよりスムーズになります。業務のムダを減らし、対応のスピードと正確性を高めるためにも、現場の声に耳を傾けたツールの導入が効果的です。
ネクスウェイのコミュニケーションツール「店舗matic」は、本部から店舗に届いた連絡を自動的に整理したり、本部が現場の状況をリアルタイムで確認できたりと、業務の効率化を加速させる多彩な機能を搭載しています。店舗maticで本部と店舗間のコミュニケーションに関する悩みを解決しましょう。
◆コミュニケーションツールの導入をご検討の方は、ぜひこちらで課題を整理してみてください。
店舗コミュニケーションツール「店舗matic」の特徴
「店舗matic」は、本部と店舗間の情報伝達を効率化し、現場の業務負荷を軽減するために開発されたクラウド型コミュニケーションツールです。ここでは、店舗maticがもたらす主な3つの特長をご紹介します。
業務連絡を一元化し、負担を軽減
本部から店舗への連絡手段が複数に分かれていると、情報の見落としや伝達ミスが起きやすくなります。「店舗matic」は、そうした課題を解決するため、業務に必要なすべての連絡をひとつのプラットフォームに集約。
「お知らせ」や「作業指示」「回答フォーム」「カレンダー」などの機能を通じて、あらゆる情報を一元管理できます。
店舗スタッフは、どこを見れば何の情報が確認できるかが一目でわかるため、日々の確認作業がスムーズになります。また、本部側も「誰に、何を、いつ伝えたか」を明確に把握できるため、再送信やフォローアップの負担を大幅に減らすことが可能です。
リアルタイムで指示を共有し、店舗運営をスムーズに
店舗maticは、リアルタイムでの情報共有を可能にする機能を多数備えています。たとえば、指示内容の送信と同時に既読確認や回答の収集ができ、実施状況の可視化にも対応しています。
「重要な連絡が埋もれてしまった」「誰が確認したのかわからない」といった従来の悩みを解消し、迅速で正確なコミュニケーションを実現します。特に、多忙な店舗業務の合間でも直感的に操作できるUI設計により、現場への負担を抑えながら情報の浸透を図れるのが大きな強みです。
時間や場所にとらわれず、必要な情報を即座に共有できる環境は、全体の業務スピードを加速させ、売上やサービス品質の向上にもつながります。
多店舗管理を効率化し、業務の属人化を防ぐ
店舗maticは、100店舗を超えるような多店舗展開企業においてもスムーズな運用が可能です。店舗ごとの対応状況や報告内容が可視化されるため、本部側は全体の進捗をリアルタイムで把握できます。
さらに、報告業務やアンケート、売場ノートなどの情報も集約できるため、「特定の担当者しか分からない」「いつもの担当が不在で対応が遅れる」といった属人化のリスクも軽減されます。
蓄積されたデータは共有・再利用も容易で、ノウハウの継承や業務の標準化にも活用可能です。部門間の連携や異動時の引き継ぎもスムーズになり、組織全体としての業務効率が高まります。
◆店舗maticの機能詳細はこちらをご覧ください。
店舗コミュニケーションツール「店舗matic」の主な機能
「店舗matic」は、単なる連絡ツールにとどまらず、業務管理から情報共有、コミュニケーションまで、店舗運営に欠かせない機能を多数搭載しています。本部と店舗の橋渡しを行うこのツールが、どのように日々の業務をサポートしているのかをご紹介します。
業務管理機能
現場の業務効率を高めるために、「店舗matic」には多彩な業務管理機能が搭載されています。
たとえば「ToDoリスト」では、本部からの作業指示を店舗単位で一覧化。スタッフはやるべきタスクを明確に把握でき、業務の漏れや遅れを防ぐことができます。
また、「かんたん集計」機能を使えば、売上報告やキャンペーン結果などの定量情報をすぐにまとめられるため、本部の集計作業にかかる手間を大幅に削減可能です。「定期報告」では、月次・週次など繰り返し発生する報告業務もテンプレート化され、提出の抜け漏れを防止します。
さらに「実施状況の把握」や「利用状況レポート」によって、誰が、いつ、どの情報を確認・実行したのかを一目で把握できるため、進捗管理がよりスムーズになります。
「エリアマネージャービュー」は、複数店舗を管理するマネージャー向けの機能で、店舗ごとの進捗状況や対応内容を一覧で確認できます。現場の状況を把握しながら、効果的なフォローが行えるようになります。
情報共有機能
本部からの情報が確実に届き、現場で正しく理解されるためには、見やすく整理された情報共有の仕組みが不可欠です。
「フレッシュマニュアル」機能では、従来の紙ベースの手順書に代わり、画像や動画を使ったわかりやすいマニュアルを共有できます。新人スタッフの教育や店舗運営の標準化にも有効です。
また、「アンケート」機能では、簡単な操作で意見収集や状況把握が行え、未回答者への自動リマインドも可能です。「カレンダー」では部署間のスケジュール共有ができるため、業務の重複や連携ミスを防ぎます。
加えて、「ワークフロー」機能により、店舗から本部への申請や承認プロセスもスムーズに。さらに「ファイル管理」機能を使えば、販促物や業務資料などの共有もクラウド上で一元化でき、必要な情報にいつでもアクセスできます。
コミュニケーション機能
本部と店舗、また店舗間でのコミュニケーションを促進するために、いくつかの専用機能も用意されています。
「コミュニティ」機能では、店舗同士の情報交換やノウハウの共有が可能です。成功事例の紹介や質問のやり取りを通じて、店舗全体のレベルアップにつなげることができます。
「メッセンジャー」では、個別またはグループ単位でのやり取りができ、リアルタイムな情報共有に便利です。口頭や電話に頼らず、履歴を残した形でコミュニケーションを行えるため、確認ミスの防止にも役立ちます。
◆店舗maticの
小売店舗でのコミュニケーションツール活用事例
スタッフが使いやすいコミュニケーションツールを活用することによって、小売店舗でありがちなコミュニケーションにおける課題を解決することができます。
ここでは、コミュニケーションツール「店舗matic」をお使いいただいた事例を通じて、どのようにしてコミュニケーションの改善を実現し、業務効率の向上を果たしているのかをご紹介します。
株式会社大創産業様の事例
100円ショップ「ダイソー」を主として、国内外5,000店舗以上の出店実績を持つ株式会社大創産業様。
これまで、複数のコミュニケーションツールが混在しており、本部やSVからの指示が分散し、コミュニケーションコストが増加していることや、指示の形式がバラバラでタスクの期日や優先順位が分かりづらく、回答の漏れや遅れが出てしまうという課題がありました。
本部側でも、店舗側の作業の進捗状況が見えにくいことや、問い合わせ対応や回答の遅れ・漏れに対するリマインドの業務負担が大きいという課題があったようです。
そこで、ネクスウェイの「店舗matic」にツールを一元化したところ、タスク管理の負担が軽減し、作業の実行性が向上しました。本部側も進捗確認の管理がしやすくなり、問い合わせ対応も激減しました。
詳しい事例は、以下のリンクで詳しくご確認していただけます。
イオン東北株式会社様の事例
東北6県で157店舗を展開するイオン東北株式会社様。店長やマネージャーに情報が集中し、1日100件以上のメール対応が発生するなど、本部と店舗間の情報共有に大きな課題を抱えていました。
また、メールやグループウェアの併用によって情報が分散し、重要な連絡の見落としや指示の遅れも発生していたとのことです。
ネクスウェイの「店舗matic」を導入したことで、本部-店舗間の連絡を一元化。指示の伝達精度が向上し、店舗側でも情報の見落としが大幅に減少しました。
さらに、アンケート機能やカレンダー機能の活用により、業務効率と部署間の連携も改善されています。
詳しい事例は、以下のリンクで詳しくご確認していただけます。
株式会社チュチュアンナ様の事例
全国に262店舗を展開する株式会社チュチュアンナ様では、本部からの指示が各店舗でどの程度実行されているか把握しづらく、実行率向上が大きな課題となっていました。特に、指示が伝わっていないのか、内容が理解されていないのかが判断できず、改善の糸口が見えない状況が続いていたといいます。
また、店舗には各部門から不定期にさまざまな連絡が届く一方で、本部側も指示の実施状況を確認できず、コミュニケーションの非効率さが顕在化していました。
ネクスウェイの「店舗matic」を導入したことで、情報の整理と指示の伝達がスムーズになり、本部と店舗のコミュニケーションが大幅に改善。実行状況の把握も可能になり、業務全体の精度向上につながりました。
詳しい事例は、以下のリンクで詳しくご確認していただけます。
店舗コミュニケーションツール「店舗matic」の料金プラン
「店舗matic」では、導入企業様の規模や活用目的に合わせて選べる3つの料金プランをご用意しています。

ミニマムプラン(月額2,480円/1店舗あたり)
「まずは基本機能から試したい」という企業様向けのプランです。お知らせ機能や作業指示、回答、カレンダーなど、情報伝達に必要な基本機能を網羅しています。
利用状況のレポートや売場ノートにも対応しており、シンプルかつ効率的な運用を低コストで始められます。
ライトプラン(月額3,480円/1店舗あたり)
機能を絞りつつも、より幅広い業務に対応したい企業様に適したプランです。ミニマムプランの機能に加え、書庫、定期報告、フレッシュマニュアルなどが利用可能となります。
情報の蓄積や業務の定型化に取り組みたい場合におすすめです。
スタンダードプラン(月額6,000円/1店舗あたり)
「店舗matic」のすべての機能が利用できる最上位プランです。業務アプリ、メッセンジャー、施設・設備予約などを含んでおり、本部・店舗間のコミュニケーションを完全に一本化したい企業様に最適です。
複雑な業務や多部門連携が必要な企業でも、スムーズな情報共有と運用が可能になります。
店舗コミュニケーションツールを導入するなら「店舗matic」
多店舗展開を行う小売企業にとって、本部と店舗の連携は業務の効率だけでなく、売上や顧客満足度にも大きく影響します。そんな中、「店舗matic」は、現場の声を反映した多機能なクラウドツールとして、高い評価をいただいています。
本部と店舗の連絡を一元化し、業務の効率を大幅に向上
本部からの情報発信や指示を「店舗matic」に一本化することで、メールや電話、紙の資料といった複数の手段による連絡を削減できます。情報の見落としや伝達ミスが減り、業務のムダを解消。
タスクの進捗状況もリアルタイムで可視化できるため、本部側の管理負担も大きく軽減されます。
業務指示・進捗管理をスムーズにし、働きやすい環境を実現
「誰が」「いつ」「何を実行したのか」がひと目でわかる設計により、現場スタッフも安心して業務に集中できます。
また、直感的に使えるシンプルな画面構成は、ITに不慣れな従業員にも好評です。マニュアルやアンケート、メッセンジャー機能なども活用することで、店舗ごとの情報レベルの差も縮小され、全体のクオリティが向上します。
まずは資料ダウンロード・無料相談をご利用ください
「店舗matic」では、無料の資料ダウンロードやご相談を随時受け付けております。実際の導入事例や機能詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
◆資料ダウンロードはこちら(無料)
◆導入に関するご相談はこちら
まとめ
多店舗展開を経営している企業は、コミュニケーションにおいて本部と店舗それぞれが課題を抱えているケースも珍しくありません。本部と店舗間のコミュニケーションにズレが生まれる要因はさまざまですが、企業としての方針を明確にしたり情報共有のルールを策定することで対策できます。
株式会社ネクスウェイでは、チェーンストア企業様向けの情報通信サービスを提供しています。本部と店舗間のコミュニケーションや業務効率化などの課題を解決するツールとアプリを用意し、10年以上にわたり提供してきました。
「店舗matic」は、多店舗展開を行っている企業の課題を根本から解決する店舗コミュニケーションツールとして、多くの企業で導入が進んでいます。情報の一元管理やタスクの可視化、操作性の高いインターフェースにより、本部と現場の連携を強化し、業務全体の質を高めることが可能です。
コミュニケーションに関する悩みや情報共有の仕組みに課題を感じている企業様は、ぜひ一度「店舗matic」の資料をご覧ください。
無料トライアルや個別相談も受け付けております。導入前の不安や疑問にも丁寧に対応いたします。
>>本部店舗間コミュニケーションを円滑にする「店舗matic」の資料をダウンロードする【無料】
【3分でわかる!】本部店舗間コミュニケーション課題タイプ診断の資料をダウンロードください。