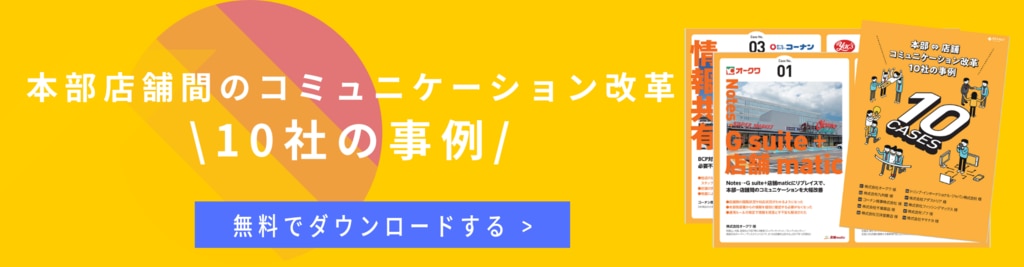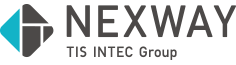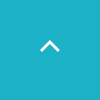店舗DXとは?導入事例や課題、実施するポイントをわかりやすく解説
目次[非表示]
- 1.店舗DXとは?
- 1.1.店舗DXは運用・体験に分けられる
- 1.1.1.店舗DXの例
- 1.2.店舗DXを行う目的
- 2.店舗DXが進められている理由
- 2.1.慢性的な人手不足
- 2.2.顧客体験の向上
- 2.3.データ活用による業務改善
- 2.4.多店舗展開・本部管理の効率化
- 3.店舗DX導入のメリット
- 4.店舗DX導入時の課題
- 4.1.導入コストがかかる
- 4.2.従業員への教育が必要になる
- 4.3.データセキュリティ対策をする必要がある
- 5.店舗DX化のためツールを導入した事例
- 5.1.株式会社ヤマナカ様の事例
- 5.2.イオン東北株式会社様の事例
- 5.3.株式会社バロックジャパンリミテッド様の事例
- 6.店舗DX導入のポイント
- 6.1.課題や目標を明確にする
- 6.2.適切なツールを選定する
- 6.3.継続的に評価・改善をする
- 7.店舗DXの第一歩ならコミュニケーションツールの活用がおすすめ
- 8.まとめ
少子高齢化による人手不足、顧客体験の多様化、データ活用の重要性など、店舗運営を取り巻く課題は年々複雑化しています。
こうした背景のもと、注目を集めているのが「店舗DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
単なるアナログ業務のデジタル化にとどまらず、業務効率の向上やサービス品質の変革を通じて、競争力のある店舗運営を実現することが求められています。
本記事では、店舗DXの基本的な考え方から、導入の目的、実際の取り組み事例、導入にあたっての課題と対策、そして成功のポイントまでをわかりやすく解説します。
店舗DXとは?
店舗DXとは、デジタル技術を活用して店舗運営や顧客体験を抜本的に変革する取り組みのことです。単なるアナログ業務のデジタル化にとどまらず、業務効率の向上やサービス品質の最適化など、ビジネス全体の競争力を高めることを目的としています。
近年では、レジ業務の無人化、デジタルサイネージの導入、顧客データの活用など、さまざまな業態・業種で店舗DXが進められており、特にチェーンストア本部や多店舗を展開する企業にとっては、全体最適を見据えたDX戦略が欠かせない時代となっています。
店舗DXは運用・体験に分けられる
店舗DXの取り組みは大きく分けて「運用DX」と「体験DX」に分類されます。
「運用DX」は、店舗のバックヤード業務や本部とのやりとりなど、店舗運営に関わるプロセスを効率化・可視化することを指します。たとえば、キャッシュレス決済の導入、業務タスクの一元管理、グループウェアによる情報共有などが代表例です。
一方、「体験DX」は、顧客との接点にデジタル技術を取り入れ、より便利で魅力的な購買体験を提供することを目的としています。オンライン注文、会員アプリ、パーソナライズされたプロモーションなど、顧客満足度の向上につながる施策が該当します。
店舗DXの例
実際の取り組み例としては、AI付き防犯カメラによる来店者分析、デジタルサイネージでのキャンペーン訴求、クラウドベースの勤怠管理、グループウェアを通じたタスク共有などがあります。これらは一見バラバラに見えても、すべてが業務効率と顧客体験の向上に結びつく、DXの一部です。
店舗DXを行う目的
店舗DXを進める目的は、企業ごとに異なるものの、大きく以下のような狙いに集約されます。
- 業務の属人化を解消し、店舗運営を標準化する
- スタッフの負担を軽減し、現場の働きやすさを高める
- 顧客の行動やニーズをデータで把握し、戦略的な販売施策につなげる
- パーソナライズされた情報の提供により顧客の意思決定をサポートする
- 本部と店舗の連携を円滑にし、スピード感のある意思決定を可能にする
こうした目的のもと、多くの企業が自社に最適なDXのかたちを模索しています。次のセクションでは、こうしたDXの流れがなぜ加速しているのか、その背景を見ていきます。
店舗DXが進められている理由

デジタル技術の進化に加え、社会やビジネス環境の変化により、店舗DXの必要性は急速に高まっています。ここでは、店舗DXが注目されるようになった主な背景を4つの観点から解説します。
慢性的な人手不足
少子高齢化により労働人口が減少する中、多くの業界で人手不足が深刻な課題となっています。小売・サービス業も例外ではなく、シフトの穴埋めや教育コストの増加、スタッフの定着率低下など、現場の負担は年々増しています。
このような状況に対して、DXの導入により省人化や業務効率化を図ることで、少ない人数でも店舗運営が回る体制を構築する企業が増えてきました。たとえば、作業の自動化や業務の可視化によって、スタッフの負担を減らすことが可能になります。
顧客体験の向上
ネットショッピングが当たり前となった今、リアル店舗に求められるのは“わざわざ訪れたくなる体験”です。アプリを通じた来店予約やポイント管理、AIデジタルサイネージによるプロモーション、セルフレジの導入など、DXを通じて利便性や満足度を高める取り組みが進められています。
このような購買体験の質が向上することで、顧客のロイヤルティが高まり、リピーターやファンの獲得にもつながります。
データ活用による業務改善
紙や勘に頼った業務判断から脱却し、実際の顧客行動や売上データに基づいた運営が求められる時代です。DXによって情報をリアルタイムに収集・分析できる環境を整えることで、販売戦略の最適化や業務改善が進みます。
POSデータの分析による売場設計の見直しや、来店者データを活用したキャンペーン施策など、データを活かした店舗運営が成果を生む鍵となっています。
多店舗展開・本部管理の効率化
チェーンストアやフランチャイズにおいては、店舗数の増加に伴い、本部と各店舗の連携が複雑化していきます。従来のメールやFAXによる連絡では情報の抜け漏れや伝達遅れが発生しやすく、現場対応が後手に回るケースもあります。
こうした課題に対し、クラウド型のコミュニケーションツールやタスク管理システムを活用することで、本部からの指示がリアルタイムに届き、実行状況を即時に把握できるようになります。結果として、全体最適な運営が可能になります。
このように、店舗DXが進められる背景には、多角的な課題とそれに応えるソリューションの存在があります。次のセクションでは、DX導入によって得られる具体的なメリットについてご紹介します。
店舗DX導入のメリット
店舗DXを導入することで、現場・本部双方にとって多くのメリットが生まれます。ここでは、業務効率だけでなく、売上や人材定着といった視点からも、その効果を見ていきましょう。
業務の効率化・省人化が実現できる
DXの最大のメリットは、業務の効率化と省人化の実現です。たとえば、紙で行っていたチェックリストや報告書をデジタル化することで、記入・提出・確認にかかっていた時間を大幅に短縮できます。また、タスクの進捗管理やシフト作成、備品の発注など、手間のかかる作業を自動化することで、限られた人員でも店舗を円滑に運営できるようになります。
店舗全体の売上や業績の改善に寄与する
業務効率が上がることで、スタッフは顧客対応や売場づくりといった“本来注力すべき業務”に時間を割けるようになります。その結果、サービス品質が向上し、顧客満足度の向上にもつながります。さらに、データに基づいた売上分析やキャンペーン施策の最適化が進むことで、店舗全体の収益力を底上げすることが可能です。
データに基づく経営判断が可能になる
これまで勘や経験に頼っていた業務判断も、DXの導入により客観的なデータに基づいて行えるようになります。たとえば、売上データ、来店者数、作業進捗状況などのリアルタイム把握が可能になれば、タイムリーな意思決定や柔軟な改善施策の立案が可能です。経営における“スピードと正確性”が飛躍的に高まります。
次のセクションでは、こうしたメリットの裏にある「導入時の課題」についても触れていきます。DXは一筋縄ではいかないからこそ、想定される障壁とその対処法を知っておくことが重要です。
店舗DX導入時の課題

店舗DXには多くのメリットがありますが、導入にあたっては現場・本部ともに乗り越えるべき課題も存在します。ここでは、代表的な3つの課題と、それに対する備えのポイントを紹介します。
導入コストがかかる
DXには一定の初期費用が必要です。ハードウェアの購入、システム導入費、月額利用料、社内の設計・調整工数など、導入の規模によっては負担が大きくなることもあります。
ただし、コストだけを見て導入をためらうのではなく、中長期的な“費用対効果”を見極めることが重要です。たとえば、人件費や時間の削減、売上の増加、離職率の低下といった数値を想定することで、投資としての意義が明確になります。小規模で始めて段階的に拡大するスモールスタートも有効な方法です。
従業員への教育が必要になる
新たなシステムを導入しても、現場のスタッフが使いこなせなければ、効果を十分に発揮できません。特にITに不慣れな従業員が多い場合、「難しそう」「面倒そう」といった心理的な抵抗がDX定着の妨げとなることがあります。
この課題を乗り越えるには、丁寧な初期レクチャーや分かりやすい操作マニュアルの整備、現場からの声を拾うフォロー体制が不可欠です。また、現場の実情に即したUIや機能を備えたツールを選ぶことも、教育コストを抑えるポイントになります。
データセキュリティ対策をする必要がある
DXによって顧客情報や業務データをクラウド上で扱う機会が増えるため、情報漏洩やサイバー攻撃に対するリスク管理が欠かせません。万が一にも不正アクセスやデータ消失が起これば、信頼の失墜や営業停止といった大きな損害につながる恐れがあります。
そのため、セキュリティ対策がしっかりと施されたサービスを選定することが前提条件となります。アクセス制限やログ管理、データ暗号化など、リスクを最小限に抑える機能を備えたツールを選び、社内でもセキュリティ意識を高める取り組みが必要です。
店舗DX化のためツールを導入した事例
業務の属人化や情報伝達の遅れ、確認作業の煩雑さなど、店舗運営における多くの課題は「コミュニケーションの非効率」に起因しています。こうした課題を解決し、業務の見える化・標準化を実現する手段として、DXツールの導入が注目されています。
ここでは、実際に店舗DXを推進するためにツールを導入し、業務効率の改善や顧客体験の向上を実現した企業の事例をご紹介します。
株式会社ヤマナカ様の事例
愛知県を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社ヤマナカは、従来のメール中心の連絡業務を見直し、「店舗matic」を導入。情報発信のルール化とフィルター機能により、店長は1日3回のタブレット確認だけで必要な指示を把握できるようになり、売場作業に集中できる環境が整いました。
また、売場写真を共有できる「売場ノート」も併用し、SVが巡回せずに現場状況を把握可能に。本部のペーパーレス化も進み、創出されたリソースはDX推進に活用されています。店舗DXを通じて、ヤマナカは業務の効率化と顧客体験の向上を同時に実現しています。
詳しい事例は以下からご確認いただけます。
【株式会社ヤマナカ様】 本部-店舗間連絡の脱メール・ペーパーレス化を同時に実現! 「店舗matic」「売場ノート」でDX推進へのマンパワーを創出
イオン東北株式会社様の事例
東北6県で157店舗を展開するイオン東北株式会社は、店舗運営のDX推進の一環として「店舗matic」を導入。店長1人あたり1日100件以上のメールを処理していた状況から脱却し、指示や連絡を一元化しました。
その結果、情報の見落としが減少し、アンケートや作業報告の負担も軽減。本部では宛先管理やメール更新の手間が削減され、カレンダー機能を活用した部署間連携も促進されています。今後はさらなる機能活用により、スマートストア実現に向けたDXを加速していく方針です。
詳しい事例は以下からご確認いただけます。
【イオン東北株式会社様】 人時効率改善を狙い157店舗と本部間の連絡を一元化 スマートストア実現に向けたDXを大きく前進
株式会社バロックジャパンリミテッド様の事例
「MOUSSY」「AZUL BY MOUSSY」など人気ブランドを展開する株式会社バロックジャパンリミテッドは、全社での業務一元化と店舗DX推進のため「店舗matic」を導入。メールやFAXでの作業依頼に起因する伝達ミスや対応遅れといった課題を解消しました。
タスクの可視化やフォトレポート機能により、店舗ではVMDの参考共有や売場改善がしやすくなり、事務作業の効率化によって接客・販売に集中できる環境を整備。本部でも確認作業の負担が軽減され、迅速かつ正確な情報共有が可能になりました。今後は「店舗matic」への業務集約をさらに進め、全ブランドでの統一運用を目指しています。
詳しい事例は以下からご確認いただけます。
株式会社バロックジャパンリミテッド様 16ブランドで「店舗matic」を活用コア業務である接客・販売へ注力できるように
店舗DX導入のポイント
店舗DXを成功させるためには、ツールを導入するだけでは不十分です。自社にとって本当に意味のある変革を実現するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、導入時に特に重要となる3つの視点を解説します。
課題や目標を明確にする
DXを進めるうえでまず大切なのは、「なぜDXに取り組むのか」「何を改善したいのか」といった課題や目的を明確にすることです。現場で困っていること、本部が改善したいことなどを具体的に洗い出すことで、導入すべき機能や優先順位が見えてきます。
たとえば、「タスクの伝達ミスが多い」「店舗ごとの業務品質に差がある」といった課題がある場合は、コミュニケーションや業務管理を強化できるツールの導入が有効です。漠然とした“DXをしなければ”という考えではなく、現場視点での課題を起点に考えることが、成果につながる第一歩となります。
適切なツールを選定する
市場には多種多様なDX支援ツールが存在しますが、すべての企業・店舗に共通して最適なものはありません。自社の課題や業務フロー、スタッフのITリテラシーに合ったツールを選定することが不可欠です。
たとえば、シンプルな操作性を重視するならスマートフォン対応のツール、マルチ店舗での管理を強化したいなら一元管理が可能なクラウド型のプラットフォームが適しています。また、ツールの価格や導入サポート体制、セキュリティ機能なども選定時の重要な判断材料となります。
継続的に評価・改善をする
DXは導入して終わりではなく、「使い続けて成果を出すこと」が本来の目的です。そのためには、運用状況を定期的に評価し、現場の声をもとに改善を重ねていく姿勢が求められます。
たとえば、導入後に「思ったより活用されていない」と感じた場合は、レクチャーの充実や運用ルールの見直しが必要です。また、機能追加や利用範囲の拡大を視野に入れて、成長に応じたアップデートも柔軟に行いましょう。継続的にPDCAを回すことで、DXの効果を最大化できます。
店舗DXの第一歩ならコミュニケーションツールの活用がおすすめ
店舗DXを推進するうえで、最初に着手すべき領域としておすすめなのが「本部と店舗間のコミュニケーション」です。
私たちが行ったアンケート(7社・1078店舗/有効回答最大1403件)では、64%の店舗スタッフが「本部からの指示に管理漏れ・忘れがある」と回答しており、現場でのコミュニケーション課題の大きさがうかがえます。
そこで有効なのが、タスク管理機能を備えたコミュニケーションツールの導入です。本部からの指示がそのまま「やるべきこと」として明確に可視化されるため、店舗側も優先順位を判断しやすく、実行率が大きく向上します。また、実施状況の確認やフォローも簡素化されるため、本部の負担も大きく軽減されます。
スマートフォンやタブレットに対応したツールであれば、ITリテラシーに不安があるスタッフでも直感的に操作でき、導入のハードルを抑えることができます。DXの第一歩として、コミュニケーションの効率化から取り組むことは、現場にとっても本部にとっても大きな成果につながる現実的なアプローチです。
まとめ
店舗DXは単なるデジタル化ではなく、業務の質とスピードを高め、店舗運営全体のパフォーマンスを底上げするための重要な取り組みです。中でも、日々の業務を支える「コミュニケーションの仕組み」を見直すことは、最小の負荷で最大の効果を生み出せるDXの入口といえるでしょう。
まずはタスク管理や情報共有を効率化するツールを導入し、店舗と本部が同じ目線で動ける環境を整えることが大切です。少しずつ確実に変化を積み重ねていくことが、結果として、業務効率・顧客満足・従業員の働きやすさといった多方面での成果につながります。
DXを「特別なこと」と構えず、「今できることから始める」。その第一歩として、コミュニケーションのデジタル化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
オペレーション見直しや業務効率化についてお悩みがございましたらお気軽にご相談ください