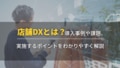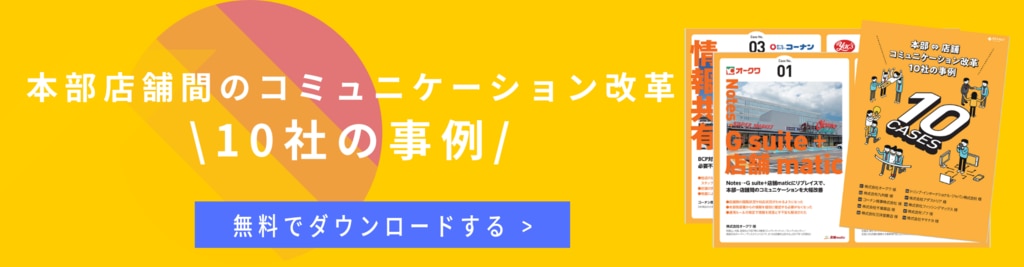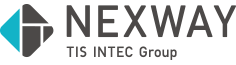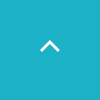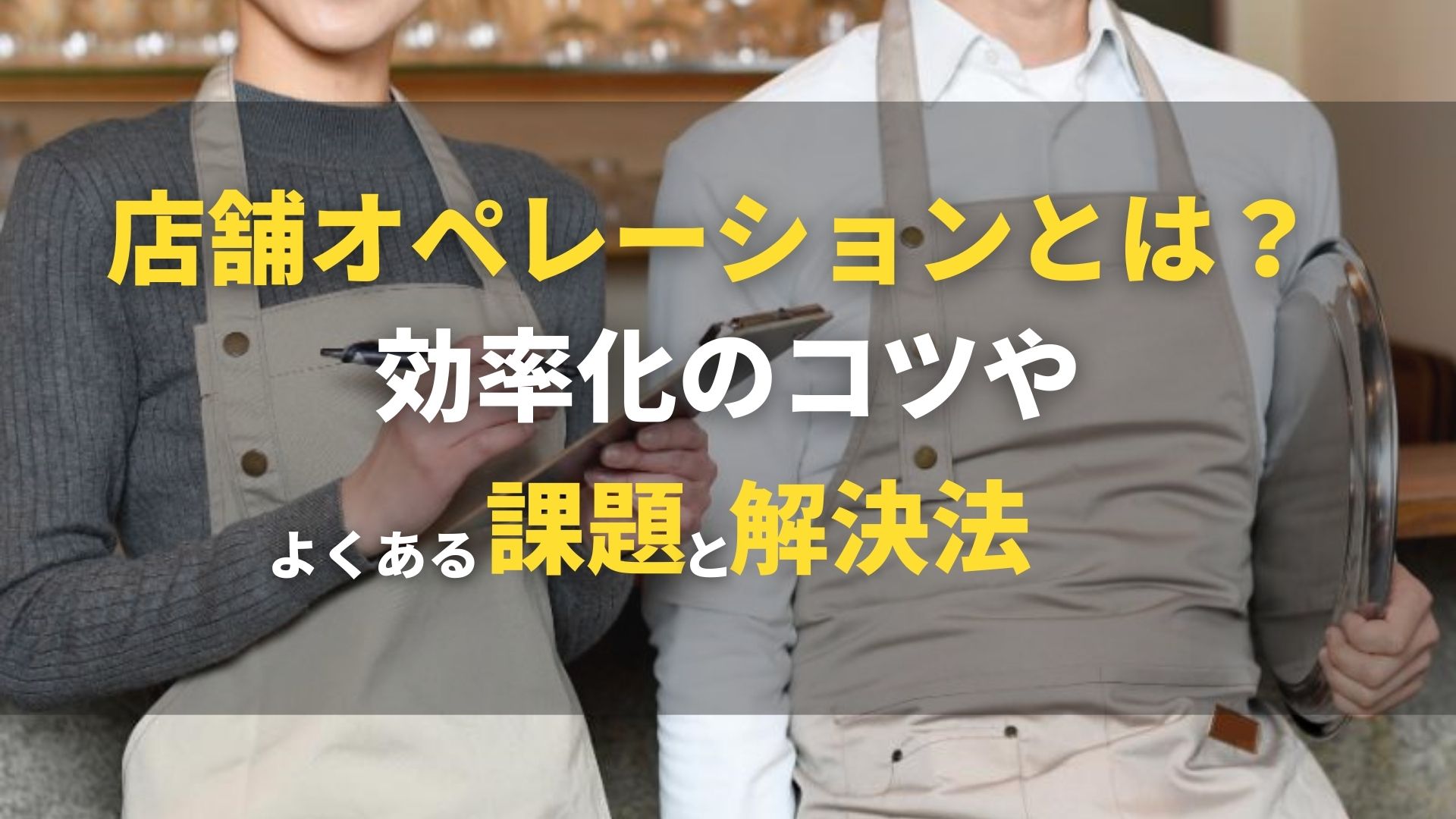
店舗オペレーションとは?効率化のコツやよくある課題と解決法
目次[非表示]
- 1.店舗オペレーションとは
- 2.店舗オペレーションはなぜ必要?
- 2.1.サービス品質の向上のため
- 2.2.売上拡大のため
- 2.3.トラブル対応のため
- 2.4.業務の効率化のため
- 3.店舗オペレーションの具体的な業務
- 4.店舗オペレーションのよくある課題
- 4.1.本部指示がうまく伝わらない
- 4.2.人員不足で一人の業務量が多い
- 4.3.事務作業が多くコア業務に時間を割けない
- 4.4.業務工数を把握できていない
- 5.店舗オペレーションの改善方法
- 5.1.ムダな業務を減らす
- 5.2.ムリのある業務を減らす
- 5.3.作業や成果のムラをなくす
- 6.店舗オペレーション改善の具体的なステップ
- 6.1.実際の業務を調査する
- 6.2.現場のスタッフから意見を聞く
- 6.3.課題点・改善点を見つける
- 6.4.運用の改善・ツール導入をする
- 6.5.施策の振り返り・改善をする
- 7.店舗オペレーションを効率化させるなら「店舗matic」!
- 8.まとめ
店舗の日々の業務を支えるのが「店舗オペレーション」です。接客や在庫管理、売上報告などの基本的な作業から、トラブル対応やサービス品質の維持まで幅広い役割を担っています。しかし現場では、人員不足や情報共有の遅れなど課題も多く、改善しなければ効率や売上に影響します。本記事では、店舗オペレーションの基本や具体的な業務、よくある課題と改善のステップを解説し、効率化を実現するツール「店舗matic」についても紹介します。
店舗オペレーションとは
店舗オペレーションとは、店舗を円滑に運営するために日々行われる一連の業務を指します。接客やレジ対応、商品の補充、在庫管理、売上報告など、店舗を運営するための基本的な作業はすべてオペレーションに含まれます。飲食店であればキッチンでの調理や仕込み、小売業であれば商品陳列や発注作業なども該当します。店舗オペレーションがスムーズであればあるほど、顧客にとって快適なサービスが提供でき、従業員にとっても働きやすい環境が整います。そのため、日々の業務効率を高め、標準化していくことが店舗運営の成否を分ける重要なポイントとなります。
店舗オペレーションはなぜ必要?
店舗オペレーションは単なるルーティン作業ではなく、店舗の品質や売上、スタッフの働きやすさに直結する重要な仕組みです。ここでは、その必要性を4つの観点から見ていきましょう。
サービス品質の向上のため
店舗オペレーションを整える最大の目的の一つは、サービスの品質を安定的に高めることです。接客方法や商品提供の手順を標準化すれば、誰が対応しても同じ水準のサービスを提供できます。これにより、顧客は安心感を得られ、リピート率の向上につながります。特に複数のスタッフが交代で勤務する店舗では、オペレーションが統一されていないと対応にばらつきが生じ、顧客満足度を損なう原因になります。逆に、マニュアルやルールがしっかり整備されていれば、新人スタッフでもスムーズに業務をこなせるため、教育コストの削減にもつながります。
売上拡大のため
売上拡大を目指すうえでも店舗オペレーションは欠かせません。たとえば、在庫補充や発注のルールが徹底されていれば、人気商品が品切れになるリスクを減らせます。また、繁忙期やキャンペーン時には通常より多くの業務が発生しますが、オペレーションが整理されていれば効率的に人員配置を行え、販売機会を逃さずに売上を最大化できます。さらに、接客から会計までの流れをスムーズにすることは、顧客の回転率を高め、結果的に売上アップに直結します。
トラブル対応のため
店舗では、クレームや機器の故障、急な欠員など、予期せぬトラブルが日常的に発生します。こうした場面でオペレーションが整っていれば、スタッフが慌てることなく迅速に対応できます。たとえば、クレーム対応のマニュアルがあれば、顧客への謝罪や上長への報告フローをスムーズに実行でき、被害を最小限に抑えることが可能です。
さらに、トラブル発生時の記録を残して共有すれば、再発防止策を講じることもでき、店舗全体の安定性を高めることにつながります。
業務の効率化のため
店舗オペレーションの整備は、業務の効率化を実現するためにも不可欠です。作業手順が明確になっていれば、無駄な動きや二重作業を減らすことができ、限られた時間でより多くの顧客にサービスを提供できます。また、誰がどの業務を担当するかを明確にすることで、責任の所在がはっきりし、業務の抜け漏れ防止にもつながります。
効率的なオペレーションはスタッフの負担軽減にも直結し、結果として離職率の低下や人材定着にも効果を発揮します。
店舗オペレーションの具体的な業務
店舗オペレーションは、店舗が日常的に回っていくために欠かせない基盤業務です。どの業界・業態でも共通する部分がありますが、業種によって重点が異なります。ここでは代表的な業務内容を紹介します。
接客
接客は店舗オペレーションの中心であり、顧客満足度を左右する最も重要な業務です。来店時のあいさつから商品説明、会計、退店時のフォローに至るまで、一連の対応が顧客の印象を決めます。接客オペレーションが整っていれば、誰が対応しても一定の品質を保つことができ、クレームの防止やリピート率向上につながります。また、顧客の声を吸い上げて本部や店舗運営に反映する役割も担っています。
在庫・売り上げ管理
在庫や売上の管理は、利益を確保するうえで欠かせないオペレーションです。発注や補充を適切に行うことで欠品や過剰在庫を防ぎ、販売機会を逃さないようにします。また、売上データを正確に記録し、日次・週次・月次での報告を行うことは、本部や経営側が店舗の現状を把握するために重要です。数値管理を徹底することは、戦略的な店舗運営の基盤ともいえます。
本部連絡
チェーン展開を行っている店舗では、本部からの指示や情報を正しく理解し、現場に落とし込むことが不可欠です。キャンペーン内容の共有や販促ツールの設置方法、店舗ごとの実施状況の報告などが代表的な業務です。情報伝達が遅れたり曖昧だったりすると、顧客対応の質にばらつきが出てしまうため、効率的で正確な本部連絡体制を整えることが求められます。
キッチン業務
飲食業界におけるキッチン業務は、商品の品質を保ちながらスピーディに提供するための要となります。仕込みや調理、衛生管理、提供スピードの調整など、多くの作業が含まれます。さらに、バックヤードでの業務効率がフロアの回転率に直結するため、調理フローやオペレーションの改善は売上に大きな影響を与えます。近年ではセントラルキッチン方式の導入や、調理工程を簡略化する仕組みも広がっており、効率的なキッチンオペレーションの重要性はますます高まっています。
店舗オペレーションのよくある課題

店舗オペレーションは、店舗の安定運営に欠かせない業務ですが、現場ではさまざまな課題に直面しています。ここでは多くの店舗に共通する代表的な課題を整理します。
本部指示がうまく伝わらない
チェーン店舗では、本部からのキャンペーン情報や施策が現場に正しく伝わらないケースが少なくありません。メールや紙での連絡に頼っていると、情報が埋もれたり、スタッフに共有されるまでに時間がかかったりすることがあります。その結果、店舗ごとに対応がバラつき、顧客へのサービスにも差が出てしまいます。特に短期間で実施する販促施策では、情報伝達の遅れが売上機会の損失につながるため、大きな課題となります。
人員不足で一人の業務量が多い
慢性的な人手不足は多くの業界で問題となっており、限られたスタッフに過剰な業務負担がかかることがあります。本来であれば複数人で分担する作業を一人でこなさなければならず、接客や調理などコア業務に集中できない状況が生まれます。これが続くとサービス品質の低下やスタッフのモチベーション低下、さらには離職率の上昇につながる恐れもあります。
事務作業が多くコア業務に時間を割けない
日報の作成や売上報告、シフト調整、本部への報告など、事務作業は店舗運営に不可欠ですが、現場スタッフの大きな負担にもなっています。特に紙やエクセルでの管理に依存していると、入力や集計に多くの時間を取られ、接客や売場改善といった本来のコア業務に十分な時間を割けなくなります。結果として、顧客体験の向上に必要な取り組みが後回しになるケースも少なくありません。
業務工数を把握できていない
日々の業務に追われるなかで、それぞれの作業にどれだけの時間がかかっているのかを正しく把握できていない店舗も少なくありません。工数が見えていないと、業務のムダや改善点を発見できず、効率化の取り組みも進まないのが実情です。
そのため、各店舗から工数データを収集し、特に負担が大きい業務を特定することが改善の第一歩となります。さらに、店舗ごとの工数を比較すれば「効率的に業務を進められている店舗」を見つけ出せるため、その店舗のオペレーションを調査してマニュアル化し、全体に展開することで効率化を実現できます。
実際に、ある企業では業務指示の実施報告と同時に作業時間も記録させ、工数の「見える化」と改善に成功した事例があります。店舗maticにも「作業工数報告」機能があり、同様にデータ収集と改善につなげている企業が増えています。
店舗maticの機能については、以下のページでご確認いただけます。
機能紹介|店舗間コミュニケーションの悩みをツール・アプリで解決【株式会社ネクスウェイ】
店舗オペレーションの改善方法
店舗オペレーションは日々の業務を支える大切な仕組みですが、現場に負担がかかりすぎると効率が落ち、サービス品質や売上にも悪影響を与えます。そのため、改善の視点を持ち、ムダ・ムリ・ムラを取り除くことが重要です。ここでは代表的な改善方法を解説します。
ムダな業務を減らす
店舗オペレーションの中には、顧客満足や売上に直結しない「ムダな業務」が存在します。たとえば、同じ情報を紙とデータの両方で管理していたり、複数のフォーマットに同じ内容を転記したりするケースです。こうした作業は効率を下げる原因となり、スタッフの時間を奪います。業務の流れを見直し、自動化ツールや一元管理システムを導入することで、不要な作業を減らし、コア業務に集中できる環境を作ることが大切です。
ムリのある業務を減らす
限られた人員で多くの業務を抱えていると、スタッフ一人ひとりに過剰な負担がかかります。これが「ムリのある業務」となり、サービス品質の低下や離職につながります。改善のためには、作業を分担できる仕組みやサポート体制を整えることが必要です。また、繁忙期やイベント時には人員配置を柔軟に調整し、過剰労働を避けることが重要です。業務フローを可視化すれば、どこに負担が集中しているかを把握でき、改善につなげやすくなります。
作業や成果のムラをなくす
オペレーションが標準化されていないと、スタッフごとに作業品質や成果にばらつきが出てしまいます。これが「ムラ」であり、顧客にとっては店舗の信頼性を損なう要因になります。マニュアルの整備や研修体制の強化、定期的なフィードバックを通じて、作業手順を統一することが改善の第一歩です。さらに、チェックリストやタスク管理ツールを活用すれば、誰が担当しても一定の水準を保ちやすくなります。
店舗オペレーション改善の具体的なステップ

店舗オペレーションの改善は、一度の取り組みで完結するものではなく、調査から改善・検証までを繰り返すプロセスが必要です。ここでは、実際に改善を進めるための具体的なステップを紹介します。
実際の業務を調査する
まずは現場で行われている業務を細かく洗い出すことから始めます。業務の流れや所要時間、担当者などを記録し、どの作業に負担が集中しているのかを明確にします。実態を把握しなければ改善策は立てられないため、調査は最初の重要なステップです。
現場のスタッフから意見を聞く
日々オペレーションを担っているスタッフの意見は、改善に欠かせない貴重な情報源です。管理者だけで判断するのではなく、現場の声をヒアリングすることで、机上では見えない課題を発見できます。スタッフの意見を反映することは、改善施策への納得感を高め、協力を得やすくする効果もあります。
課題点・改善点を見つける
運用の改善・ツール導入をする
課題が明確になったら、実際の改善策を運用に落とし込みます。マニュアルを整備して業務の標準化を図る、業務を効率化できるツールを導入するなど、具体的な施策を実行します。特に情報共有やタスク管理はツール導入による効果が大きく、現場の負担を大幅に軽減できます。
施策の振り返り・改善をする
改善策を実行したら、効果を振り返ることが欠かせません。定期的に施策の成果を確認し、うまくいった点と課題を洗い出します。そのうえで次の改善に活かすことで、継続的にオペレーションを進化させることができます。改善は一度で終わりではなく、循環させることで現場に根付き、成果が定着していきます。
店舗オペレーションを効率化させるなら「店舗matic」!
店舗オペレーションの改善を進めるうえで重要なのは、仕組みを整え、現場が迷わず動ける環境をつくることです。その実現に役立つのが、チェーンストア本部と店舗をつなぐ専用ツール「店舗matic」です。情報共有やタスク管理を一元化できるため、現場の負担を減らし、オペレーションの質を大きく高めます。
やることが一目でわかるので無駄を減らせる
店舗maticでは、本部からの指示やタスクが明確に表示され、スタッフが「次に何をすべきか」をすぐに把握できます。従来のように紙のマニュアルやメールを探す手間がなくなり、無駄な時間を削減できます。その結果、現場スタッフは重要な業務に集中でき、効率的に作業を進められます。
マニュアル管理ができて知識のムラを減らせる
新人教育や引き継ぎの際に役立つのが、店舗maticのマニュアル管理機能です。動画や画像を使ったマニュアルを共有できるため、誰でも同じ基準で業務を学べます。スタッフごとのスキル差による「作業のムラ」を減らし、サービス品質を均一化することが可能です。教育コスト削減にも効果を発揮します。
本部からの指示がわかりやすく、実施状況も確認できる
従来は本部からの指示が複数の媒体に分散し、現場での理解や対応にばらつきが出やすい状況でした。店舗maticなら、すべての指示を一元化してわかりやすく伝達できます。さらに、実施状況を本部がリアルタイムで確認できるため、進捗管理やフォローもスムーズです。これにより、全店舗での施策実行力を高め、オペレーションを統一的に進められます。
まとめ
店舗オペレーションは、接客や在庫管理といった日々の基本業務から、売上拡大やサービス品質の維持まで、店舗運営を支える重要な仕組みです。しかし現場では、人員不足や情報共有の不十分さ、事務作業の負担など、多くの課題を抱えています。
改善のためには、ムダ・ムリ・ムラを減らし、業務を標準化することが欠かせません。そのうえで、業務の調査やスタッフの意見収集、改善点の特定からツール導入、そして振り返りまでを一連の流れとして実践することが効果的です。
特に「店舗matic」を活用すれば、情報共有やマニュアル管理、進捗確認を一元化でき、現場の負担を大きく軽減できます。店舗オペレーションを効率化し、サービス品質と売上の両立を実現するために、ぜひ導入を検討してみてください。
オペレーション見直しや業務効率化についてお悩みがございましたらお気軽にご相談ください