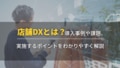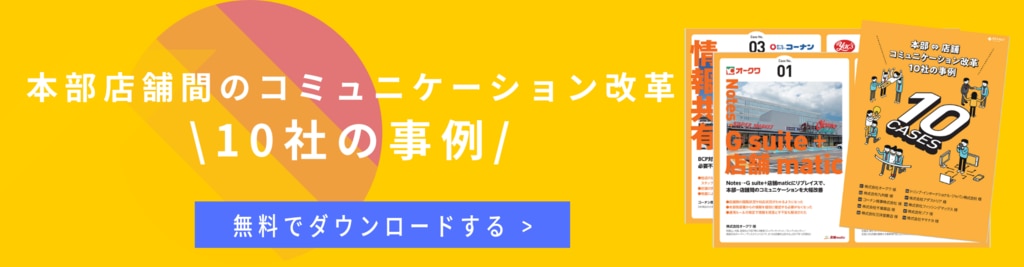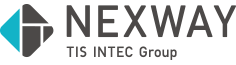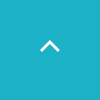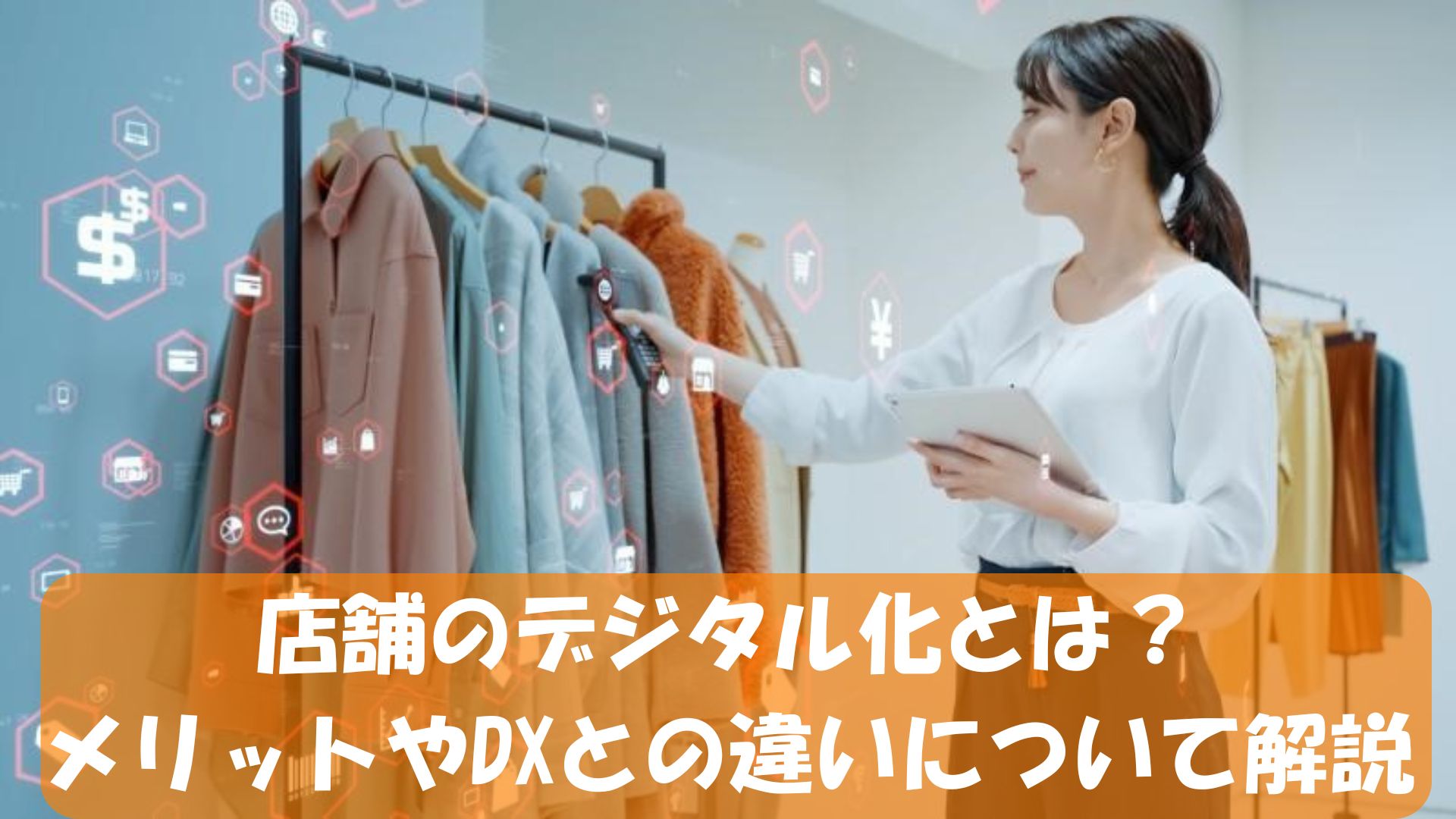
店舗のデジタル化とは?メリットやDXとの違いについて解説
目次[非表示]
- 1.店舗のデジタル化とは?
- 2.店舗DXとの違い
- 3.店舗のデジタル化を進めるメリット
- 4.店舗のデジタル化を進める際のデメリットと対策
- 5.はじめは「タスク管理」をデジタル化することがおすすめ
- 6.店舗デジタル化の事例
- 6.1.株式会社大創産業様の事例
- 6.2.イオン東北株式会社様の事例
- 6.3.株式会社チュチュアンナ様の事例
- 7.店舗のデジタル化の効果を高めるポイント
- 7.1.現場の負担にならない導入設計が必要
- 7.2.費用対効果を見極めたうえで導入する
- 7.3.導入目的や活用方法をスタッフと共有する
- 7.4.デジタル化して終わりではなく、継続的に改善をする
- 7.5.ツールに業務を合わせる柔軟性が、成功のカギを握る
- 8.コミュニケーションツールを活用し店舗デジタル化を進めよう
- 9.まとめ
店舗運営において、メール・チャット・電話・紙の書類など、さまざまな連絡手段が併用されている現場は少なくありません。
しかし、ツールが増えすぎた結果、指示や連絡の確認作業に追われ、本来の業務が圧迫されるという課題も顕在化しています。
今求められているのは、情報を一元化し、現場と本部がスムーズに連携できる仕組みです。本記事では、そうした背景を踏まえ、「店舗のデジタル化」とは何か、店舗DXとの違いや導入メリット、具体的な進め方について事例を交えて解説します。
店舗のデジタル化とは?
店舗のデジタル化とは、これまで紙や口頭で行っていた業務やコミュニケーションを、デジタルツールやITシステムを用いて効率化・可視化する取り組みを指します。たとえば、掲示板での情報共有をアプリに移行したり、手書きのチェックリストをデジタルで管理したりすることで、作業の抜け漏れを防ぎ、業務のスピードや精度を向上させることが可能です。
近年では、少子高齢化による人手不足、店舗間の連携不足、業務属人化など、多くの課題に直面する中で、デジタル化は避けては通れない経営課題のひとつになっています。特に多店舗を展開するチェーンストアにおいては、本部と店舗、店舗間の情報連携の質が業績に直結するケースも少なくありません。そのため、現場に負担をかけずに導入できる“スモールスタート”なデジタル化のニーズが高まっています。次のセクションでは、店舗DXとの違いについて解説します。
店舗DXとの違い
「店舗のデジタル化」と「店舗DX(デジタルトランスフォーメーション)」は似ているようで、目指すゴールや取り組みの範囲に違いがあります。
店舗のデジタル化は、あくまで業務の一部をITやツールで効率化することが中心です。たとえば、紙の業務連絡をチャットアプリに置き換える、Excelでの集計作業をクラウドで自動化する、といった取り組みが該当します。目的は、現行業務の「効率化」「省力化」です。
一方、店舗DXは、デジタル技術を活用して業務やサービス、ビジネスモデルそのものを抜本的に変革することを意味します。たとえば、AIによる売上予測を基に発注フローを自動化したり、デジタルサイネージやアプリを活用した顧客体験の再設計などが該当します。
つまり、店舗のデジタル化はDXへの第一歩であり、DXはそれをさらに発展させた包括的な変革といえるでしょう。どちらも重要ですが、最初のステップとして無理なく始められる「店舗のデジタル化」から着手するのが現実的です。
店舗のデジタル化を進めるメリット
デジタル化によって得られる恩恵は多岐にわたります。ここでは、店舗運営において特に大きな効果をもたらす4つのメリットについて解説します。
業務効率が向上し、人手不足の課題を解消できる
紙の帳票や口頭での指示など、アナログな業務は時間も手間もかかり、ヒューマンエラーも起こりやすくなります。デジタルツールを導入することで、タスクの可視化や進捗の一元管理が可能となり、作業効率が大幅に向上します。結果として、限られた人員でもスムーズに業務を回すことができるようになり、人手不足の影響を最小限に抑えられるようになります。
顧客満足度の向上につながる
業務効率が高まることで、スタッフが顧客対応に割ける時間や余裕が生まれます。また、店舗間の情報共有やサービス品質の統一にもつながるため、どの店舗を訪れても一定以上のサービスが受けられるという安心感を提供できます。こうした環境は、結果として顧客満足度の向上につながります。
店舗ごとの業務のばらつきを減らせる
アナログな運用では、店舗ごとに作業のやり方や業務の精度が異なりがちです。デジタルツールを活用すれば、業務手順をフォーマット化し、本部から統一的な指示を出すことが可能になります。これにより、属人的な業務を減らし、全店舗で安定した運営を実現しやすくなります。
多店舗展開における本部管理の手間が軽減される
デジタル化により、店舗からの報告や確認がリアルタイムで可視化されるようになるため、本部は現場の状況を把握しやすくなります。従来のように電話やFAXで逐一やり取りする必要がなくなり、本部側の管理工数や確認作業も大幅に削減できます。店舗数が増えるほどに、こうしたメリットは大きくなります。
店舗のデジタル化を進める際のデメリットと対策

デジタル化には多くのメリットがある一方で、導入段階や運用において課題が発生することもあります。ここでは、現場で起こりやすい3つのデメリットと、その対策についてご紹介します。
スタッフのITリテラシーによって浸透に時間がかかる
新しいツールやシステムを導入しても、すべてのスタッフがすぐに使いこなせるとは限りません。特にITに苦手意識のあるスタッフが多い店舗では、運用が定着するまでに時間がかかる可能性があります。
この課題に対しては、導入前後の丁寧なレクチャーやマニュアルの整備が有効です。また、既存の業務と似た操作感をもつツールを選ぶことで、現場での混乱を抑えやすくなります。テスト運用やトライアル期間を設けるのも効果的です。
セキュリティやデータ管理の手間が増える
業務がデジタル化されると、店舗で扱う情報の多くがクラウドやネットワーク上に保存されるようになります。その分、データ漏えいや情報の不正アクセスなど、セキュリティリスクにも目を向けなければなりません。
この対策としては、セキュリティ対策が万全なシステムを選ぶことが大前提です。情報へのアクセス権限を制限できる機能や、ログの取得機能などが備わっているかを確認しましょう。また、現場の負担を最小限にするため、必要最低限の入力やデータ管理で済むツールを選定することも重要です。
業務が増えてしまう・複雑になってしまうことも
「便利になるはずだったのに、作業が増えた」といった声が上がることもあります。これは、既存業務との整合性が取れていないままツールを導入してしまったことが原因である場合が多いです。
このような問題を防ぐには、導入前に現場の業務フローを正確に把握し、現場の声を取り入れながら設計することが不可欠です。また、店舗ごとの事情やリソースを加味して段階的に導入することも、スムーズな運用に繋がります。現場と本部の相互理解が、デジタル化成功の鍵となります。
はじめは「タスク管理」をデジタル化することがおすすめ
店舗のデジタル化を進める際、最初のステップとして「タスク管理」から着手することをおすすめします。これは、単なる業務効率化ではなく、店舗における本部指示の管理や実行における“負担”そのものを軽減するための重要な取り組みです。
たとえば現在、弊社が店舗maticを導入している企業様を対象に実施したアンケート(7社・1078店舗/有効回答最大1403件)では、「本部からの指示内容に管理漏れや抜けが発生している」と回答した店舗スタッフが64%に上りました。
さらに、「メールや指示確認作業が、本来業務を圧迫している」と感じているスタッフも60%を超えており、タスクの受け取りと管理が現場の大きな負担になっていることがわかります。
このように、店舗における「指示連絡の管理」と「実行のフォロー」は、業務上の重要課題です。LINEやメールなどで連絡を受けていても、それが「タスク」として可視化されておらず、完了状況の確認や抜け漏れの発見が困難になっているケースも少なくありません。
だからこそ、まずは「タスク管理」をデジタル化することが、現場にとって最も効果的な第一歩になります。業務指示がそのままタスク化され、進捗状況や未実施の項目が明確になることで、本部も店舗も「指示した/された」のその先まで見えるようになります。
現場にとって課題感が大きい領域でありながら、導入のハードルは比較的低く、専用デバイスの配布や複雑なシステム連携が不要な点も、タスク管理デジタル化の取り組みやすさにつながっています。
ただし、コミュニケーションツールの導入は全社に関わるものであるため、スムーズな定着には事前の準備や運用ルールの整備、導入後の支援が不可欠です。
店舗デジタル化の事例
店舗のデジタル化は、単なる理論ではなく、実際に多くの企業が導入し成果を上げている取り組みです。ここでは、実際に「店舗matic」を活用し、業務の効率化や、本部・店舗間の連携改善を実現した企業の事例をご紹介します。
株式会社大創産業様の事例
100円ショップ「ダイソー」を主に、国内外5000店以上の出店実績を持つ株式会社大創産業様。これまでは複数のコミュニケーションツールが混在し、本部・SV・店舗間の連携が煩雑化。タスクの優先順位が不明瞭なうえ、回答の遅れや漏れが頻発するなど、コミュニケーションコストが大きな課題となっていました。
こうした状況を受けて同社が導入したのが、「店舗matic」です。
情報の一元管理と指示の標準化により、店舗の作業実行性が向上。本部では回答管理が効率化され、無駄な指示を半年で500件削減するなど、定量・定性的に効果が現れています。さらに、機能に沿った業務プロセスの整備や、第三者チェック「ゲートキーパー」制度の導入により、運用レベルでの精度向上も実現しました。
詳しい事例は、以下からご確認いただけます。
イオン東北株式会社様の事例
イオン東北株式会社は、東北6県で「イオン」「マックスバリュ」などを展開する総合小売企業です。店舗運営の効率化を目指し、「店舗matic」を導入。1日100件以上のメールに埋もれていた本部からの指示が整理され、優先度や締切が一目で把握できるようになりました。
本部では宛先管理やメーリングリスト更新の手間が削減され、店舗では情報の見落としが減少。カレンダーやアンケート機能の活用により、部署間連携や人時効率も向上しました。今後はすべての本部-店舗間連絡を「店舗matic」に集約し、スマートストアの実現を加速していく方針です。
詳しい事例は、以下からご確認いただけます。
【イオン東北株式会社様】 人時効率改善を狙い157店舗と本部間の連絡を一元化 スマートストア実現に向けたDXを大きく前進
株式会社チュチュアンナ様の事例
株式会社チュチュアンナは、全国に500店舗以上を展開するアパレル小売企業です。本部からの指示に対する店舗側の対応状況が把握できず、コミュニケーション効率に課題を抱えていました。指示の実行率が低い理由も不明確で、内容の分かりづらさが原因かどうかすら判断できない状況だったといいます。
この課題を解決するために導入されたのが「店舗matic」です。指示や情報の発信元・内容・対応状況が一元的に管理できるようになり、本部と店舗間の連携が大幅に改善。さらに、写真付き報告書を簡単に共有できる「売場ノート」機能により、店舗側の報告業務も軽減されました。店舗数が急増する中でも、確実でスムーズな情報共有を実現する基盤となっています。
詳しい事例は以下からご確認いただけます。
導入事例|店舗間コミュニケーションの悩みをツール・アプリで解決【株式会社ネクスウェイ】【株式会社チュチュアンナ様】
店舗のデジタル化の効果を高めるポイント
せっかくデジタル化に取り組むのであれば、現場の負担を最小限に抑えながら、最大限の効果を引き出したいものです。ここでは、デジタル化の導入効果を高めるために意識しておきたい5つのポイントを紹介します。
現場の負担にならない導入設計が必要
どんなに優れたツールであっても、現場にとって使いにくければ定着しません。特に業務が多忙な店舗スタッフにとっては、新たなツールの操作を覚えること自体がストレスになる場合もあります。だからこそ、導入時にはレクチャーの時間を確保したり、既存の業務と近い操作性のツールを選んだりするなど、現場目線での設計が不可欠です。初期段階では使う機能を絞ってスタートするのも、スムーズな運用につながります。
費用対効果を見極めたうえで導入する
導入にかかるコストは決して安くありません。そのため、「何にどれだけの費用がかかり、どのような成果が見込めるのか」を事前に見極めておくことが重要です。コストだけでなく、導入後に得られる工数削減や業務精度の向上といった“効果”を定量的に試算し、中長期的な視点で判断することが求められます。安価なツールでも現場に合っていなければ意味がなく、逆にある程度コストをかけても、現場にしっかり定着すれば十分に回収可能です。
導入目的や活用方法をスタッフと共有する
「なぜこのツールを使うのか」「何を改善したいのか」といった導入の目的を、スタッフ全員としっかり共有することが、デジタル化を成功させるうえでの鍵になります。現場の理解や納得がないまま導入してしまうと、「また新しいことが増えた」という反発につながりかねません。導入前から定期的な説明やミーティングを通じて、スタッフの疑問や不安を解消し、チームとして目的意識を持って取り組むことが大切です。
デジタル化して終わりではなく、継続的に改善をする
デジタル化は“導入して終わり”ではありません。実際の運用が始まってからこそ、本当の意味での改善フェーズがスタートします。現場の声をもとに運用ルールを見直したり、使い方をブラッシュアップしたりすることで、ツールの活用度合いや効果も大きく変わります。また、定期的に振り返りの機会を設け、改善点や成功事例を全体で共有することにより、デジタル化の取り組みを組織全体の資産として育てていくことが可能です。
ツールに業務を合わせる柔軟性が、成功のカギを握る
ツールによるデジタル化を成功させるためには、「今の業務にツールを合わせる」のではなく、「ツールに業務を合わせる」という発想が重要です。特にパッケージ型のツールは、すべての機能が現行業務に完全に合致するとは限らず、要望があっても即時に機能改善が行われるわけではありません。だからこそ、ツールを起点に運用そのものを見直す柔軟な姿勢が求められます。現状のやり方にこだわるのではなく、ツールを最大限に活かすにはどうすればよいかを考え、必要であれば業務そのものを改革していく覚悟が、最終的な効率化の成否を左右します。
コミュニケーションツールを活用し店舗デジタル化を進めよう

店舗のデジタル化を着実に進めるには、業務の核となる「コミュニケーション」部分の見直しが欠かせません。なかでも、指示の伝達やタスクの進捗管理といった業務は、各店舗のパフォーマンスやブランド全体の品質に直結する重要な領域です。
実際、私たちが行ったアンケートでは、64%の店舗スタッフが「本部からの指示に管理漏れ・忘れがある」と回答しています。また、メールや口頭での指示確認作業が本来業務を圧迫しているという声も多く、情報共有の非効率さが現場の生産性を下げているという実態が明らかになっています。
こうした課題を解決する手段として有効なのが、タスク管理機能を備えたコミュニケーションツールの導入です。たとえば、指示を「見える化」し、実行状況をリアルタイムで把握できる仕組みを整えることで、業務の抜け漏れや重複を防ぐとともに、本部と店舗の距離感も縮まります。
また、スマートフォンやタブレットでも使えるUIを備えていれば、現場スタッフのITリテラシーに関係なく、スムーズに導入・運用することが可能です。デジタル化への第一歩として、こうしたツールの活用から始めてみるのが現実的かつ効果的なアプローチといえるでしょう。
まとめ
店舗のデジタル化は、単なる「業務効率化」ではなく、チェーンストア本部と各店舗の連携力を高め、現場の課題を根本から解決する手段です。特に、タスク管理や指示伝達といったコミュニケーション領域の見直しは、即効性のある改善につながりやすく、デジタル化の入り口として最適です。
ただし、導入には現場の声を聞いたうえでの設計や、継続的な改善の姿勢が欠かせません。初期導入の手間を最小限に抑えつつ、定着・効果の最大化を目指すには、シンプルで使いやすいコミュニケーションツールの導入が鍵となります。
「まずはできることから、確実に」。その第一歩として、店舗maticのようなツールを活用し、現場と本部が連携しやすい仕組みづくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。