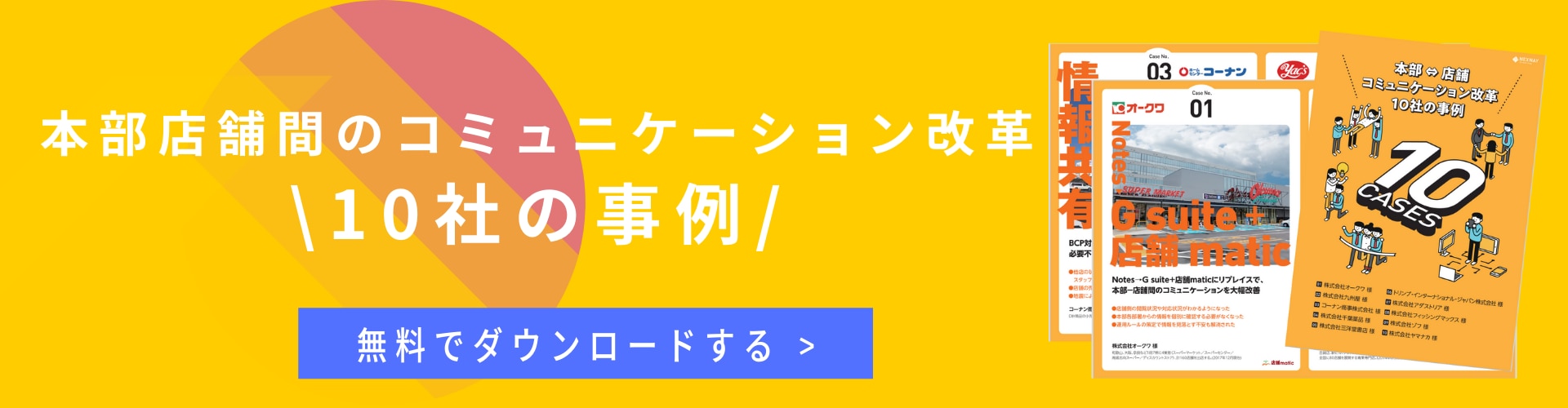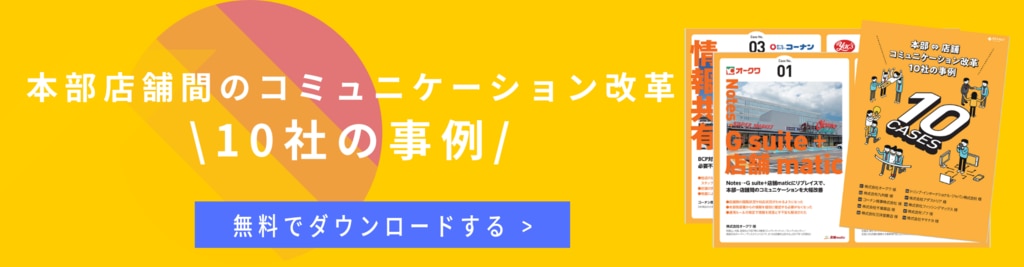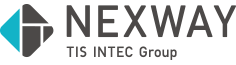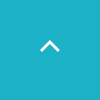店舗管理とは?業務内容や課題・効率化させる方法を解説
スーパーマーケットをはじめとする小売業では、日々の業務が多岐にわたるため、効率的な店舗管理が求められます。商品管理や売り場づくり、顧客対応に加え、人材管理や情報共有の仕組みを整えることが不可欠です。
しかし、多くの企業では本部と店舗間の連携がスムーズにいかない、管理業務が煩雑になりすぎるといった課題を抱えています。
本記事では、店舗管理の基本から、具体的な業務内容、現場が直面する課題、そして効率化の方法について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.そもそも店舗管理とは?
- 2.店舗管理に関する店舗側の課題とは
- 3.店舗管理に関する本部側の課題とは
- 3.1.店舗への指示が伝わっているか確認できない
- 3.2.売り場づくりのイメージを伝えにくい
- 3.3.臨店の時間・人材の確保ができない
- 4.店舗管理業務を効率化させるには?
- 4.1.1.現状の課題を把握する
- 4.2.2.目標を明確にする
- 4.3.3.マニュアルを作成する
- 4.4.4.システム導入を検討する
- 5.小売業におすすめの店舗管理ツール
- 6.まとめ
そもそも店舗管理とは?
店舗管理とは、店舗責任者が店舗を円滑に運営するために実施する管理業務です。具体的には、商品管理、売り場管理、情報管理などが含まれます。小売業全般において、扱う商品や規模に応じて管理すべき要素は異なりますが、適切な管理が売上向上や業務効率化につながります。
特にチェーンストアでは、店舗・本部間の連携も重要です。店舗と本部のコミュニケーションに問題があるとスムーズな店舗運営ができません。
顧客対応管理
顧客対応管理は、小売業全般において重要な業務です。具体的には、接客、クレーム対応、地域ニーズの把握などが含まれます。チェーンストアでは、接客マニュアルの管理も重要です。親切でどのお店でも気持ちの良い接客を提供できればブランド力が上がり、顧客の安心感・満足度も向上します。
良い顧客対応が適切に評価される仕組みづくりや、クレームやヒヤリハットなどのトラブルを共有して接客マニュアルを定期的に見直すことも求められます。
売り場管理
売り場管理とは、商品を陳列し売れる売場を展開することです。具体的には、陳列棚の整理整頓や値札管理、POP作成・掲示、商品の補充などが含まれます。照明の明るさや清潔感、魅力的なディスプレイも重要です。売り場管理の良し悪しは、売上に大きく影響します。
バックヤード・施設管理
バックヤードや施設を安全・衛生的に管理する業務です。自動ドアや玄関マット、通路、トイレ、カートなど、顧客の目に触れる施設や備品をこまめにチェックして、清潔・安全に保ちます。
バックヤードの整理整頓や清掃、不用品の処分なども重要な業務です。バックヤードが片付いていないなどの不十分な管理では、在庫のずれが起きたり思わぬトラブルにもつながり信用問題に発展しかねないため、気を抜けません。
商品管理
商品の仕入や在庫を管理する業務です。売上を随時チェックしてタイムリーに発注・仕入を行い、必要な商品を過不足なくそろえます。
品質管理、賞味期限のチェックも重要です。スーパーマーケットや小売業は扱う品目が多いため、商品管理が複雑化するケースが珍しくありません。ECサイトとリアル店舗の両方を運営している場合などでは、商品管理の難易度がさらに上がります。適切な商品管理を行うことで、無駄な在庫を減らし、顧客のニーズに迅速に対応できる店舗運営が可能になります。
組織・作業管理
組織を円滑に運営するためのマネジメント業務です。重要事項の伝達、目標確認、業績評価はもとより、スタッフへの作業指示、作業割当、作業方法の改善、OJTなども含まれます。
店舗には本部からの指示や連絡が頻繁に届くため、情報を的確に把握して必要な作業を漏れなく行う必要があります。
情報管理
商品ごとの売上や在庫の状況、売価、売れ筋商品、客数、顧客ニーズなどの情報を管理する業務です。パソコン業務がメインで、日報・報告書の作成、伝票・日割り予算の入力、本部・現場スタッフとの報連相などが含まれます。情報量が多いと担当者の負担になりやすく、売場に立てないなどの弊害も珍しくありません。
予実管理
売上の目標(予算)と実績を管理する業務です。日々の売上やコスト、ロスの原因などを分析して、業績アップにつながる企画・施策を考えます。
小売業では、店舗全体の売上だけでなく、商品カテゴリーや部門ごとの売上チェックも重要です。天候や地域のイベントなども客足に影響するため、こまめな情報収集とデータ管理が求められます。
人事・労務管理
人材に関する管理業務です。具体的には、勤怠管理や給与管理、シフト管理、人材採用などが含まれます。
小売業では、多様な雇用形態のスタッフが働いており、それぞれの勤務状況を適切に管理することが求められます。
また、日本の労働力不足が深刻化する中、離職を防ぎ、安定した店舗運営を行うためには、スタッフのスキル向上やモチベーション維持の取り組みが欠かせません。研修制度の充実、適切な評価制度の導入、働きやすい職場環境の整備などを通じて、人材の定着を図ることが重要です。
店舗管理に関する店舗側の課題とは

店舗運営において、管理業務の負担が大きすぎると、本来優先すべき業務に十分な時間を確保できなくなります。特に予実管理や顧客対応など、売上や顧客満足度に直結する業務への時間を捻出することが難しくなり、多くの店長が課題として感じています。ここでは、具体的な課題を整理し、解決策を考えていきます。
メイン業務に取り組む時間が取れない
店舗の運営において、店長やスタッフが最も時間を割くべきなのは、売上向上や顧客満足度の向上につながる業務です。しかし、現状では管理業務が多すぎるため、それらの重要な業務に十分な時間を確保することができません。
株式会社ネクスウェイが2021年に実施した調査によると、店長が業績を向上させるために最も増やしたい業務は「予実管理」であり、66.7%がこの業務にもっと時間を使いたいと回答しています。さらに、「顧客対応」や「情報管理」も上位に挙げられています。この結果からも、管理業務の負担を減らし、より本質的な業務に集中できる環境を整えることが重要だとわかります。
ネクスウェイの詳しい調査結果については以下の資料をご覧ください。
【調査報告】スーパーマーケット本部・店舗間コミュニケーションの現状把握調査2
本部と店舗間のコミュニケーションが取りづらい
本部と店舗間のスムーズなコミュニケーションは、円滑な店舗運営に欠かせません。しかし、情報量が多すぎたり、伝達手段が煩雑であったりすると、情報の見逃しや報告漏れ、作業ミスなどの問題が発生します。本部からの指示が適切に伝わらないことで、現場の対応が遅れたり、業務の進行が滞ったりするケースも少なくありません。
特に多店舗展開をしている企業では、各店舗ごとの状況を正確に把握することが難しく、適切な指示を出せないという課題もあります。このような課題を解決するためには、情報共有の仕組みを見直し、効率的に伝達できるツールの導入や仕組みの整備が求められます。
店長の人材管理・作業管理の負担が重い
人材管理や作業管理は、店舗運営において欠かせない業務ですが、その負担が大きすぎると、店長の負担が過剰になり、全体の業務効率が低下する原因となります。ネクスウェイの調査でも、店長が減らしたい業務として「人事・労務管理」や「組織・作業管理」が挙げられています。これらの業務にかかる負担が大きいほど、売上向上のための業務やスタッフの育成にかける時間が確保しづらくなります。
人材管理や作業管理の負担を軽減するためには、業務の標準化やデジタルツールの活用が有効です。例えば、シフト管理システムや業務管理アプリを活用することで、管理の手間を削減し、店長がより重要な業務に集中できる環境を整えることが可能です。
店舗管理に関する本部側の課題とは
本部は、各店舗の状況を正確に把握し、適切な指示を出すことで売上や業務効率の向上を目指しています。しかし、情報伝達や管理体制に課題があると、指示が適切に伝わらず、現場との連携がうまくいかないケースが発生します。ここでは、本部側が抱える代表的な課題について解説します。
店舗への指示が伝わっているか確認できない
本部から各店舗に業務指示を出しても、その内容が現場で正しく伝わっているかどうかを確認する手段が限られています。特に、メールや紙のマニュアルだけでは、指示が曖昧になったり、スタッフによって解釈が異なったりすることがあります。その結果、業務の進行が遅れたり、指示通りに実施されないケースが発生し、本部の意図が正しく反映されない原因となります。
また、本部の各部署が個別に指示を出している場合、店舗スタッフは情報の優先度を判断しにくく、業務の混乱を招くこともあります。これを防ぐためには、店舗との情報伝達を一元化し、指示の内容を明確にする仕組みの導入が必要です。
売り場づくりのイメージを伝えにくい
店舗での売り場づくりは、売上に直結する重要な要素です。しかし、本部が意図するレイアウトやディスプレイの方針が、店舗スタッフに正しく伝わらないことがよくあります。売り場づくりのイメージを言葉だけで伝えるのは難しく、スタッフの解釈によって意図と異なる形になってしまうことがあるため、再現性の低さが課題となります。
また、売り場の変更指示があった場合、各店舗でどのように実施されたかを本部がリアルタイムで把握するのが難しい点も問題です。このような課題を解決するには、ビジュアルを活用した売り場指示や、店舗からのフィードバックを即座に確認できるツールを導入することが効果的です。
臨店の時間・人材の確保ができない
本部の担当者が各店舗を巡回し、現場の状況を直接確認することは、売上向上や業務改善のために非常に有効です。しかし、全店舗を頻繁に訪問するには多くの時間と人材を確保しなければならず、実際には対応が難しいのが現状です。その結果、現場の課題を十分に把握できず、適切なサポートが行えないケースが発生します。
特に多店舗展開をしている企業では、臨店が十分に行えないことで、各店舗の業務品質にバラつきが生じやすくなります。この課題を解決するためには、リモートでの店舗確認ができる仕組みや、現場からの報告を効率的に集約できるツールを活用することが求められます。
店舗管理業務を効率化させるには?

店舗管理業務の効率化を進めるためには、まず店舗側・本部側の両面から業務の見直しを進める必要があります。具体的な施策を導入する前に、現状の課題を把握し、改善に向けた目標を明確に設定することが大切です。以下では、店舗管理業務を効率化するために必要なステップを詳しく紹介します。
小売業における店舗運営については、以下の記事でも詳しくご確認いただけます。
小売業における店舗運営の課題・解決策やDXを導入する効果を解説
1.現状の課題を把握する
店舗管理業務の効率化にあたって最初に行うべきことは、店舗側・本部側の現状を正確に把握することです。業務内容やフローを細かく洗い出し、どの部分で効率化が妨げられているのか、売上アップの障害となっている要素は何かを明確にします。例えば、「情報処理業務に追われ、売場作りや接客など本来のメイン業務の時間が十分に取れない」といった課題が見つかることがあります。
次に、これらの課題に優先順位をつけ、改善の緊急度や影響の大きさを判断します。
2.目標を明確にする
業務の課題が明確になったら、次に必要なのは具体的な目標設定です。課題を解決した結果、どのような状態を目指すのかを数値として把握できるKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、「人事管理業務を月あたり〇時間削減する」「予実管理に使える時間を○%増やす」といった明確な目標を立てることで、取り組むべき施策が具体化されます。
また、設定したKPIに基づいてPDCAサイクルを迅速に回すことで、施策の効果を確認しながら改善活動を継続的に進められます。これにより、効率化をスピーディに実現できるでしょう。
3.マニュアルを作成する
業務を効率化するためには、スタッフ全員が業務を正しく理解し、均一に実行できる環境を整える必要があります。そのために効果的なのがマニュアルの作成です。マニュアルがあれば、新しいスタッフでも業務内容や手順を簡単に理解でき、作業のバラつきを減らせます。さらに、現場スタッフが判断に迷う時間を削減することにもつながり、店舗全体で業務効率が向上します。
マニュアルは、一度作成したら終わりではなく、常に最新の状態にアップデートすることで業務効率の維持・改善を続けることができます。
4.システム導入を検討する
効率化の施策として最も効果が高いのは、システム導入です。特に店舗管理業務では、業務を一元化できるシステムを導入することで、複雑な情報処理や煩雑な管理業務を軽減できます。システム導入にあたっては、管理業務の負担軽減や効率化につながる課題に特化したツールを選ぶことが重要です。
また、システムの中でも導入に時間がかからないSaaS型のシステムは、店舗管理業務の効率化に最適です。SaaSは導入コストや時間を削減できるうえ、既に確立されたベストプラクティスを活用できるため、現場スタッフが直感的に使いやすく、効果をすぐに実感できます。
小売業におすすめの店舗管理ツール
小売業の店舗管理を効率化するためには、適切なツールの活用が欠かせません。株式会社ネクスウェイが提供するチェーンストア向けの店舗管理ツールは、本部と店舗間のコミュニケーションを円滑にし、業務の効率化をサポートします。
ここでは、特におすすめの2つのツール「店舗matic」と「売場ノート」について紹介します。
店舗matic
「店舗matic」は、本部と店舗をつなぐコミュニケーションツールで、店舗スタッフが主体的に業務を進めやすい環境づくりを支援します。業務の可視化やタスク管理の自動化により、現場の負担を軽減しながら、本部側の指示を的確に伝えることが可能です。
主な機能とメリット
-
店舗スタッフのToDoリストを自動生成
各店舗の業務内容に応じたToDoリストを自動作成し、業務の抜け漏れを防ぎます。 -
本部が指示した作業の進捗状況をリアルタイムに確認
店舗側の対応状況を本部がリアルタイムで把握できるため、適切なタイミングでフォローが可能になります。 -
アンケートやデータの集計機能
店舗スタッフからのフィードバックを効率よく収集し、データに基づいた改善策を講じられます。 -
共用カレンダー機能やワークフロー作成機能
スタッフのシフト管理や業務フローの整理が簡単にでき、日々の業務をスムーズに進められます。
このように「店舗matic」は、業務の効率化だけでなく、スタッフの主体性を引き出し、スムーズな店舗運営をサポートするツールです。
売場ノート
主な機能とメリット
-
スマートフォンで撮影するだけで本部に自動送信
店舗スタッフが売場写真を撮影すると、自動で本部に送信されるため、報告作業が簡単になります。 -
本部担当者が改善ポイントを直接画像に書き込み
売場の改善点を写真上に直接記入できるため、言葉だけでは伝わりにくい指示も、視覚的にわかりやすく伝えられます。 -
売場写真を店舗間で共有
他店舗の成功事例や工夫を共有することで、売場づくりのノウハウを学ぶことができます。 -
催事売場やVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)指示の再現性を向上
本部が指示した売場レイアウトを正確に再現しやすくなり、ブランドイメージの統一にもつながります。
「売場ノート」は、売場の管理をよりシンプルかつ迅速に行うためのツールで、売場づくりの改善に大きく貢献します。
まとめ
店舗管理は業務範囲が広く、日々の業務に追われ、効率化に手が回らないと感じることも少なくありません。もし店舗管理の負担が大きいと感じている場合は、業務の効率化や店舗運営のDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組むことを検討してみましょう。
株式会社ネクスウェイでは、チェーンストア企業が「らしさ」を追求しながらDXを実現できるよう、コミュニケーションの観点から業務改革をサポートしています。本部と店舗の情報共有を円滑にし、売場づくりや臨店業務の課題を解決するためのツールを提供しています。店舗管理の改善をお考えの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
こちらよりお気軽にお問い合わせください