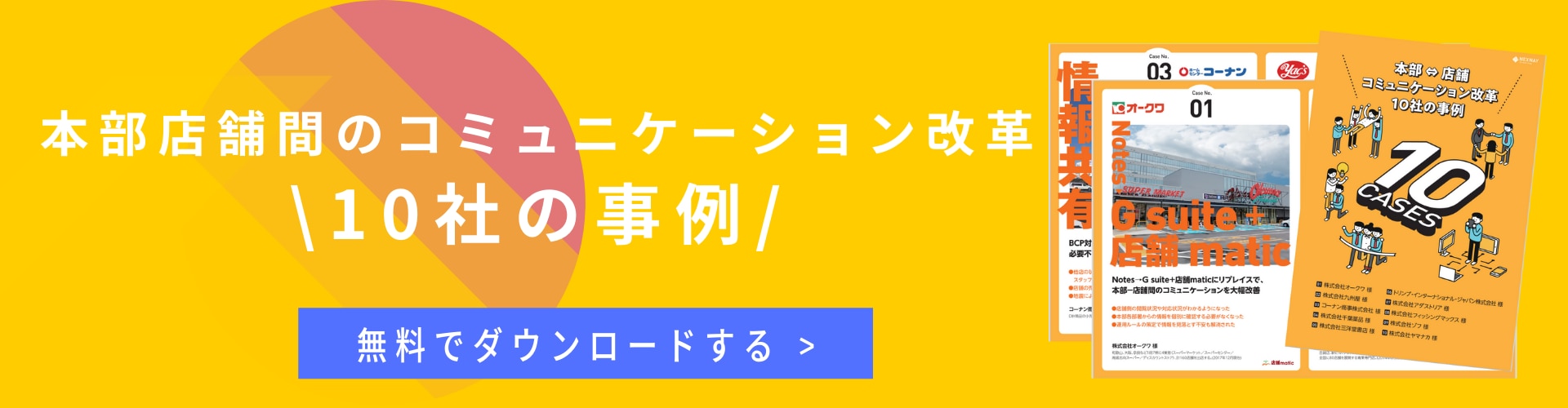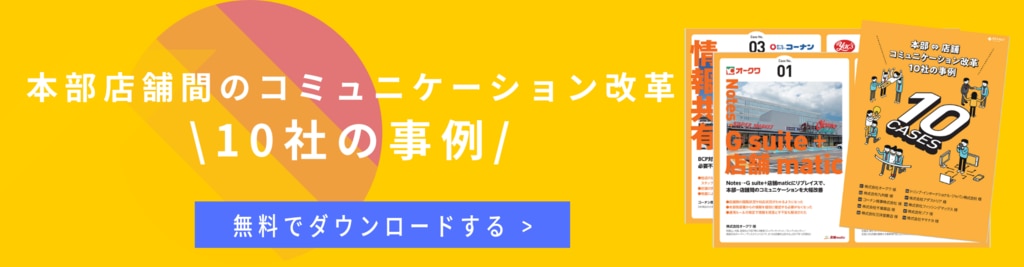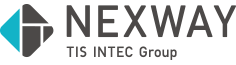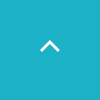VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)とは?基本の考え方と活用法を解説
小売の現場で「最近、ECにお客様が流れている気がする…」「売り場作りまでが回らない…」そう感じたことはありませんか?
そんな今こそ見直したいのがVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)です。VMDとは単なる装飾や陳列方法ではなく、顧客の視覚に訴えるマーケティング手法です。この記事では、店舗運営に欠かせないVMDの基本知識や実装方法を、初心者の方にもわかりやすく解説します。売場の見せ方や商品配置を工夫するだけで、売り上げが変わる。その理由と実践方法を詳しく見ていきましょう。
ネクスウェイでは、VMD報告をスマートフォンやタブレットのアプリから簡単に実施できる機能を備えた「店舗matic」を提供しています。事例共有、売場コンテストでも活用いただいております。詳しくは、下記をご覧ください!
>>店舗maticサービスサイト(売場ノートの機能紹介ページ)
大創産業様やバロックジャパンリミテッド様をはじめとする、店舗maticの導入事例をご確認いただけます。VMD報告に活用いただいているトップバリュコレクション様の事例もぜひご覧下さい。
目次[非表示]
- 1.VMDとは
- 1.1.VMDの具体的な内容
- 1.2.DP(ディスプレイ)との違い
- 1.3.VMDで期待できる効果
- 2.VMDの基本知識|欠かせない3つの要素VP・PP・IP
- 3.VMDを自店で実践する方法
- 3.1.顧客導線を意識した商品配置
- 3.2.計画・実施・分析
- 3.3.スタッフの負担を減らす「ルール化」
- 3.4.社内共有・フィードバック
- 4.【業種別】VMDの実践事例
- 5.ECとの競争・人手不足のこれからの時代に求められる新たなVMDの考え方
- 5.1.ルール化しECやWEBページのブランドイメージを反映させる
- 5.2.店舗ならではの「感情に訴える空間演出」
- 5.3.写真・動画・マニュアルでVMDを共有する仕組みづくりが大切
- 5.4.各店舗のVMDを共有し横展開できる体制づくり
- 6.まとめ|VMDの基本知識を武器に、選ばれる店舗へ
VMDとは
VMDとは、ビジュアルマーチャンダイジング(visual merchandising)を略した言葉です。
日本ビジュアルマーチャンダイジング協会は、ビジュアルマーチャンダイジングを次のように定義しています。
「ビジュアルマーチャンダイジングとは文字どおりマーチャンダイジングの視覚化である。それは企業の独自性を表わし、他企業との差異化をもたらすために、流通の場で商品をはじめすべての視覚的要素を演出し管理する活動である。この活動の基礎になるものがマーチャンダイジングであり、それは企業理念に基づいて決定される。」
視覚的に消費者の感性や感覚に訴求し、購買を促進することを目的としています。また、陳列だけでなく、商品の外装や店舗の内装・什器等の視覚的な要素すべてをコントロールすることで、企業やブランドの世界観を店舗で表現し、その企業らしさを体現する目的もあります。また、売れる導線を設計することもVMDの役割です。
VMDの具体的な内容
VMDとは視覚的に消費者の感性や感覚に訴求する手法です。陳列方法や演出方法などによって、顧客の購買意欲を刺激するマーケティング技法です。
例えば、なんとなく入りやすいお店や、季節感が演出されていてワクワクしてしまうお店などはVMDが効果的に実践されている例です。また店外からみて、ひと目でお店の雰囲気やコンセプトが伝わるお店も、VMDがうまく機能している例といえます。
VMDが実践されているお店では、それぞれの商品が見やすいだけでなく、導線も考えられています。多くの商品を手にとったり見ているうちに、店内の奥まで誘導したり、販売強化商品の前に誘導することが可能です。
DP(ディスプレイ)との違い
VMDとDP(ディスプレイ)の違いがわからないという人も多いでしょう。DPとは、VMDの一部であり商品を見栄えよく魅力的に陳列することを指します。一方、VMDは陳列だけでなくマーケティング活動全般を指します。
VMDでは、どんな人をターゲットとして、どのようにおすすめ商品の前で足を止めてもらうか、店内を見て回ってもらうか、購買意欲を刺激するためにはどんな施策が必要か、など商品の購買につなげるすべての要素を検討しなければいけません。装飾や陳列だけでなく、それらの施策によって売上向上やその企業らしさの表現などを実現することが目的です。つまり、DPはVMDを行うための手段の1つと考えられるでしょう。
VMDのチェックを簡単に!写真共有アプリ「売場ノート」はこちらよりご覧いただけます。
VMDで期待できる効果
VMDを取り入れることでまず期待できるのが、売上アップです。
顧客が店内で商品を見つけやすくなり、気づきやすくなることで、購買機会が自然と増加します。特に視線の高さや照明の明るさなどを工夫することで、主力商品や高利益商品に注目を集めやすくなります。
また、ブランドイメージの向上にも大きく貢献します。VMDによって統一感のある世界観を演出することで、顧客はその店舗に対して「洗練されている」「居心地がいい」といった印象を持ちやすくなります。結果的にリピーターの増加や顧客ロイヤルティの向上にもつながります。
さらに、顧客動線の最適化にも役立ちます。VMDでは人の心理や行動パターンを踏まえてレイアウトを設計するため、来店客が自然に店内を回遊し、複数の商品に触れるように導くことができます。このように、VMDは見た目の美しさだけでなく、購買心理や行動分析を踏まえた「売れる仕組みづくり」として、店舗運営に欠かせない要素となっています。
こちらの記事ではVMDの効果を最大化させる方法を3つのポイントに分けて紹介しています。
>>店舗ディスプレイ・VMDの効果を上げる3つのポイント!
VMDの基本知識|欠かせない3つの要素VP・PP・IP
VMDを考える上で欠かせない要素があります。それは、VP(ビジュアルプレゼンテーション)・PP(ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション)・IP(アイテムプレゼンテーション)の3つです。ここでは、各要素について解説します。
VP(ビジュアルプレゼンテーション)
VPとは、企業のブランドコンセプトやイメージ、季節ごとのテーマや重点商品などをビジュアル的に表現することです。店舗内でもっとも視覚効果の高い場所で行うもので、一般的には店舗の入り口付近の売り場づくりやメインステージなどの売り場づくりに用いられます。
VPはいわば、「店舗の顔」を作るもので、企業やブランドのイメージ、伝えたい世界観などを示すものです。顧客の第一印象を決める重要な要素ともいえるでしょう。顧客を店内に誘導するための導線の役割も果たすので、他店との差別化や魅力的な見せ方が重要となります。
PP(ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション)
PPとは、特定の商品を選んで行われるもので、壁や天井、陳列棚などを利用したアピール方法です。一部のスペースを使って、特に重点的に売上を促進したい「おすすめ商品」を目立たせるような演出をします。おすすめ商品や人気のある商品などが見つけやすくなり、顧客の購買意欲を刺激する効果が見込めるでしょう。
PPは店内をいくつかの区画に分けて、その区画内でもっとも目につきやすく視覚効果の高い場所で行います。スペースごとにピックアップアイテムを選んで演出することで、その区画にどのようなアイテムがあるのかわかりやすくなる、見出しとしての役割もあります。
IP(アイテムプレゼンテーション)
IPとは、アイテムつまり個々の商品をアピールするための手法です。商品がバラバラに陳列されていると、顧客は何がどこにあるのかわからずに、目当ての商品を探しにくくなってしまいます。IPを意識してアイテムを見やすく、かつ手に取りやすく陳列することで、顧客が商品を選びやすくなります。
IPは、VPやPPによって誘導された顧客が、お目当ての商品を手に取りやすくするために必要な要素です。商品を分類・整理して、規則性を持って商品を配置することにより、どこに何があるかわかりやすくなり、ストレスのない円滑な購買体験を顧客に提供できます。
3つをバランス良く取り入れることで、顧客の視線を導き、購買行動につなげる設計が可能になります。
VP・PP・IPについてや、VMDにかかわる基本用語などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
>>顧客満足度・売上向上につながるVMDの基本とは|重要な要素VP・PP・IPの違いと役割をわかりやすく解説
VMDを自店で実践する方法
VMDの基本を理解したら、次は自店舗でどのように取り入れていくかを考える段階です。店舗ごとに立地や客層、取り扱う商品の特性は異なるため、自店の状況に合わせたVMDの実践が求められます。
ここでは、顧客導線を意識した商品配置や、計画・分析の進め方、スタッフ負担を減らすルール化など、現場で再現しやすい実践ステップを紹介します。
顧客導線を意識した商品配置
前項で紹介したVP・PP・IPの3つの要素は、顧客が店舗に入店して購買に至るまでの導線づくりであることをしっかりと理解しましょう。VMDは、顧客の目を引くような装飾、陳列などが目的ではありません。3つの要素の最終目的は、あくまでも商品の購入だということを意識して、売り場の構成を改善しましょう。
「入口→特設→売れ筋→会計」など一連の流れを意識することで、自然に「買わせる」導線を設計できます。
計画・実施・分析
VMDはパッと見の陳列や装飾といったその場の感覚的なものに頼るのではなく、計画・実施・分析という工程を経ることが大切です。
店頭データやPOSデータを活用することも効果的です。顧客の購買行動や趣味嗜好などの分析、企業の販売戦略や商品戦略などのさまざまなデータを収集・分析して、分析結果に基づいたVMD計画を実施することで効果が増幅します。
スタッフの負担を減らす「ルール化」
VMDを継続的に実践していくためには、属人的な感覚や経験に頼らず、ルールとして仕組み化することが欠かせません。特に、PP(ポイント・プレゼンテーション)やIP(アイテム・プレゼンテーション)の考え方をマニュアル化しておくことで、誰が担当しても一定の品質を保った売場づくりが可能になります。
たとえば、商品の陳列位置、色や高さのバランス、POPの配置ルールなどを明文化して共有することで、スタッフ間の判断ブレを防げます。さらに、新人スタッフやアルバイトが担当する場合でも、マニュアルに沿って作業を進められるため、教育コストや管理の手間を大幅に削減できます。
このようにVMDのルール化は、店舗全体のブランドイメージ統一を実現するとともに、現場の負担軽減と運営効率化にもつながります。結果として、限られた人員でも質の高い売場を維持でき、安定した顧客体験の提供が可能になります。
社内共有・フィードバック
VMDを成功させるためには、現場任せにせず、社内全体での共有とフィードバックの仕組みを整えることが重要です。VMDの目的や意図をスタッフ全員が理解していなければ、せっかくのレイアウトや演出も効果を発揮しにくくなります。
たとえば、定期的に店舗の写真を共有し、各店のVMD実施状況を比較・確認することで、優れた事例を横展開できます。また、実際に接客を担当するスタッフから「お客様がどの棚で立ち止まっていた」「この配置にしてから売上が上がった」などの現場の声を吸い上げることで、より実践的な改善が可能になります。
本部やマネージャーは、こうしたフィードバックをもとに、季節やキャンペーンに合わせたVMDの方向性を明確化し、現場に再共有します。このようにPDCAサイクルを意識してVMDを継続的に改善していくことで、売場の完成度と顧客満足度を同時に高めることができます。
VMD写真を、より効率的に確認・フィードバックしたいと思いませんか?
店舗maticの一機能である「売場ノート」であれば、スマホアプリから写真報告ができ、集計も全店分が画像を横並び確認・フィードバックすることができます!
>>店舗maticの機能詳細はぜひこちらから、無料ダウンロードしてください。
【業種別】VMDの実践事例
実際にVMDを活用する際に、どのように活用すればよいのかわからない人も多いでしょう。ここでは、アパレル店とスーパーでのVMD実践事例を紹介します。ぜひ、参考にしてください。
【アパレル店】PPを効果的に活用した配置
あるアパレル店では、これまでジャケットやブラウス、ボトムスというように商品ジャンルごとにハンガーで陳列して、商品を探しやすくしていました。しかし、ハンガーでの陳列では商品の色しか視覚的に捉えることができません。
この問題点を解決するために、ジャンルごとの陳列は崩さずに、特に注目してほしいアイテムを正面に配置し、商品の形やデザインなどが判別できるようにしています。IPを効果的に活用した陳列方法により、顧客の購買意欲を刺激して、スムーズな購買導線を作り出すことが可能です。
下記の動画では、株式会社ユナイテッドアローズ様の事例を紹介し、VMD業務の改善事例を紹介しています。
>>売れる売場を作りたい!
【食品スーパー】VPを効果的に活用した店頭装飾
あるスーパーでは、野菜や果物の陳列方法を工夫しています。野菜をより色鮮やかに見せるためにスポットライトを当て、顧客の購買意欲をかきたてる仕組みです。また、木に実っているようにブドウを吊り下げて陳列し、生産地に思いを馳せるような演出効果や、季節感を演出しています。遠くからでも売場が見つけやすい効果もあります。
また別のスーパーでは、各店舗によってテーマを決めています。例えば、テーマパークのように人形などを飾るなど、小さな子どもでも飽きずに買い物できるような工夫をしている店舗もあります。買い物の場や時間を楽しいものにしたいというブランド戦略が反映されています。
店舗はお客様とコミュニケーションをとる重要な場です。スーパーのようにEC売上比率が少なく店舗がメインである場合は、店舗での印象がその企業のイメージを大きく左右することになります。
ECとの競争・人手不足のこれからの時代に求められる新たなVMDの考え方
リアル店舗では今、次のような課題を抱えています。
・ECに顧客が流れ、来店数が減少
・人手不足で売場作りに手が回らない
・本部からの販促指示が現場にうまく伝わらない
これらの課題に対し、これからの時代に求められるVMDの考え方について解説します。
ルール化しECやWEBページのブランドイメージを反映させる
店舗を訪れる前にWEBページやECサイトで検索する、という顧客が増えています。これまで別物として考えられてきた店頭とWEBですが、今後は統一された表現を意識することが必要です。
顧客がイメージに対して齟齬を抱かないよう、ルール化することで、少ないリソースでも効果的な売場づくりができるようになります。
店舗ならではの「感情に訴える空間演出」
ECでなんでも買える時代に、わざわざ店舗に足を運ぶ理由は、それが体験として価値があるからです。予想を超える演出、ワクワクする店づくり、そんな期待をもって店舗に来店されます。
その期待を裏切らない感情に訴える演出が、より求められるようになっていくと思われます。
写真・動画・マニュアルでVMDを共有する仕組みづくりが大切
VMDを全店舗で統一して運用するためには、写真や動画、マニュアルなどを活用した共有の仕組みづくりが欠かせません。
文字だけの指示では伝わりにくい色彩のバランスや照明の強弱、POPの位置なども、視覚的な資料を用いることで誰でも理解しやすくなります。
実際の店舗事例を撮影した写真や、売場づくりの手順を動画化したマニュアルを社内共有ツールにまとめておくことで、スタッフの習熟度に関係なく均質なVMDを再現しやすくなります。
こうした仕組みは人手不足の中でも効率的な教育を可能にし、ブランド全体のビジュアル品質を維持するうえで大きな力を発揮します。
店舗maticは、写真や動画、マニュアルでVMDを共有する機能が搭載されています。詳しくは以下のページでご確認いただけます。
各店舗のVMDを共有し横展開できる体制づくり
VMDの品質を全体で底上げするには、成功している店舗の取り組みを他店に横展開できる体制を整えることも重要です。
各店舗で撮影した売場写真や販促ディスプレイの事例をデータベース化し、本部や他拠点からも閲覧できるようにすることで、現場同士の学び合いが促進されます。
季節ごとのディスプレイテーマや装飾アイデアを共有すれば、店舗間の温度差をなくし、ブランドとして一貫した世界観を演出できます。
また、定期的にVMDコンテストや共有会を開催することで、現場スタッフのモチベーション向上にもつながります。こうした情報共有の文化を根づかせることが、これからの時代のVMD運用において鍵となります。
まとめ|VMDの基本知識を武器に、選ばれる店舗へ
VMDは、店舗の陳列方法や演出方法を事前に計画して実行するものです。その計画が成功したのかそうではなかったのか、成功したのであればなぜうまくいったのかなどを分析することが必要です。分析の結果を他のシーズンや店舗にも応用し、成功事例を増やすことが可能になります。
分析するためには、自店のVMDを記録して蓄積することや、VMD担当が確認してフィードバックを行うこと、つまり「売り場づくりのPDCA」が重要です。その結果として、そのお店らしさとして差別化が図れ継続的に安定した利益を上げられるようになります。時差なくスピーディなPDCAサイクルを回すためには、店舗・本部も負担なく売り場状況を報告・確認する仕組みを取り入れることが必要になります。
ネクスウェイでは、チェーンストア企業向けの売場写真共有アプリ「売場ノート」を提供しています。店舗からの売場写真報告と本部のフィードバックをストレスなく行えることで、VMDのPDCAを回すことが可能になります。また店舗の売場写真を全店舗が相互に確認できることで、他店の良い例を取り入れ自店に活かす好循環によって、全店でのVMDレベルの向上が期待できます。VMDのコミュニケーションや報告チェック作業の効率化などに課題を感じられているご担当者様は、ぜひ資料をご覧ください。
※「売場ノート」は店舗maticの機能の一部です。
▼販促指示・売場演出の共有・報告をスムーズにし、VMDの」実行精度を上げる売場ノートは下記よりご覧ください
↓売場づくりのPDCAを高速化した改善事例はこちらから↓