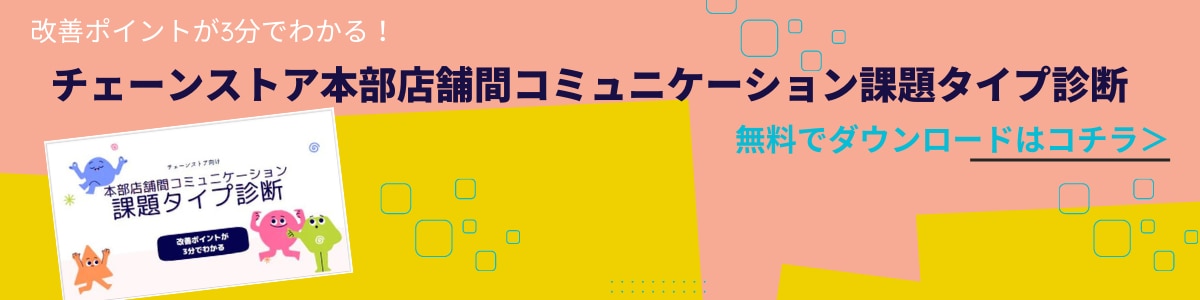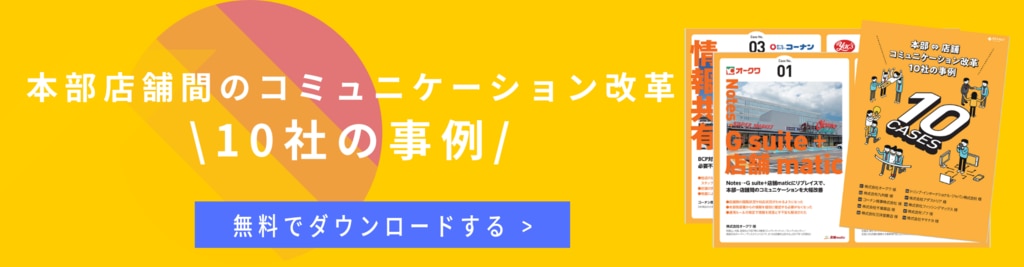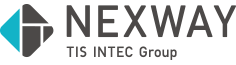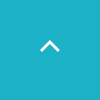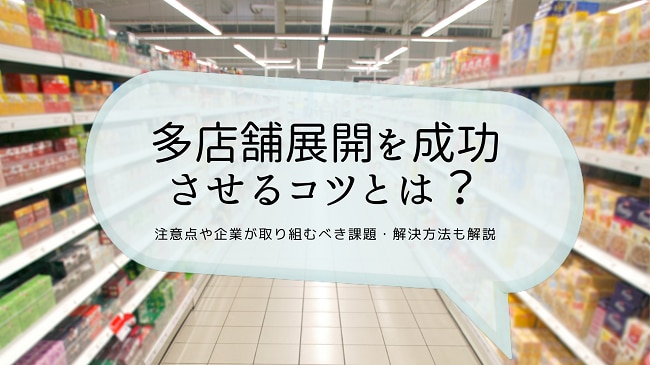
多店舗展開を成功させるコツとは?成功の秘訣や失敗回避、取り組むべき課題も解説
はじめに なぜ今「多店舗展開」が必要なのか
多店舗展開(複数の店舗を運営するビジネスモデル)は、成長を目指す小売企業や飲食企業にとって非常に魅力的な戦略です。 近年では、コロナ禍からの回復、ECと実店舗のOMO、地方市場の再評価、都市部での小型・無人店舗の拡大など、多店舗展開を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。
しかし、単に店舗数を増やせば成功するわけではありません。
オペレーションの標準化、人材の確保、現場の柔軟な対応、そして強固な本部-店舗間のコミュニケーション体制など、多くの課題をクリアして初めて、持続可能な成長が実現します。
この記事では、多店舗展開を成功に導くためのポイント、よくある失敗パターンとその回避策、最新トレンド、成功事例までわかりやすく徹底解説します。
多店舗展開における、本部店舗間コミュニケーション課題診断はこちらより
目次[非表示]
- 1.はじめに なぜ今「多店舗展開」が必要なのか
- 2.多店舗展開とは
- 3.多店舗展開の種類と特徴
- 4.多店舗展開を行うメリット
- 4.1.市場シェアの拡大
- 4.2.ブランド認知の向上
- 4.3.従業員のキャリアアップや採用力の強化
- 4.4.仕入れや物流の費用のコストダウン
- 4.5.リスク回避・分散
- 5.多店舗展開の課題
- 5.1.経費の増加に見合う売上を上げられるか
- 5.2.複雑化する経営管理にどう対応するか
- 5.3.人材の確保・育成
- 5.4.標準化と個店独自のよさのバランスの難しさ
- 5.5.品質やサービスレベルの低下
- 6.多店舗展開を成功させる三つの柱 標準化・個店対応・コミュニケーション
- 6.1.標準化をする
- 6.2.個店のよさを活かす
- 6.3.コミュニケーション体制の強化
- 6.4.デジタル活用とローカル戦略で加速する
- 7.まとめ 多店舗展開成功のカギは「標準化・個店対応・強いコミュニケーション」
- 8.多店舗展開の成長を支える「本部-店舗間コミュニケーション」のご相談はネクスウェイへ
多店舗展開とは
多店舗展開とは、その名のとおり1店舗だけでなく複数の店舗を展開することです。複数店舗を経営することで、売上拡大や仕入れコストの削減などが見込めます。多店舗展開にも2種類あり、「直営店展開」と「フランチャイズ展開」に分けられます。それぞれの特徴については後述するので、そちらを参考にしてください。
多店舗展開の種類と特徴
前述したように、多店舗展開は「直営店展開」と「フランチャイズ展開」があります。ここでは、それぞれの特徴について解説します。
直営店展開
直営店展開とは、自社で店舗を用意して、自社から人員を配置するタイプの多店舗展開です。つまり、自社と店舗スタッフの間に直接雇用関係が発生します。店舗のスタッフは自社社員となるため指示や命令権があり、管理が比較的容易にできるという特徴があります。また、店舗の売上はすべて自社のものとなり、利益が大きくなるのも特徴です。
ただし、直営店展開の場合は、店舗を出店する場所からスタッフの確保、出店に必要な投資などはすべて自社で行わなければいけません。また人件費や家賃、その他の費用なども負担する必要があり、経費負担が大きくなりがちです。
フランチャイズ展開
フランチャイズ展開とは、自社が開発した技術や仕組み、ノウハウなどを加盟店に提供して、事業運営を認める形の多店舗展開です。企業は、加盟店から加盟金やロイヤリティなどを受け取ることができます。また、直営店展開とは異なり経費負担はすべて、フランチャイズオーナーが負担します。そのため、利益率の高さが魅力です。
ただし、自社と雇用契約したスタッフではないため指示・命令権がなく、マネジメントが難しくなっています。フランチャイズ店のイメージや技術不足、ミスなどもすべて自社への評価となるため、ブランドイメージが損なわれるリスクがあります。
多店舗展開を行うメリット
多店舗展開にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、多店舗展開を行うメリットを解説します。
市場シェアの拡大
多店舗展開することで、特定の地域やエリアだけでなく広い市場にプレゼンスを広げることができます。1店舗だけ経営している場合よりも顧客の人数が増加することが見込めるため、売上の向上につながります。
競合他社が出店していないエリアに店舗を構えることで、早期にシェアを獲得でき、ブランドの優位性を確立できます。
また、複数店舗のネットワークにより、全体としての売上ボリュームが増え、規模の経済が働きます。
ブランド認知の向上
多くの店舗を街中や商業施設に展開することで、店舗やロゴなどの自社を表すものが人の目に触れる機会が増えます。何度も同じ店舗名やロゴを見ることで、 「よく見る」「知っている」という顧客の心理が働き、ブランドの認知度が自然と高まります。
特にSNSや口コミで店舗間の情報が広がれば、店舗単独では得られない広がりのある話題づくりが可能になります。
また、認知度や知名度が向上すれば、広告に頼らずに集客しやすくなることも大きなメリットです。多くの広告費をかけずに顧客を獲得できるため、経費の削減もにつながります。
結果として、単純に「1店舗の売上×店舗数」だけではない、さらなる収益増加が期待できます。
従業員のキャリアアップや採用力の強化
多店舗展開によって、従業員のキャリアアップにつながるケースもあり、モチベーションの向上が期待できます。多店舗展開では、キャリアパスの多様性(本部異動、エリアマネージャー昇進など)を示しやすくなります。真面目に仕事をし続けてスキルを磨けばキャリアアップできる、将来的な可能性が広がることは、スタッフのやる気アップにもつながるでしょう。
また、「有名な会社」「よく見かけるお店」という印象は、求職者にとって安心感や魅力につながります。多店舗展開でブランド力が上がると、求人募集時の応募数が増えやすくなり、人材確保がしやすくなります。
優秀な人材の採用・定着ができれば、生産性が向上し売上の向上も期待できます。
仕入れや物流の費用のコストダウン
店舗を複数経営する場合、単独経営時よりも多くの仕入れが必要となります。大量に仕入れをすることで、仕入れ先との値下げ交渉がしやすくなるため、全体としてのコストダウンにつながるでしょう。
また、多くの商品や原材料を仕入れることで、仕入れ先との信頼関係が深まります。よりよい関係を築くことで、値下げ交渉をしやすくなる、融通を聞かせてもらうなどの効果も見込めます。
さらに、在庫の相互補完や、売れ筋商品のデータ共有など、多店舗ならではのオペレーション改善も可能になります。
リスク回避・分散
単独経営の場合、その店舗の売上が振るわなければ、そのまま赤字になってしまいます。しかし、多店舗展開していれば、1つの店舗で業績が思ったように上がらなくても、売上を伸ばしている他の店舗でフォロー可能です。そのため、倒産などのリスクを軽減できます。
また、多くの店舗のデータを収集できることもポイントです。業績のよい店舗と悪い店舗の比較が可能で、早い段階で問題点や改善点が把握できるため、トラブルなどのリスク回避にもつながります。
多店舗展開の課題
多店舗展開では、5つの課題があります。以下では、それぞれの課題について詳しく解説します。
経費の増加に見合う売上を上げられるか
店舗数が増えれば増えるほど、家賃や店内の内外装費、人件費や光熱費、設備費、仕入れ費用といった必要経費の額は大きくなります。また、人事、経理、在庫、売上、クレーム対応など、本部の管理部門の負担が一気に増え、管理コストや運営コストも増える可能性があります。
売上が少ないと必要経費をカバーしきれずに、赤字になってしまう場合があるため注意しましょう。
十分なシステム化や運用ルールを整えないまま拡大を続けると、非効率な業務が増え、利益を圧迫しかねません。店舗を増やす際には、綿密な資金計画と共に、運営にかかわる整備の計画を練る必要があります。
複雑化する経営管理にどう対応するか
多店舗展開は、単独経営と比べると管理が複雑化します。それぞれの店舗に適した仕入れ数、スタッフの確保・教育、コストの把握、売れ筋商品の分析やキャンペーン展開などを1店舗だけでなく複数店舗で行わなければいけないため、経営管理は複雑化してしまうでしょう。
複数店舗の経営管理がうまくいかず、業務に支障をきたしてしまうケースもあります。そのため、本部で一元管理できるシステムを導入するなど、徹底管理できる仕組み作りが必要です。
人材の確保・育成
多店舗展開する場合、店舗数が増えれば増えるほど多くの人材が必要となります。顧客が満足できるサービスを提供するには、スタッフの質や人数が重要です。しかし、慢性的な人手不足が続く小売・飲食業界では、全店舗に十分な人材を配置するのが難しく、既存スタッフに過剰な負担がかかりやすくなります。
その結果、対応が遅くなり、ミスやクレームが増えるだけでなく、働く環境の悪化で離職率の上昇からさらに人材不足という悪循環に陥るリスクがあります。
標準化と個店独自のよさのバランスの難しさ
多店舗の運営を効率化するため、一律のルールや商品・サービスで統一しようとすると、現場が持つ地域特性や顧客ニーズを無視してしまい、「画一的でつまらない店」と見られる可能性があります。
逆に、個店ごとに自由度を持たせすぎると、全体の統制が取れずブランドの一貫性が崩れたり、
運営効率が落ちてしまう問題が発生します。
品質やサービスレベルの低下
店舗数が多いと、現場の状況を細かく把握しきれなくなり、サービス品質や商品クオリティのばらつきが生じやすくなります。
たとえ一店舗でも対応が悪いと、その口コミがSNSやレビューサイトで拡散し、全体のブランドイメージが低下するリスクがあります。
特に、情報伝達ミスやコミュニケーションの断絶は、現場の混乱や顧客満足度低下に直結します。
例えば、本部からのキャンペーン開始日が正しく伝わらない、新しいマニュアルが届いていない、現場の改善要望が届かないなど、こうした小さなズレが積み重なると、店舗運営に混乱を招き、現場スタッフのモチベーション低下や顧客離れにつながります。
そのため、情報の一元管理や双方向コミュニケーションを支える仕組みづくりが不可欠です。
多店舗展開を成功させる三つの柱 標準化・個店対応・コミュニケーション
多店舗展開を成功させるためには、3つのポイントを押さえましょう。ここでは、各ポイントについて解説します。
標準化をする
標準化の最大の目的は、店舗数が増えても品質を落とさないことです。急成長するシーンで多店舗展開を進めた場合、どうしても現場任せの運営になりがちですが、標準化を徹底すれば、各店舗が一定基準のサービス・商品・体験を提供できます。
結果として、顧客満足度の維持やブランド信頼の向上につながります。
-
統一されたマニュアルとオペレーションを用意する
全店舗に共通のマニュアルやオペレーション手順を用意することで、スタッフ一人ひとりが「何を、どうやるべきか」を迷わず実行できます。特に新人スタッフやアルバイトが多い店舗では、標準化されたマニュアルがあるだけで作業スピードが安定し、属人的なやり方によるミスや品質のばらつきを防げます。
これにより、本部としても全体の運営状況を把握しやすくなります。
-
ブランドイメージの一貫性保持
標準化は、顧客がどの店舗を訪れても同じ体験を得られる土台とも言えます。たとえば、接客の言葉遣いや商品ディスプレイのルール、清掃や衛生管理の基準が統一されていれば、「このブランドは信頼できる」という印象を与えやすくなります。
逆に店舗ごとに基準がバラバラだと、ブランド全体のイメージに悪影響を及ぼすリスクがあります。
-
教育・研修の効率化
統一ルールや標準マニュアルがあれば、新人教育やスキルアップ研修が効率的に行えます。
指導内容が店舗や教育担当者によって変わることがなく、どのスタッフも共通の基準でスキルを習得できます。
また、動画やeラーニングを活用した全社的な教育プログラムも導入しやすくなります。
個店のよさを活かす
標準化を進め全国の店舗が画一的になりすぎると、それはそれで魅力の薄い店舗になってしまいます。各店舗の強みを活かすためには、現場主導の自由度が不可欠です。本部が決めたルールに縛りすぎると、現場の強みが発揮されず、顧客ニーズの変化にも対応できなくなります。
標準化と現場の裁量、この二つをうまくバランスさせることが、多店舗展開での長期的な成長の鍵です。
-
地域特性や客層に応じた柔軟な対応
多店舗展開といっても、立地や周辺環境、客層は店舗ごとに大きく異なります。例えば、都市部のオフィス街ではランチタイムの回転率が重視される一方、郊外の住宅地では家族連れを意識したゆったりした空間づくりが求められる場合があります。
こうした地域特性を無視して画一的な運営を行うと、顧客の期待に応えられず、売上やリピート率が低下するリスクがあります。
-
現場裁量を活かした独自施策
各店舗の現場スタッフは、その土地や常連客のことを一番よく理解しています。現場にある程度の裁量を持たせ、「この店舗だからこそできる取り組み」を行えるようにすることで、地域密着のファン作りや、特定ニーズへの対応が可能になります。
本部からの一方的な指示だけでなく、現場主導の試みを評価し、柔軟に取り入れる姿勢が重要です。
-
地域限定キャンペーンやメニュー開発
個店対応の好例として、地域限定キャンペーンやオリジナルメニューがあります。地域特産品を使った商品、季節限定のイベント、地元の学校・企業とコラボした企画などは、その土地ならではの「特別感」を演出でき、集客力を高めます。
これにより、全国一律の商品展開では届かない顧客層を取り込むことができます。
コミュニケーション体制の強化
多店舗展開の成否を分ける、大きな要素として「人と情報のつながり」があります。結局、多店舗展開を支えているのは「人」と「情報」。どれだけ立派な計画を立てても、現場の人が動き、情報が回らなければ実現できません。
だからこそ、コミュニケーション体制の強化は単なる補助的なものではなく、事業成功の根幹を支える最重要要素の一つといえます。
-
現場の声を正確・迅速に吸い上げる仕組み
店舗運営で生じる問題点やアイデアは、最前線の現場から生まれます。「この商品の売れ行きが落ちている」「お客様からこういう要望があった」など、リアルな声を本部が素早くキャッチし、施策に反映できる仕組みが不可欠です。
現場からの報告が滞ると、改善のスピードが落ち、機会損失につながります。
-
本部の指示・情報を効率的に現場へ伝達
新しいキャンペーン、マニュアル更新、衛生管理の注意点など、本部からの重要な情報は日々大量に発生します。
これらを正しく・迅速に各店舗へ届けなければ、現場の混乱やミスが増えるリスクがあります。
メールや電話、FAXなど複数チャネルに分散した伝達方法ではなく、一元管理できるシステムを活用することが効果的です。
-
ツール例:店舗matic
例えば「店舗matic」のような多店舗向け情報共有ツールを導入すれば、本部からの指示・店舗からの報告・進捗確認までを一元管理できます。「誰が、いつ、何を確認・対応したか」が見える化されることで、伝達ミスや確認漏れが防げ、全体の運営効率が向上します。
ツールを導入することで、コミュニケーションの質そのものが改善されます。
デジタル活用とローカル戦略で加速する
DXという言葉が一般化しましたが、多店舗展開でもDXを推進していくことが重要です。デジタル活用によって、業務効率化を図るとともに、ローカライズも効果的に行えます。
例えば、
・業務効率化クラウドツール(タスク・在庫・勤怠管理)
・教育・ナレッジ共有プラットフォーム
で効率化を図り、
・Googleビジネス、プロフィール(GBP)の最適化
・SNS・口コミ・レビュー活用のデジタルマーケ戦略
などでローカルな情報発信を実施する、などがあげられます。
現場のアナログなボトルネックをデジタルで解消することが、多店舗展開をスケールさせる突破口になりえます。
こちらの記事もあわせてご覧ください。小売業でできるDXとは?
まとめ 多店舗展開成功のカギは「標準化・個店対応・強いコミュニケーション」
多店舗展開を成功させるためには、
- 標準化による効率的なオペレーション
- 個店ごとの地域特性・顧客ニーズに応じた柔軟な対応
- そして何より、本部と店舗間の強固なコミュニケーション体制
この3つの柱が揃って初めて、持続可能な成長が可能になります。特に、現場と本部をつなぐコミュニケーションの質とスピードは、組織力を最大化する決定的な要素です。
多店舗展開の成長を支える「本部-店舗間コミュニケーション」のご相談はネクスウェイへ
ネクスウェイは、多店舗展開企業が抱える情報共有・現場連携の課題を解決する
本部-店舗間コミュニケーションツール「店舗matic」を提供しています。
現場の声を本部に届ける。
本部の指示を正確・迅速に現場へ伝える。
それは、成長し続ける組織の基盤です。
「これからの多店舗展開に欠かせないのは、強いコミュニケーション力。」
まずはお気軽に、貴社の課題やお悩みをご相談ください。
【今すぐ資料ダウンロード】
\ 成功事例・導入効果がわかる!無料資料はこちら /
【専門スタッフに相談する】
\ 課題整理・ご提案無料サポート /
会社名:株式会社ネクスウェイ
部署名:販売支援事業部
監修者名:安田美弥子