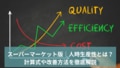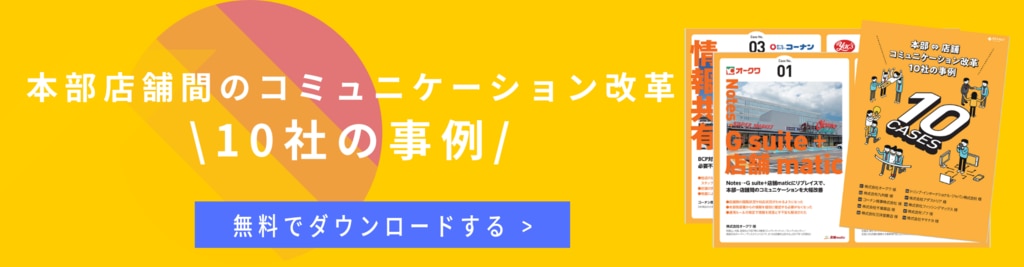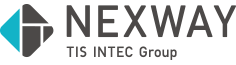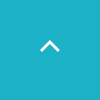店舗ディスプレイの目的とは|基本のコツや効果的な陳列方法を解説
店舗ディスプレイは、顧客の「目」を引き、「心」を動かすための重要な仕掛けです。美しく整えられた売場は、商品そのものの価値を高めるだけでなく、ブランドの世界観を伝え、購買意欲を自然に喚起します。近年では、ECサイトとの競争が激化する中で、リアル店舗だからこそできる“体験価値”の提供が求められています。
本記事では、店舗ディスプレイの基本から、売上アップにつながるVMDの考え方、効果的なレイアウト設計のポイントまでを解説します。どんな店舗でも実践できるアイデアを取り入れて、「また来たい」と思われる売場づくりを目指しましょう。
店舗のディスプレイ写真をストレスなく共有!「売場ノート」はこちらよりご覧いただけます。
目次[非表示]
- 1.店舗ディスプレイを整える目的とは
- 2.売れる店舗ディスプレイをつくるVMDとは
- 3.店舗ディスプレイの基本とは
- 4.ゾーニングと棚割(プラノグラム)の考え方
- 4.1.カテゴリマップの作り方
- 4.2.エンド・ゴンドラ・平台の役割
- 5.店舗ディスプレイにおすすめの5つの陳列方法
- 5.1.トライアングル陳列
- 5.2.リピート(リピテーション)陳列
- 5.3.大量陳列
- 5.4.シンメトリー陳列
- 5.5.アシンメトリー陳列
- 6.「売れる」店舗ディスプレイを叶えるためのポイント
- 6.1.陳列面を増やす
- 6.2.ゴールデンラインを活用する
- 6.3.配置を工夫する
- 6.4.吊り下げる
- 6.5.投げ込み(ジャンブル)を活用する
- 6.6.備品や什器選びも大切
- 7.店舗ディスプレイで他店と差別化する方法
- 7.1.空間を変化させる
- 7.2.個性的な什器を使用する
- 8.店舗ディスプレイに使えるアイテムを紹介
- 8.1.什器
- 8.2.スタンド・天吊り
- 8.3.季節を感じられるグッズ
- 9.店舗ディスプレイの集客チェックリストを確認
- 10.まとめ
店舗ディスプレイを整える目的とは
店舗ディスプレイを整える目的は、顧客に店舗への訪問を促すためです。また、ディスプレイは視覚に訴えることで、購買意欲をかきたて、売上アップに貢献します。顧客に「商品を買いやすい」「買い物が楽しい」と思わせる店舗をつくるために、店舗ディスプレイを整えましょう。主な目的をまとめると下記が挙げられます。
- お客様の目を引く(アイキャッチ)
- 商品の価値をわかりやすく伝える
- 回遊性を高めて売り上げを伸ばす
- ブランドや季節感を表現する
さらに、店舗ディスプレイは単なる装飾ではなく、店舗全体のコンセプトを体現する重要なマーケティング要素でもあります。たとえば、ナチュラル志向のブランドであれば木材やグリーンを使った温かみのある演出、高級志向のブランドであれば照明や素材感で上質さを演出するなど、ディスプレイによって顧客に伝えるメッセージが大きく変わります。
また、ディスプレイの工夫は顧客の購買心理にも影響します。入口付近に新商品や季節商品を配置することで興味を引き、店内奥には滞在時間を伸ばす仕掛けを取り入れるなど、視覚と動線を意識した設計が求められます。これにより、顧客の購買体験をより魅力的にし、結果的にリピーターの増加やブランドロイヤルティの向上にもつながります。
このように、店舗ディスプレイを整える目的は「売れる空間をつくる」ことにとどまらず、「ブランドの世界観を伝え、顧客との関係を深める」ことにもあります。定期的な見直しや季節ごとの更新を行い、常に新鮮で魅力的な売場を保つことが大切です。
売れる店舗ディスプレイをつくるVMDとは
売れる店舗ディスプレイを実現するためには、感覚やセンスだけに頼らず、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の考え方を取り入れることが欠かせません。VMDとは、商品を「どのように」「どこに」「どんな見せ方で」陳列するかを戦略的に設計し、顧客の購買意欲を高めるための手法です。つまり、単におしゃれな売場をつくるのではなく、視覚的な演出を通じて売上につながる仕組みを構築することが目的となります。
VMDは大きく「VP(ビジュアル・プレゼンテーション)」「PP(ポイント・プレゼンテーション)」「IP(アイテム・プレゼンテーション)」の3つの要素で構成されます。VPは店舗全体の世界観を伝えるディスプレイで、ウィンドウや入口付近に設置され、来店意欲を高めます。PPは注目商品やテーマを打ち出すエリアで、販促やシーズン企画などに適しています。そしてIPは、実際に顧客が商品を手に取りやすいように並べる陳列部分で、購買行動を後押しする役割を担います。
これら3つをバランスよく設計することで、顧客は店舗に足を踏み入れた瞬間から自然な導線で商品に触れ、購買へとつながります。
近年は、店頭とネットの垣根がなくなりつつあり、オンライン注文や会員サービスの利用も増えています。
店舗のVMD戦略でも、サイトやカタログ上での商品情報・価格表記・配送ガイドなどをわかりやすく連動させることが重要です。たとえば、店頭で見た商品を後からネットで検索・注文できるようにすることで、来店機会を逃さず販促につなげられます。
VMDについて詳しくは、以下の記事でも詳しく紹介しています。
>>>VMDを徹底解説!初心者でも分かる基本の考え方と活用方法 | チェーンストアの店舗運営DX/ネクスウェイ
>>>顧客満足度・売上向上につながるVMDの基本とは|重要な要素VP・PP・IPの違いと役割をわかりやすく解説
>>>店舗ディスプレイ・VMDの効果を上げる3つのポイント!
店舗ディスプレイの基本とは
訪問客に効果的にアピールする店舗ディスプレイについて、基本的な考え方を解説します。
清潔感
店舗に清潔感がなければ、店舗をアピールする以前の問題です。まずは店舗を掃除しましょう。どんなにきれいなディスプレイでも、ショーウインドーが汚れていたり、入口付近のマットが汚れていたりする店舗に入りたいと思うでしょうか?また乱雑な店舗は印象を悪くし、ディスプレイも目立ちません。整理整頓にも力を入れて取り組みましょう。
明白さ
伝えたいメッセージが明白なディスプレイは、それだけで顧客を惹き付けます。そのためには、ディスプレイの軸がぶれてはいけません。テーマを設定すると商品をアピールする理由がシャープになり、顧客に店舗からのメッセージが伝わりやすくなります。
テーマを設定する際は、どの商品を買ってほしいのか、来客を希望するターゲットの属性・季節性の高いイベントや行事・ライフスタイルの節目などを意識しましょう。
テーマの統一感
設定したテーマに合わせた統一感を意識して売り場を作りましょう。イメージやカラーの統一は見やすさや居心地の良さを強め、顧客の購買意欲を高めます。
グルーピング
グルーピングとは、関連する商品をまとめて陳列する方法です。グルーピングされた売り場は商品がどこに陳列されているかわかりやすく、顧客は快適にショッピングできます。
1つの棚に商品を水平に並べた「水平くくり」や、平積みで商品を縦方向に並べた「垂直くくり」などは、グルーピングの一種です。また、棚の水平・垂直方向に商品をまとめて陳列する方法を「ブロックくくり」と呼びます。
フェイシング
商品のパッケージやラベルを、顧客側に向けてディスプレイする手法がフェイシングです。フェイシングでは、基本的には売れ筋商品ほど面積を広くとり、売れ行きの悪い商品ほど少なめに陳列します。売れ筋商品を多く並べるほど大勢に注目されやすく、在庫切れのリスクも防げます。
配色
ディスプレイの配色は顧客の心理状態に影響を及ぼし、売り場の印象を左右します。ディスプレイの配色を決める際は、色相環(※下図参照)を活用しましょう。色相環とは色を環状に配置したものです。色相環の隣り合う色同士を使うと統一感が増し、落ち着きある売り場になります。一方、色相環で向かい合う色同士を選ぶと、目立つ売り場になります。

アクセント
アクセントをつけると、注目してほしい商品を目立たせられます。POPをつける、台の上に置いて高さを出す、少し前に出すなどで、メリハリをつけて陳列しましょう。
動線
売上向上のためには、動線づくりが重要です。例えば、通路を広く確保して買い物しやすい環境を整えると、顧客満足度が向上します。また、店舗の奥まで顧客に誘導するほど、多くの商品を見てもらえます。POPで店舗奥を目立たせる、奥の商品が見えるよう配置を考えるなどの工夫をしましょう。
入口付近の動線も考えるべきです。外から店内が見渡せ、出入りでぶつかることなく入店できるように、開放的な配置が求められます。
陳列量
店舗や商品のイメージ・コンセプトに応じて、陳列量を調整しましょう。陳列量により、顧客から見た売り場の印象は変わります。陳列量が多ければ、活気ある売り場である、売れ筋の商品であるなどと、顧客に印象づけられます。
ただし、陳列する量が少なくても、売り場が寂し気に見えるとは限りません。たとえば、高級感を重視する店舗であれば、陳列量を抑えて商品ごとの間隔をあけるとエレガントに見えます。
ゾーニングと棚割(プラノグラム)の考え方
店舗ディスプレイを効果的に行うためには、商品を「どこに」「どのように」配置するかという空間設計が欠かせません。その基本となるのがゾーニングと棚割(プラノグラム)の考え方です。
ゾーニングとは、売場全体をエリアごとに区分し、顧客が自然に商品を見つけやすくする設計のこと。棚割は、棚や什器の中で商品をどの位置にどの数量で置くかを定める具体的な配置計画を指します。
ゾーニング設計では、商品のサイズや横幅に合わせて展示スペースを確保することが大切です。業務用什器やスチールラックなどを活用し、商品カテゴリーごとに最適な収納・展示を行いましょう。店頭では、お客様の視線の高さや動線に基づく配置を意識し、ショーケースや木製什器を使って季節特集やクリスマスコーナーなどを展開すると効果的です。
カテゴリマップの作り方
ゾーニングを行う際の第一歩が、カテゴリマップの作成です。カテゴリマップとは、店舗全体のレイアウト図に商品カテゴリーを当てはめた設計図のようなものです。たとえば、来店客が最初に目にする入口付近には新商品や話題性のあるアイテムを、奥には定番商品やリピート率の高い商材を配置するなど、顧客心理と導線を意識して構成します。
また、購買動機や用途ごとにカテゴリーをグルーピングすることで、商品を探す手間を減らし、買いやすい売場をつくれます。季節商品やキャンペーンコーナーなどの「変動ゾーン」を明確にしておくと、定期的なレイアウト変更もスムーズに行えます。カテゴリマップは、店舗の戦略と顧客体験をつなぐ“設計図”として活用すると効果的です。
エンド・ゴンドラ・平台の役割
棚割の設計で重要なのが、エンド・ゴンドラ・平台の使い分けです。エンドとは通路の突き当たり部分にある陳列棚で、来店客の視線を集めやすく、特売商品や新商品の訴求に最適です。ゴンドラは店舗中央の通路に設置された棚で、複数カテゴリーの商品を見せるための主要な売場です。そして平台は、季節限定品や関連商品をまとめて展開する際に効果的で、自由な演出やボリューム感を出しやすいのが特徴です。
これらを適切に組み合わせることで、店舗全体にリズムや動きを持たせ、顧客の回遊性を高められます。たとえば、エンドで注目を集め、ゴンドラで比較・選択を促し、平台で衝動買いを誘うというような一連の流れを意識することで、ディスプレイの効果を最大限に引き出すことができます。
店舗ディスプレイにおすすめの5つの陳列方法
顧客への訴求力が高い陳列方法を紹介します。テンプレート化された陳列方法を活用しましょう。
トライアングル陳列
トライアングル陳列は、高さがバラバラの商品を陳列する際に適しています。ディスプレイの中心付近にもっとも高さのある商品を置き、遠くから「山」に見えるように商品を配置しましょう。トライアングル陳列は顧客の目を引きやすく、狭いスペースでも陳列できます。
リピート(リピテーション)陳列
リピート陳列は、同じまたはよく似た商品を、向きと間隔をそろえて配置する陳列方法です。リピート陳列は遠くからでも目立つため、店舗正面に飾ると入店を促せます。また、入口から通路沿いにリピート陳列すると、店舗奥まで顧客を誘導できます。
違いがわかりやすいところも、リピート陳列のポイントです。たとえばアパレル業界ではコーディネートの異なるマネキンを並べ、着回しのバリエーションをアピールしています。
大量陳列
大量陳列は、同じ商品を大量に集める陳列方法です。大量陳列は、ホームセンターやスーパーマーケットなど、商品を大量に保有する店舗でよく使われます。棚一面に並べる、大きなトレーに山盛りにするなど、大量陳列の方法はさまざまです。
大量陳列は離れた位置からも目立ちます。また、外観が同じものが大量に並ぶ様子は壮観です。大量陳列は、好調な売れ行きを顧客に与えられ、購買への心理的ハードルを引き下げられます。新製品やディスカウント商品、イベントや行事に向けた商品などのアピールに、大量陳列を活用しましょう。
シンメトリー陳列
シンメトリー陳列とは、中心線を境に商品を左右対称に並べる陳列方法です。規則正しく商品が並べられているため、商品の売れ行きがよくわかります。また、商品の売れ具合がよくわかる点も、シンメトリー陳列の特徴です。
アシンメトリー陳列
アシンメトリー陳列は、シンメトリー陳列からすると対極的なディスプレイ手法です。アシンメトリー陳列は、中心線を境に商品を左右非対称に配置して顧客に斬新な印象を与えます。個性的な商品が魅力のセレクトショップや、高級感を出したいジュエリーショップなどでは、アシンメトリー陳列がよく用いられます。
「売れる」店舗ディスプレイを叶えるためのポイント
魅力的な店舗ディスプレイは、単に見た目が整っているだけではなく、顧客の購買行動を自然に促す工夫が施されています。
小売店の規模や業種を問わず、「売れる売場」をつくるためには、限られたスペースの中で商品の魅力を最大限に引き出す工夫が欠かせません。ここでは、どの店舗でも実践しやすい5つのポイントを紹介します。
陳列面を増やす
陳列面を増やすことで、顧客の目に触れる機会を高められます。売れ筋商品や注目商品は、棚の奥ではなく正面やアイキャッチとなる位置に複数フェイス展開するのが効果的です。フェイスが多いほど人気商品に見える“ボリューム効果”が生まれ、購買意欲を刺激します。また、陳列面を広げることで在庫回転もスムーズになり、補充作業の効率化にもつながります。
ゴールデンラインを活用する
ゴールデンラインとは、顧客の視線が最も集まりやすい「床から120〜160cm前後」の高さを指します。
この高さに主力商品や利益率の高い商品を配置することで、手に取られる確率を大幅に上げることができます。逆に、低い位置にはストック性の高い商品や大型商品、高い位置には季節感や装飾性を演出するアイテムを置くと、全体のバランスが良くなります。ゴールデンラインを意識することは、売上アップの基本戦略のひとつです。
配置を工夫する
商品の配置には、顧客心理を意識した戦略が必要です。たとえば、入口付近に話題性のある新商品を置き、店内奥に定番商品を配置することで、自然に回遊を促すことができます。
また、関連商品を隣り合わせに置く「クロスマーチャンダイジング」を活用すると、ついで買いやセット購入を促進できます。商品カテゴリーごとに配置を整理しつつ、導線上に変化をつけることで、顧客が飽きずに売場を楽しめる構成を意識しましょう。
吊り下げる
棚だけでなく、天井や壁面を活用した吊り下げディスプレイも効果的です。吊り下げることで遠くからでも視認性が高まり、売場に立体感や動きを与えることができます。
特に軽量商品や季節アイテム、アクセサリー、小物などに向いており、スペースの有効活用にもつながります。また、POPやサインを吊ることで販促メッセージを目立たせ、顧客をスムーズに目的売場へ誘導することも可能です。
投げ込み(ジャンブル)を活用する
投げ込み(ジャンブル)とは、箱やカゴ、平台などに商品をあえて“ざっくりと”陳列する方法です。一見無造作に見える陳列ですが、「掘り出し物を探す楽しさ」や「お得感」を演出できるため、顧客の購買意欲を刺激します。特にセール商品や在庫処分品、雑貨などの回転率を上げたい商品に向いています。ただし、雑然とした印象を与えないよう、色味やボリューム感を意識して配置することがポイントです。
このように、ディスプレイの工夫ひとつで顧客の滞在時間や購買行動は大きく変わります。売場の特性や商品の性質に合わせて最適な手法を組み合わせ、「見やすく、選びやすく、買いたくなる」空間をつくりましょう。
備品や什器選びも大切
店舗ディスプレイを実践する際は、商品を引き立てる什器や備品選びも重要です。ハンガー、ボックス、パイプ什器、アクリル製のショーケースなど、展示する商品のサイズや重量に合わせて選定しましょう。
たとえば、透明なアクリルスタンドやスチール製の棚は視認性が高く、店頭の雰囲気をシンプルにまとめたい場合におすすめです。ラッピング用紙や紙袋、収納ボックスなどの販促用品も併せて整えることで、スタッフが使いやすくお客様にも分かりやすい売場を作ることができます。
店舗ディスプレイで他店と差別化する方法
他店と一味違うディスプレイは、顧客が店舗に関心をもつきっかけになります。ディスプレイで他店と差別化する方法を紹介します。
空間を変化させる
ディスプレイを変更する際は、商品を入れ替えるだけでは面白みがありません。商品の配置を変えると空間に変化がもたらされ、顧客にディスプレイの変化に気がついてもらいやすくなります。
個性的な什器を使用する
個性的な什器やアイテムをディスプレイに使うと、店舗の個性を表現できます。ディスプレイそのものを楽しみに店舗を訪れる顧客もいます。店舗のイメージや雰囲気にマッチする什器を選びましょう。
店舗ディスプレイに使えるアイテムを紹介
店舗ディスプレイには、棚以外のアイテムも活用できます。商品の設置、装飾に使えるアイテムを紹介します。
什器
什器とは、商品を陳列するための設備を指します。棚やラック、ワゴンなどは什器の一種です。耐久性が強く移動しやすい什器は、頻繁に配置を変える店舗ディスプレイで重宝します。
ディスプレイのテーマによっても什器を使いわけましょう。商品を目立たせるためには、簡素な什器が適しています。一方、什器もディスプレイの一種として活用する際は、個性的なデザインの什器が向いています。
スタンド・天吊り
スタンドや天吊りは、セール価格やアピールしたい商品の告知などに便利です。スタンドは、卓上に置き、パネルなどを挟みます。置き場所の確保が難しいときは、天吊りにより告知しましょう。天井付近は視界を遮るものが無いため、遠くからでも告知に気がついてもらえます。
季節を感じられるグッズ
季節を感じられるグッズを店舗ディスプレイに採用すると、顧客の購買意欲を高めます。季節を連想させる色や、イベントにちなんだグッズを配置しましょう。
たとえば、春には桜を思わせるピンク色、夏には爽やかな青や水色が似合います。イベントについては、秋にはハロウィンを意識したパンプキンフェイス、冬にはクリスマスツリーや門松などが飾られます。
店舗ディスプレイの集客チェックリストを確認
店舗ディスプレイの見直しに役立つチェックリストを紹介します。以下のリストを見て、集客力の高い店舗に仕上げましょう。定期的に見直すことで、常にいい売場を保つことができます。
- ショーウインドーや看板、入口のガラスが汚れていないか
- 入口付近から、店舗の奥まで目が届くか
- 通路は、すれ違えるだけのスペースを確保しているか
- ディスプレイは店舗やブランドのイメージにあっているか
- 季節感があるディスプレイか
- 商品にあったディスプレイか、魅力が伝わるディスプレイか
- 顧客にとって居心地のよい空間づくりができているか
- 顧客が商品を比較検討できるよう、グルーピングされているか
まとめ
適切な店舗ディスプレイは集客力を高め、売上を向上させます。陳列面の拡大やゴールデンラインの活用、商品配置の工夫などで、店舗ディスプレイを見直しましょう。
また、継続的に効果的な売り場を作っていくには、店舗の陳列方法や演出方法を計画して実行したあと、その計画を振り返り分析することが必要です。分析の結果は他のシーズンや店舗にも応用することができます。
自店の売り場を記録して蓄積し、スーパーバイザーや商品部などが確認してフィードバックをするような売り場づくりのPDCAを回しましょう。その蓄積によって、差別化が図れ継続的に安定した利益を上げられるようになります。
ネクスウェイでは、チェーンストア企業向けの売場写真共有アプリ「売場ノート」を提供しています。店舗からの売場写真報告と本部のフィードバックをストレスなく行えることで、店舗ディスプレイづくりのPDCAを回すことが可能になります。また店舗の売場写真を全店舗が相互に確認できることで、他店の良い例を取り入れ自店に活かす好循環によって、全店でのディスプレイのレベル向上が期待できます。店舗ディスプレイづくりのコミュニケーションや報告チェック作業の効率化などに課題を感じられているご担当者様は、ぜひ資料をご覧ください。