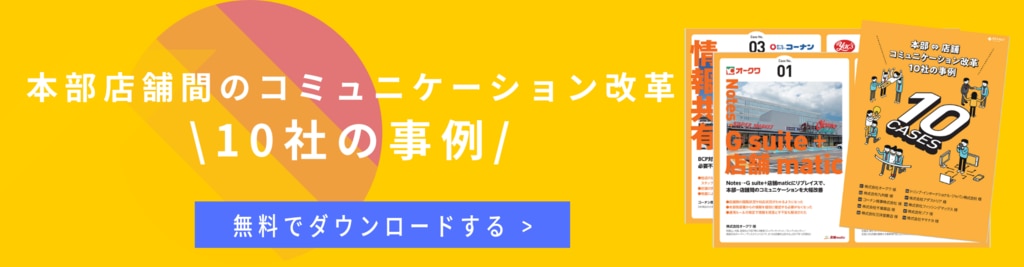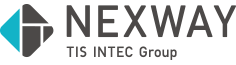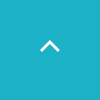情報共有ツールとは?種類・選び方・おすすめツールを紹介
目次[非表示]
- 1.社内情報共有ツールとは?
- 2.社内情報共有におけるよくある課題
- 2.1.情報が分散していて、どこに何があるか分からない
- 2.2.伝言ゲームのようになり、誤解や伝達漏れが発生する
- 2.3.店舗間・部門間で情報共有のレベルに差がある
- 2.4.情報が属人化しており、誰かが休むと対応できない
- 3.社内情報共有ツールの主な種類と特徴
- 3.1.社内Wiki:ナレッジ蓄積と検索性に強み
- 3.2.ビジネスチャット:リアルタイムな会話に最適
- 3.3.グループウェア:スケジュール・連絡・タスク管理が一元化
- 3.4.オンラインストレージ:ファイル共有と管理に便利
- 4.情報共有ツールを導入するメリット
- 4.1.社内状況や業務進捗の可視化
- 4.2.情報共有のスピード向上による意思決定の迅速化
- 4.3.チーム内のコミュニケーション活性化
- 4.4.属人化防止と業務の標準化
- 5.情報共有ツールを導入・運用する際の注意点
- 6.情報共有ツールを選定する際のチェックポイント
- 6.1.操作性:現場スタッフにも使いやすい設計か
- 6.2.機能:必要な情報が一箇所に集約されているか
- 6.3.コスト:利用人数や機能に対して費用対効果があるか
- 6.4.多言語対応の有無:外国籍スタッフがいる場合の配慮
- 6.5.安全性:IP制限や二段階認証などのセキュリティ機能
- 7.情報共有ツールの選定で迷ったら「店舗matic」!
- 8.まとめ
多店舗展開を行う小売業やチェーン店舗の現場では、本部と店舗間の情報共有がうまくいかず、業務に支障をきたすケースが少なくありません。メールや紙での連絡に頼っていた結果、伝達ミスや進捗の把握不足、業務の属人化といった問題が生じている企業も多いのではないでしょうか。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが「情報共有ツール」です。チャットや掲示板、ファイル共有などの機能を活用することで、情報のやりとりがスムーズになり、業務の効率化や標準化にもつながります。
本記事では、情報共有ツールの基本的な役割や種類を紹介したうえで、導入時のチェックポイントや失敗しない選び方を解説します。現場にも定着しやすいおすすめのツールもご紹介しますので、自社に合った仕組みづくりの参考にしてみてください。
社内情報共有ツールとは?
社内情報共有ツールとは、企業内での情報伝達や業務連携をスムーズに行うためのツールです。特に小売業や多店舗展開を行うチェーン店では、複数の拠点間で同じ情報を正しく、かつリアルタイムに共有することが求められます。日報や売上データ、販促資料、マニュアルなど、さまざまな情報を紙や口頭、メールだけで管理していると、情報が分散して非効率になりがちです。こうした課題を解決し、組織全体の情報連携を最適化するのが情報共有ツールの役割です。
社内情報共有におけるよくある課題
情報共有ツールが導入されていない、あるいは機能が不十分な環境では、日々の業務にさまざまな支障が生まれます。店舗や部門ごとに情報の扱い方がバラバラだったり、重要な連絡が現場まで正確に届かなかったりと、組織の連携にズレが生じやすくなります。ここでは、よくある情報共有の課題について具体的に見ていきましょう。
情報が分散していて、どこに何があるか分からない
連絡はメール、資料は共有フォルダ、マニュアルは紙で配布といったように、情報があちこちに散在していると、必要な情報を探すだけで時間がかかってしまいます。急ぎの対応が求められる場面では、これが大きなストレスや業務の遅延につながります。情報を一か所に集約し、誰でもすぐにアクセスできる仕組みが必要です。
伝言ゲームのようになり、誤解や伝達漏れが発生する
本部からの指示が店長を介してスタッフへ、さらにパートへと伝わる中で、内容が抜け落ちたり、解釈に差が出たりするケースも少なくありません。いわゆる「伝言ゲーム」状態となることで、業務にズレが生じたり、トラブルに発展することもあります。正確な情報をタイムリーに共有できる手段の整備が求められます。
店舗間・部門間で情報共有のレベルに差がある
同じ本部から指示を受けていても、店舗や部門によって情報共有の理解度や実行のスピードに差が出てしまうことがあります。ある店舗ではスムーズに運用できている施策も、他店舗ではうまく機能していないという状況が、業務の非効率や不公平感につながります。全体の足並みを揃えるには、ツールによる仕組み化が効果的です。
情報が属人化しており、誰かが休むと対応できない
特定のスタッフだけが情報を把握している、特定の担当者しか使えない資料がある、といった属人化もよくある課題です。担当者が不在になるだけで業務が滞ったり、ミスが起きたりするため、業務の安定性を保つにはリスクが高い状態といえます。誰でも同じ情報にアクセスし、必要な対応ができる体制が重要です。
社内情報共有ツールの主な種類と特徴

一口に「情報共有ツール」といっても、その目的や機能に応じてさまざまな種類があります。業種や組織体制によって、適したツールは異なるため、自社の課題や運用スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。ここでは、代表的な社内情報共有ツールと、それぞれの特徴について紹介します。
社内Wiki:ナレッジ蓄積と検索性に強み
社内Wikiは、業務マニュアルやQ&A、業務フローなどのナレッジを蓄積し、必要なときに誰でも参照できるようにするツールです。ページごとの編集が可能で、更新履歴が残るため情報の整備や管理がしやすいのが特長です。特に新入社員や異動者にとっては、業務のキャッチアップに役立ちます。一方で、使いこなすには社内での運用ルールづくりが重要です。
ビジネスチャット:リアルタイムな会話に最適
SlackやChatworkに代表されるビジネスチャットは、テキストベースのリアルタイムなやりとりに適しています。メールよりもスピーディに情報を共有でき、会話の履歴も追いやすいため、日々の業務連携がスムーズになります。通知機能やチャンネル分けにより、情報の整理や緊急連絡にも対応しやすいのが魅力です。ただし、情報が流れやすいため、後から確認しづらいという弱点もあります。
グループウェア:スケジュール・連絡・タスク管理が一元化
グループウェアは、組織内のスケジュール調整や掲示板、タスク管理、ファイル共有などを一つのツールに統合した情報基盤です。複数の拠点や部門がある企業でも、全体の動きを把握しやすくなり、情報伝達のばらつきが減ります。紙や個別のツールで管理していた情報を一元管理することで、運用効率の向上が期待できます。
オンラインストレージ:ファイル共有と管理に便利
Google DriveやDropboxなどのオンラインストレージは、ファイルをインターネット上で保存・共有できる便利なツールです。複数人での同時編集や、フォルダごとの権限管理が可能で、業務に必要な資料をクラウド上で一括管理できます。最新のファイルを探す手間や、誤送信のリスクも軽減されるため、情報共有の基盤として多くの企業に導入されています。
情報共有ツールを導入するメリット
情報共有ツールは、単なる「連絡手段の置き換え」ではありません。導入によって業務全体の透明性やスピードが向上し、現場の負担軽減やミスの削減、組織力の底上げにもつながります。ここでは、情報共有ツールを導入することで得られる具体的なメリットを整理してご紹介します。
社内状況や業務進捗の可視化
情報共有ツールを導入する最大のメリットの一つは、業務の「見える化」です。どの店舗や部署で、誰が、いつ、何に取り組んでいるのかをリアルタイムで確認できるため、現場の混乱を未然に防ぐことができます。従来のように電話や紙の報告書でやり取りしていた情報がツール上で一元管理されることで、管理者の確認作業や対応時間が大幅に削減されます。また、各担当者の進捗状況が可視化されることで、早期のフォローアップやタスクの再分配もしやすくなり、全体の生産性向上にもつながります。報告・連絡・相談のハードルが下がることも、見逃せないポイントです。
情報共有のスピード向上による意思決定の迅速化
組織運営において、「情報が届かない」「判断が遅れる」といった状況は、ビジネスチャンスの損失や業務の停滞を引き起こします。情報共有ツールの活用により、連絡内容や業務の変化をリアルタイムに全社で共有できるようになることで、意思決定に必要な情報を素早く集約できる環境が整います。とくに小売業や多店舗展開をしている企業では、現場ごとの判断を待つことなく、本部主導で迅速な対応が可能になるため、売場づくりや販促施策の反映スピードも格段に上がります。スピードが求められる現場では、こうした環境が競争力そのものになるのです。
チーム内のコミュニケーション活性化
情報共有ツールは、業務に関する「報告の場」にとどまらず、チームメンバー同士が日常的にコミュニケーションをとれる「つながりの場」としても機能します。普段顔を合わせる機会が少ない異なる店舗のスタッフ同士でも、ツールを通じて成功事例を共有したり、困りごとを相談したりと、横のつながりを築くことができます。こうした日常的なやり取りが増えることで、チーム全体の関係性が深まり、業務上の連携もスムーズに。結果として、連携ミスの減少や現場のモチベーション向上にもつながり、チームとしての一体感が生まれていきます。
属人化防止と業務の標準化
特定の業務や情報が一部のスタッフにしか分からない状態は、組織のリスクとなります。属人化が進むと、担当者の不在や退職時に業務が止まったり、後任者が混乱したりといった問題が発生しやすくなります。情報共有ツールを活用すれば、マニュアルや手順、ノウハウをクラウド上に蓄積でき、誰でも必要な情報にアクセスできる環境を構築できます。業務プロセスの標準化も進み、担当者に依存しない体制づくりが可能になります。また、新人スタッフや異動者への教育も効率化され、組織全体の対応力が強化されるという副次的な効果も期待できます。
情報共有ツールを導入・運用する際の注意点

情報共有ツールは便利な反面、導入や運用を誤ると、かえって混乱を招いたり、利用が定着しなかったりするリスクもあります。とくに多店舗展開をしている小売企業においては、現場の業務負担やリテラシーの差を考慮した丁寧な導入と、継続的な運用体制の構築が不可欠です。ここでは、ツール導入にあたって押さえておくべき注意点を紹介します。
導入作業は段階的に、現場の理解を得ながら進める
どれだけ高機能なツールでも、現場が使いこなせなければ意味がありません。一気に全社展開するのではなく、まずは一部の店舗や部署でテスト運用を行い、使用感や課題を洗い出すことが重要です。そのうえで、マニュアルやFAQの整備、使い方のレクチャーを通じて現場の理解と納得を得ることが、導入成功のカギとなります。また、導入初期はサポート担当を明確にし、困ったときにすぐ相談できる体制を整えておくと、現場の不安も軽減されます。
運用ルールを整備し、全員が守れる仕組みにする
ツールを導入しただけでは情報共有の質は高まりません。どのタイミングで、誰が、どの情報を発信・確認するのか、明確なルールを整備することが必要です。たとえば「週次で本部が方針を投稿」「店舗は毎日15時までに進捗を報告」など、具体的な行動ルールを設けることで、属人化を防ぎつつ、情報が確実に流れるようになります。また、ルールを形だけで終わらせないためにも、ツール内にガイドラインを常に掲示しておくことや、運用の定期見直しも効果的です。
情報漏洩リスクやアクセス制限などセキュリティ対策を講じる
業務に関わる重要な情報を扱うツールだからこそ、セキュリティ対策は欠かせません。店舗ごとのアクセス権限を適切に設定し、「誰がどの情報を見られるか」を管理することで、不要な情報の閲覧や誤操作を防ぐことができます。また、ログイン認証や操作履歴の記録など、基本的なセキュリティ機能の有無も選定時に確認しておきたいポイントです。さらに、スタッフへのセキュリティ教育も並行して行うことで、組織全体としての情報リテラシーを高めていくことができます。
情報共有ツールを選定する際のチェックポイント
情報共有ツールは多種多様で、機能や価格、運用スタイルもそれぞれ異なります。とくに小売・チェーン店舗においては、本部と現場の双方が無理なく活用できることが導入成功の条件となります。ここでは、選定時に注目すべきポイントを整理し、現場に根付くツール選びのヒントをお届けします。
操作性:現場スタッフにも使いやすい設計か
まず確認したいのが、ツールの操作性です。普段からパソコンやシステムに慣れていない現場スタッフも多いため、直感的に使える画面設計やナビゲーションであることが重要です。マニュアルがなくても使い方がわかるようなUIや、スマートフォン対応などもあると、導入ハードルがぐっと下がります。操作が複雑すぎると、結局使われずに形骸化してしまうリスクがあるため注意が必要です。
機能:必要な情報が一箇所に集約されているか
情報共有の効率化には、業務に必要な情報が一元管理できることが不可欠です。チャット、ファイル共有、タスク管理、マニュアル掲載など、複数の機能を備えているかどうかを確認しましょう。たとえば、日報やToDoリスト、売場指示などがすべてツール内で完結できる設計であれば、他のツールと行き来する手間もなくなり、業務全体がスムーズに流れます。
コスト:利用人数や機能に対して費用対効果があるか
機能が充実していても、導入・運用コストが高すぎては継続的な利用が難しくなります。導入前には、初期費用だけでなく月額費用、利用人数による課金体系、オプション機能の有無などを総合的に比較検討しましょう。また、無料トライアル期間を活用し、実際の現場での使い勝手や効果を見極めたうえで判断することもおすすめです。
多言語対応の有無:外国籍スタッフがいる場合の配慮
多店舗展開を行っている企業では、外国籍スタッフが働いているケースも珍しくありません。その場合、ツールの多言語対応は重要なチェックポイントになります。基本的な表示やマニュアル、通知機能などが複数言語に対応していれば、外国籍スタッフも安心して使うことができ、情報格差の防止にもつながります。誰にとっても使いやすい環境づくりが、現場の連携強化につながります。
安全性:IP制限や二段階認証などのセキュリティ機能
業務に関わる情報を扱う以上、セキュリティ対策も万全であるべきです。ツール選定時には、アクセス制御の柔軟性や、IP制限、二段階認証といった基本的なセキュリティ機能の有無を確認しましょう。万が一の情報漏洩や不正アクセスを防ぐためには、ツール自体の安全性に加えて、社内での運用ルールや教育体制もセットで考えておく必要があります。
情報共有ツールの選定で迷ったら「店舗matic」!
チェーン店舗での情報共有ツールなら、店舗maticをご利用ください。
店舗maticは、ToDo管理・カレンダー・アンケート・マニュアル管理・コミュニケーション機能等、店舗運営に必要な要素が揃った、オールインワンの情報共有ツールです。
業務の見える化と一元管理を実現し、伝達ミスや業務の属人化と言った、課題を根本から解消。実際に導入した企業からも「現場の負担が軽減された」「本部の指示がスムーズに伝わるようになった」といった声が多く寄せられています。
事例は以下からご覧いただけます。
導入事例|店舗間コミュニケーションの悩みをツール・アプリで解決【株式会社ネクスウェイ】
業務の効率化を図りたい企業、現場との距離を縮めたい本部担当者様は、ぜひこの機会にお問い合わせください。
まとめ
社内の情報共有は、単に「連絡を伝える手段」にとどまらず、業務効率・従業員満足度・企業全体の生産性に直結する重要なテーマです。情報が分散していたり、伝言ゲームのように誤解が生じていたりする現状を放置すれば、現場の混乱や業務の非効率化を招きかねません。
だからこそ、操作性・機能性・安全性を兼ね備えた情報共有ツールを選び、現場が安心して活用できる体制づくりが不可欠です。ツール導入に迷った際は、チェーン店舗の現場事情に最適化された「店舗matic」も選択肢の一つとして、ぜひ検討してみてください。
▽店舗maticとは

サービスについての詳しい質問や導入時のお悩みもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ|店舗間コミュニケーションの悩みをツール・アプリで解決【株式会社ネクスウェイ】