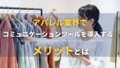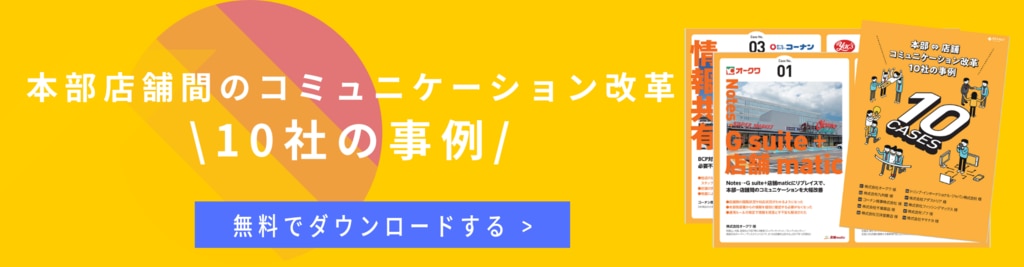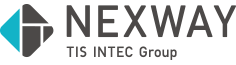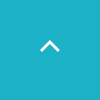飲食店のコミュニケーションを円滑に!おすすめツールと導入のメリット
目次[非表示]
- 1.飲食業界におけるコミュニケーションの課題
- 1.1.責任者が常に現場を確認できない
- 1.2.飲食店の理念やオペレーションを共有しづらい
- 1.3.スタッフ間の情報共有が不十分で業務ミスが発生する
- 1.4.複数の連絡手段を使い分けることで情報が散乱する
- 2.飲食店でコミュニケーションツールを導入するメリット
- 2.1.情報の一元化で指示漏れ・認識のズレを防ぐ
- 2.2.シフト管理やタスク共有がしやすくなる
- 2.3.マニュアルが見やすくなり、スタッフ教育が効率化する
- 2.4.エリアマネージャーの負担軽減につながる
- 3.飲食店におすすめのコミュニケーションツール「店舗matic」
- 3.1.本部・店舗間の情報共有を一元化
- 3.2.業務タスクを可視化し、業務の負担を軽減
- 3.3.マニュアルを共有しスタッフ教育も効率化できる
- 4.まとめ
飲食業界では、スピーディーで的確な連携が求められる一方で、スタッフ間の伝達ミスや情報の行き違いが起こりやすいという現実もあります。
「言った・言ってない」「確認していなかった」といったトラブルは、業務効率を下げるだけでなく、顧客満足度の低下にも直結します。そんな課題を解決する手段として注目されているのが、コミュニケーションツールの導入です。
本記事では、飲食業界における典型的な課題を整理したうえで、ツール導入によるメリットや、おすすめのツール「店舗matic」の特長をご紹介します。
飲食業界におけるコミュニケーションの課題
飲食店の現場は、常にスピードと正確性を求められる環境です。しかしその一方で、情報共有や指示伝達に課題を抱える店舗も少なくありません。特に多店舗展開をしている飲食店や、シフト制で動くスタッフが多い現場では、情報の伝達ミスや意識のズレが日常的に起こりやすい状況です。ここでは、飲食業界における典型的なコミュニケーションの悩みを整理してみましょう。
責任者が常に現場を確認できない
店長やエリアマネージャーなどの責任者は、多忙な業務の合間に複数店舗を兼任しているケースも多く、現場の様子をリアルタイムで把握するのが難しくなります。その結果、業務の遅れやスタッフの対応状況に気づくのが遅れ、問題が深刻化してから報告が上がることも珍しくありません。「現場で何が起きているのか」をすぐに把握できないことが、判断の遅れや業務ミスの温床になっているのです。
飲食店の理念やオペレーションを共有しづらい
企業としての理念や接客方針、料理提供の基準などをすべてのスタッフに正しく伝えるのは簡単ではありません。特にアルバイトスタッフが多く在籍する飲食店では、理念の浸透やマニュアルの徹底が不十分になりがちです。その結果、スタッフごとの対応にばらつきが出て、顧客体験にも差が生まれてしまいます。こうしたズレは、ブランド全体の評価にも影響を与えることになります。
スタッフ間の情報共有が不十分で業務ミスが発生する
調理とホール、キッチンとフロア、あるいは早番と遅番といったように、飲食店では業務が分担されるため、スタッフ間での引き継ぎや情報共有が重要になります。しかし、口頭だけで伝達が行われていたり、伝言が伝わっていなかったりすると、オーダーミスや準備不足などのトラブルにつながります。小さなミスでも積み重なれば、店舗の信頼性を損なう原因になりかねません。
複数の連絡手段を使い分けることで情報が散乱する
LINEで個別連絡、紙でシフト表、口頭で注意事項……といったように、情報のやりとりが複数の手段にまたがってしまうと、重要な連絡が埋もれたり、確認漏れが起こったりすることがあります。情報の整理や管理に時間がかかるうえ、スタッフ側も「どこに何があるかわからない」と混乱しやすくなります。こうした状態では、全員が同じ方向を向いて業務に取り組むことは困難です。
飲食店でコミュニケーションツールを導入するメリット

飲食店での業務はスピード感と連携が命です。しかし、現場での情報共有がうまくいかなければ、サービスの質やオペレーションに大きな影響を与えてしまいます。そこで注目されているのが、コミュニケーションツールの導入です。ここでは、ツール導入によって得られる具体的なメリットを紹介します。
情報の一元化で指示漏れ・認識のズレを防ぐ
コミュニケーションツールを使えば、本部からの連絡事項や店長からの業務指示をすべて一つのプラットフォーム上で管理できます。これにより、「聞いていない」「伝わっていなかった」といった指示漏れや誤解が減り、全スタッフが同じ情報を共有しながら動くことが可能になります。掲示板やチャット、既読機能を活用することで、誰がどの情報を確認したのかも明確になり、業務の正確性が向上します。
シフト管理やタスク共有がしやすくなる
飲食店では、曜日や時間帯ごとに異なるシフトが組まれ、それに応じた業務の割り振りも発生します。コミュニケーションツールの中には、シフト管理やタスク機能が搭載されているものもあり、今日誰が何をすべきかが一目で分かる環境を整えられます。変更があった場合の通知もリアルタイムで行えるため、混乱を最小限に抑えることができます。
マニュアルが見やすくなり、スタッフ教育が効率化する
紙のマニュアルや口頭での説明に頼る教育では、内容の抜け漏れや伝達のばらつきが起こりがちです。コミュニケーションツールを使えば、動画や画像、文書でマニュアルをいつでもどこでも確認できるようになり、新人スタッフでも自分のペースで学ぶことができます。教育担当者の負担が軽減されると同時に、店舗全体でのオペレーションの質も安定します。
エリアマネージャーの負担軽減につながる
複数店舗を担当するエリアマネージャーにとって、各店舗の状況把握や指示出しは大きな負担になります。コミュニケーションツールを導入すれば、現場の進捗や報告をリアルタイムで確認でき、巡回せずとも必要な対応を的確に行うことが可能になります。報告や相談もツール上で完結するため、電話や訪問の回数が減り、移動や確認業務の時間を大幅に削減できます。
飲食店におすすめのコミュニケーションツール「店舗matic」

飲食業界の現場で発生するコミュニケーションの課題に対し、実践的かつ定着しやすいツールとして注目されているのが、ネクスウェイが提供する「店舗matic」です。店舗運営の見える化と情報共有の一元管理を実現し、業務のムダを減らしながらサービス品質の向上にもつなげることができます。ここでは、飲食店における「店舗matic」の主な特長をご紹介します。
本部・店舗間の情報共有を一元化
「店舗matic」では、本部からの通達、業務連絡、売上報告、業務日誌など、店舗運営に必要なやりとりをすべて一つのプラットフォーム上に集約できます。紙や口頭で伝えていた内容も、掲示板やチャット、タスク機能を使って明確に記録されるため、情報の抜け漏れを防ぎ、確認作業の手間も軽減。リアルタイムに情報が届き、スタッフ一人ひとりが「何を・いつ・どうするか」を理解したうえで動けるようになります。
業務タスクを可視化し、業務の負担を軽減
「店舗matic」では、その日の業務タスクをToDo形式で一覧表示できます。誰が・何を・いつまでに行うべきかが明確になることで、現場の混乱を防ぎながら、スタッフが自律的に動ける環境を整えることができます。また、完了報告もツール上で簡単にできるため、管理者は業務の進行状況を常に把握でき、対応が必要な箇所へすぐにフォローを入れられるのも大きな利点です。
マニュアルを共有しスタッフ教育も効率化できる
新人スタッフの教育や業務の標準化にも、「店舗matic」は力を発揮します。マニュアルや動画、チェックリストをツール上に集約することで、必要な情報にいつでもアクセス可能に。研修担当者が手取り足取り教えなくても、スタッフ自身で学べる仕組みが整い、現場の教育負担が軽減されます。また、店舗間で教育内容の差が出るのを防ぐことで、全体として均質なサービス品質を維持できるようになります。
まとめ
飲食店におけるコミュニケーションの課題は、スタッフ間の情報共有や業務連携の方法に起因しているケースが多く見られます。特に多店舗展開やシフト制を採用している店舗では、従来の方法では限界を感じる場面もあるでしょう。そんな中、情報を一元管理し、指示やタスク、マニュアルまでをスムーズに共有できるコミュニケーションツールは、業務効率の大幅な改善に貢献します。なかでも「店舗matic」は、飲食業界の現場に特化した設計で、操作のしやすさと定着力の高さが特長です。スタッフ全員が迷わず動ける環境を整えたいと考えているなら、ぜひ「店舗matic」の導入を検討してみてください。現場が変われば、サービスの質も大きく変わります。
▽店舗maticとは

サービスについての詳しい質問や導入時のお悩みもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ|店舗間コミュニケーションの悩みをツール・アプリで解決【株式会社ネクスウェイ】