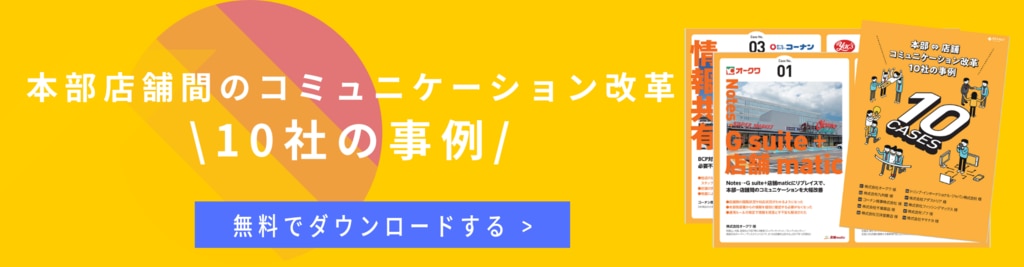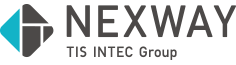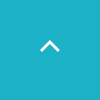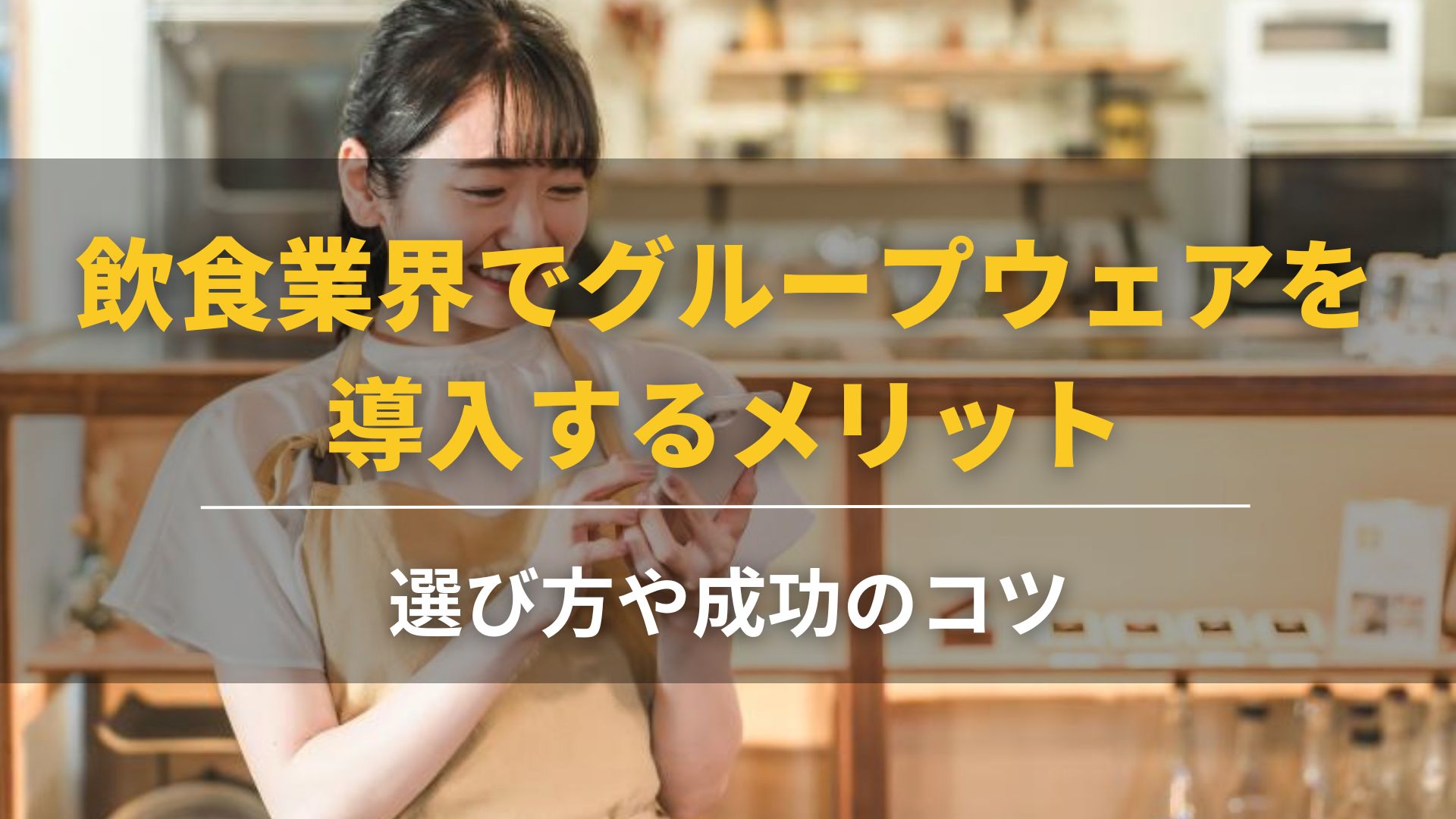
飲食業界でグループウェアを導入するメリット。選び方や成功のコツ
目次[非表示]
- 1.飲食業界のよくある課題
- 1.1.人手不足
- 1.2.エリアマネージャーの負担が大きい
- 1.3.スタッフ育成のための時間が取れない
- 1.4.本部と店舗の連携が上手くいかない
- 2.飲食店でグループウェアを導入するメリット
- 2.1.情報共有を一元化できる
- 2.2.業務連絡のミスを削減できる
- 2.3.多店舗の連携を強化できる
- 2.4.マニュアルの共有で人材育成も効率化できる
- 3.飲食店でのグループウェア導入を成功させるコツ
- 3.1.シンプルな操作性を選ぶ
- 3.2.各店舗のノウハウを共有し、定着させる
- 4.飲食店でのグループウェアの選び方
- 5.飲食店で使えるグループウェアなら「店舗matic」
- 5.1.今日何をするかが一目でわかる画面
- 5.2.定着しやすい、ルール化された記入画面
- 5.3.多店舗運営をスムーズに
- 6.まとめ
飲食店の現場では、シフト調整や情報共有、スタッフ教育など、日々の業務に追われながら多くの課題と向き合っています。特に多店舗展開をしている企業では、本部と店舗、店舗間の連携が滞ることで、サービス品質のばらつきや業務効率の低下が起きやすくなります。
そんな課題を解消する手段として注目されているのが「グループウェア」です。
本記事では、飲食業界におけるグループウェア導入のメリットや成功のポイント、導入時の選び方、そして飲食店に特化したグループウェア「店舗matic」の特長をご紹介します。
飲食業界のよくある課題
多店舗展開や現場のスピードが求められる飲食業界では、日々の業務にさまざまな課題を抱えている企業が少なくありません。人材の確保や育成、本部との情報連携など、多岐にわたる悩みが積み重なり、現場の負担はますます増加しています。ここでは、飲食業界における代表的な課題について整理し、それぞれが業務のどこに影響を与えているのかを見ていきます。
人手不足
飲食業界は、慢性的な人手不足に悩まされている業界の一つです。求人を出してもなかなか応募が集まらず、スタッフの定着率も決して高くはありません。
結果として、一人の従業員にかかる業務負担が増加し、シフトの調整やオペレーションに無理が生じるケースも多く見られます。この状況が続くと、サービスの質が下がったり、スタッフのモチベーションが維持できなかったりと、悪循環に陥る可能性もあります。
エリアマネージャーの負担が大きい
複数の店舗を担当するエリアマネージャーは、売上の管理から人員配置、クレーム対応まで幅広い業務をこなさなければならず、その負担は非常に大きいです。移動時間や現場での対応に追われる中で、本部からの連絡や各店舗の状況把握まで行うのは、長時間働く原因となり、結果として残業時間が増加することも少なくありません。
さらに、スタッフが不足している場合には、その負担がさらに大きくなり、業務が滞ることもあります。
スタッフ育成のための時間が取れない
現場が忙しくなるほど、新人教育やマニュアル整備に時間を割くことが難しくなります。結果として、研修が不十分なまま接客や調理を任され、現場でのトラブルやサービスの品質低下につながるケースも少なくありません。
また、ベテランスタッフに教育を任せきりになると、育成方法にばらつきが出て、店舗ごとのスキルの差も広がってしまいます。
本部と店舗の連携が上手くいかない
本部からの指示が正しく伝わらなかったり、店舗側からの報告が遅れたりといった「情報のズレ」も、飲食業界ではよくある課題のひとつです。
電話による口頭伝達やメールでの伝達だけでは、確認漏れや誤解が生じやすく、業務のミスにもつながります。現場のスピード感と本部の意思決定がかみ合わないと、オペレーション全体に影響を及ぼすリスクがあります。
飲食店でグループウェアを導入するメリット

人手不足や店舗間の連携不足といった課題を抱える飲食業界において、グループウェアの導入は大きな解決策となります。業務の見える化や情報の一元管理を通じて、現場と本部、スタッフ同士のコミュニケーションをスムーズにし、業務効率を大幅に高めることが可能です。ここでは、グループウェア導入によって得られる主なメリットを紹介します。
情報共有を一元化できる
メニューの変更、キャンペーンの開始、衛生管理の注意点など、飲食店では日々さまざまな情報が動いています。こうした情報をメールや紙の掲示だけで伝えると、見落としや周知漏れが発生するリスクがあります。
グループウェアを使えば、これらの情報を一元管理でき、誰が・いつ・どの情報を確認したのかまで把握することが可能になります。常に最新の情報をスタッフ全員が共有できる環境が整えば、業務の質も安定します。
業務連絡のミスを削減できる
営業中の店内では、伝言ミスや口頭でのすれ違いが起きやすく、業務の混乱につながることもあります。グループウェアのチャット機能や掲示板機能を活用すれば、重要な連絡を文章で残せるため、指示の抜け漏れや伝達ミスを防げます。
既読・未読の確認もできるため、「伝えたつもり」が「伝わっていなかった」といった事態も回避でき、チーム内での認識のズレが減ります。
多店舗の連携を強化できる
複数の店舗を運営している場合、本部からの指示や各店舗の状況をリアルタイムで把握するのは簡単ではありません。グループウェアを導入すれば、各店舗の進捗や売上報告、シフト状況などを一覧で管理でき、エリアマネージャーや本部担当者の負担が軽減されます。
また、店舗間で成功事例や改善点を共有する文化が生まれれば、グループ全体のレベルアップにもつながります。
マニュアルの共有で人材育成も効率化できる
新人スタッフの教育や業務の標準化には、分かりやすいマニュアルが不可欠です。グループウェアにマニュアルや動画、チェックリストを格納しておけば、必要なときに誰でもすぐに確認でき、教育のスピードと質が向上します。
現場が忙しい時間帯でも、自主的な学習ができる環境が整えば、育成コストを抑えながら即戦力化を進めることができます。
飲食店でのグループウェア導入を成功させるコツ

グループウェアは導入しただけで効果が出るものではありません。現場で実際に使われ、業務に根付いてこそ本来の効果を発揮します。特に飲食店では、日々の忙しさのなかで新しいツールを浸透させるには工夫が必要です。ここでは、グループウェア導入を成功させるための2つのポイントを紹介します。
シンプルな操作性を選ぶ
飲食店の現場では、スタッフが常にパソコンやタブレットを使えるとは限りません。また、年齢層やITスキルもばらつきがあるため、操作が複雑だと定着しにくくなります。そのため、直感的に操作できるシンプルなUI(ユーザーインターフェース)を備えたグループウェアを選ぶことが重要です。必要な機能がわかりやすく配置されており、マニュアルを見なくても感覚的に使えるような設計であれば、現場への浸透スピードも速くなります。
各店舗のノウハウを共有し、定着させる
導入したグループウェアを効果的に運用していくには、ただ情報を伝えるだけでなく、現場での“実践的な使い方”を共有していくことが重要です。たとえば、ある店舗が売上向上につながったキャンペーン施策を共有することで、他店舗でも応用が可能になります。
また、「こういう使い方をすると便利」といった小さなノウハウの共有も、全体の活用度を高めるきっかけになります。各店舗の成功体験や工夫を共有しながら運用を進めていくことで、グループウェアが現場に根付き、継続的な効果を生み出せるようになります。
飲食店でのグループウェアの選び方
飲食業界に適したグループウェアを導入するためには、現場の業務フローや課題に合った機能を備えているかどうかが大きなポイントになります。ただ機能が多いというだけでは現場で使いこなせず、結果として定着しないケースも少なくありません。ここでは、飲食店がグループウェアを選ぶ際に注目すべきポイントを紹介します。
複数の連絡手段を一元管理できるか
グループウェアを選ぶうえで重要なのは、「チャット」「掲示板」「ファイル共有」など、これまで分散していた連絡手段を一つのツールでまとめられるかどうかです。紙の伝言や口頭のやり取り、LINEやメールなどが混在していると、情報の見落としや伝達ミスが発生しやすくなります。連絡手段をグループウェアに集約すれば、スタッフ間のコミュニケーションが整い、業務全体のスピードと精度が向上します。
店舗ごとに業務進捗が確認できる機能があるか
複数店舗を展開している場合、店舗ごとの対応状況や進捗を把握できる機能は必須です。たとえば、ToDoリストやタスク管理機能があれば、各店舗に割り当てた業務が完了しているかどうかを本部やマネージャーが一目で確認できます。現場への指示も漏れなく伝わり、遅延や対応忘れを防ぐことができます。タスクの可視化によって管理側の負担も軽減され、スムーズな運営につながります。
スタッフの教育・研修が効率化できる仕組みが整っているか
飲食業界では、常に新しいスタッフの受け入れや教育が発生します。そのため、研修用のマニュアルや動画、チェックリストなどを共有できる機能があるかも重要なポイントです。グループウェア上に教育コンテンツを集約しておけば、店舗ごとに教育レベルの差が出ることなく、標準化された育成が実現できます。また、スタッフ自身が好きなタイミングで学習できるため、現場の教育担当者の負担軽減にもつながります。
飲食店で使えるグループウェアなら「店舗matic」
飲食業界の現場課題に特化して開発された「店舗matic」は、ネクスウェイが提供するグループウェアです。多店舗展開する企業の業務効率化を支援するために設計されており、情報共有の一元化や業務の見える化を誰でも簡単に実現できます。ここでは、飲食店で実際に活用されている「店舗matic」の特長をご紹介します。
今日何をするかが一目でわかる画面
「店舗matic」では、スタッフがアプリを開いた瞬間に「今日やるべきこと」が一目で確認できます。ToDoリスト形式で表示されるため、オープン準備や棚卸し、キャンペーン対応など、その日に対応すべき業務が明確に把握できます。現場の忙しさの中でも、指示内容の確認や優先順位の整理が簡単にでき、業務の抜け漏れや重複を防ぎます。
定着しやすい、ルール化された記入画面
導入初期にネックになりがちな「現場への定着」も、店舗maticなら安心です。記入画面にはあらかじめ入力ルールが設定されており、スタッフはフォーマットに沿って情報を記入するだけで、必要な内容が正確に本部へ届きます。自由記述が多いと発生しがちな記載ミスや内容のばらつきも抑えられ、情報の質と管理のしやすさを両立できます。
多店舗運営をスムーズに
複数店舗の情報を一覧で確認できるダッシュボード機能も、店舗maticの大きな特長の一つです。各店舗の売上状況、タスクの進捗、スタッフの対応状況などが一画面で確認でき、エリアマネージャーや本部担当者の移動や確認作業の負担を大幅に削減します。また、店舗同士でのナレッジ共有も促進され、グループ全体での業務改善やサービス品質の向上にもつながります。
まとめ
飲食業界では、現場のスピード感と正確な情報共有が求められる中、グループウェアは業務効率化と人材育成、店舗間連携の強化に大きく貢献します。導入を成功させるには、操作性がシンプルで現場に定着しやすく、業務にフィットした機能を持つツールを選ぶことが不可欠です。その点、ネクスウェイが提供する「店舗matic」は、飲食業界の課題に即した機能を備えており、多店舗運営を支える強力なパートナーとなります。店舗運営の質を向上させたいとお考えの方は、ぜひ「店舗matic」の導入をご検討ください。
▽店舗maticとは

サービスについての詳しい質問や導入時のお悩みもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ|店舗間コミュニケーションの悩みをツール・アプリで解決【株式会社ネクスウェイ】