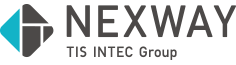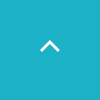株式会社ハンズ様
本 社 :東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア
設 立 :1976年8月
代表者 :代表取締役社長 社長執行役員 桜井 悟
事業内容 :住まいと住生活・手づくり関連の製品・道具・工具・
素材・部品の総合専門小売業
資本金 :1億円
店舗数 :国内店舗数84店舗(2025年9月)
ホームページ:https://hands.net/
導入のポイント
課題
店舗
-
指示伝達のわかりにくさにより作業もれが発生することがあった
-
一覧性や検索性の低さが原因で、その日にやるべきタスクの把握が困難であった
-
店舗内の進捗状況の把握や共有がしづらく、非効率な運用も発生していた
本部
-
指示連絡の作成方法がわかりづらく、運用ルールに沿った情報発信が難しい

店舗オペレーション推進部 店舗業務マニュアル推進グループ
グループマネージャー 鈴木 仁子氏
グループマネージャー 鈴木 仁子氏
背景・選定の経緯
「ハンズらしさ」を残しつつ
効率的なチェーンオペレーションを目指す
ハンズでは、各店舗の自主性を重んじる文化が根づいており、店舗それぞれにおいて独自のルールが設けられていた。しかし、2022年10月、カインズ(ベイシアループ)の一員として新体制となったことをきっかけに標準化・効率化への意識が強く芽生えたという。「お客様へのサービスを重視する『ハンズらしさ』を残しつつ、カインズの強みであるチェーンオペレーションを取り入れるべく、取り組みを始めました」と店舗オペレーション推進部 店舗業務マニュアル推進グループ グループマネージャーの鈴木仁子氏は振り返る。
組織全体の基盤を作り、業務の標準化と効率化を通じて、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整える。それが店舗オペレーション推進部のミッションだ。同部署の仁子氏・鈴木美和氏・根本千尋氏は店舗での実務経験や店舗へのアンケートをもとに課題及び新システムに必要な要件を洗い出した。「以前は、店舗スタッフ同士の情報連携がしづらく、とくに担当スタッフが不在の際は、メモをロッカーに張っておくなどの非効率的な情報伝達が常態化していました」と美和氏は話す。根本氏も「引継ぎに要している時間が長く、業務負荷が高い状態であった。誰が何の作業をしているか一見して分からず、その日出勤していない人がいると、確認や対応が遅れてしまい、お互いに負担が大きかったです」と口を揃える。
「既存のツールは指示や作業の一覧性が不十分で、『今日、何をやるんだっけ?』『どのタスクが自分に必要なんだろう?』と、迷う時間が非常に多かったと感じています。たとえ数秒のことでも、2000人分となると大きな課題です。しかも、毎日繰り返されるのです。この無駄を少しでもなくし、接客や売場づくりなどの付加価値業務に注力してほしいと考えました」(仁子氏)
新システムを導入するべく数社を比較検討したが、「良いけど、ちょっと足りない」と感じる点ばかり。「こんな機能があったらいいのにね」と部内で話していたところ、偶然見つけたのが「店舗matic」だったという。
「サービスサイトを見たとき、まさに欲しかった機能が備わっていると感じました。特に目を奪われたのは、作業メモ機能です。『今、誰がこの作業をしているか』がトップ画面に表示されるため、情報共有の課題を解決する糸口となりました」(美和氏)
仁子氏も、「今日やるべきタスクが自動で整理され、一覧表示される機能はシンプルで分かりやすい。UIも見やすいですし、既存のツールに比べて検索性が高いです」と高く評価する。
導入までのフロー
全社を巻き込んだ店舗matic導入プロジェクト
「みんなで良くしていこう」という空気感が醸成された
「店舗matic」導入の中心であった美和氏は、導入までの4ヵ月間ネクスウェイから様々なサポートを受けた。「営業担当の方からは、『店舗matic』の機能や他社さんの活用方法について丁寧に教えていただきました。だからこそ安心して進められましたし、サポート担当の方に引き継がれても不安はありませんでしたね」と話す美和氏。
特に印象的だったのが、サポート担当の「店舗オペレーション推進部だけでなく、全社を巻き込んでいこう」という姿勢だったという。「全従業員が使うシステムの変更は、極めて重大で勇気ある決断」と仁子氏が言及するように、「店舗matic」の導入はハンズにとって一大プロジェクトだ。だからこそ、「みんなで良くしていこう」という空気感の醸成は不可欠だったと美和氏は述べる。

店舗オペレーション推進部 店舗業務マニュアル推進グループ
鈴木 美和氏
鈴木 美和氏
「たとえ良いシステムを開発できたとしても、いきなり導入したのではなかなか納得感を得られません。ですが、サポート担当の方に他部署の代表者や店舗を巻き込むきっかけを作っていただき、1時間×4店舗の店舗ヒアリングを重ね、店舗matic導入の説明会も10回にわたり行ってくださったおかげで、従業員一人ひとりの意識が徐々に変わりました。『全員でシステムを変えていくんだ』という土壌が生まれたと思います」(美和氏)
説明会の対象は、のべ1000人に上った。従業員からは「どうしてこんなに変えるのか」という否定的な質問ではなく、「こういう風にできるか」と、改善に向けた意見が活発に寄せられたという。仁子氏は、「私たちの部署は縁の下の力持ちのような存在です。スポットライトを浴びる機会はそう多くはないので、説明会後、『凄く良くなりそう』『頑張ってね』という感想を頂いて、とても嬉しい気持ちになりました。『いい立ち上がりだね』と部内で密かに話し合っていました」と笑う。
「サポート担当の方とお会いしない日はなかったほど、ネクスウェイさんは密に連携してくださいました。まさに、ワンチームで取り組ませていただいたと思っております」(仁子氏)
店舗maticについて詳しく知りたい方はこちらより資料を無料でダウンロードいただけます。

店舗オペレーション推進部
根本 千尋氏
根本 千尋氏
導入後について
ネクスウェイと進む方向性が一致しているからこそ、
理想のWin-Win関係を築けている
「店舗matic」の本格導入を控える現在、根本氏は、「現在の部署に配属される以前は、店舗の管理担当として、各部署からの指示連絡を取りまとめている側でした。店舗で受けた作業を手動で取りまとめ、担当のスタッフへ共有する。とくにセール前などは情報が多く、時間もかかり大変でした。情報を集約し取りまとめる作業に、店舗の担当者がいかに苦労しているかを目の当たりにしてきたからこそ、ほかの従業員同様、『店舗matic』の導入にワクワクしています」と期待を寄せる。
一方で、導入後の課題について仁子氏は「説明会に参加し、積極的に意見をくれたのは、比較的『新しいことに前向きな層』でした。本稼働後は、2000人の全従業員が『店舗matic』に触れるようになり、おそらく『全然分からない』という声が飛んでくるようになります。それでも、何度だって説明すればいい。店舗maticの浸透に心をこめて取り組んでまいります」と述べる。
「そのためにも、当社とネクスウェイさんの目指す方向性が一致していることが重要」と断言する仁子氏。
「店舗オペレーション推進部として、最も重視されているのは『店舗が使いやすい』環境の実現。本社業務ももちろん大切ですが、店舗スタッフの日々の業務をできるだけ効率化し、接客や売場作りといった付加価値業務に時間を割けるようにすることが、最終的にお客様の満足度向上につながると考えています。この理念は、当社にもネクスウェイさんにも共通しています」(仁子氏)
「店舗が使いやすい環境を整備する」。この理念を具現化する上で、重要なカギとなっているのが、現場で日常的に使われるPDA(携帯情報端末)だ。仁子氏は、「PC画面が美しくても、PDA画面では文字が小さいうえに横に長く、見づらくなってしまうこともあります。ですが、ネクスウェイさんは2026年度に向けて、モバイルアプリの機能開発と拡張を、今後さらに進めてくださるとのこと。『ネクスウェイさんなら、当社の考えていることを実現してくれるのではないか』と大きな期待を抱いています」と語る。
「これも、SaaSのメリット。進む方向が一緒であれば、当社の望む開発を自動的にしてくださる。これこそ、理想的なWin-Winの関係だと思います」(仁子氏)

株式会社ハンズ様の本部-店舗間でのコミュニケーションにおける導入前の課題、導入後の効果、今後の展開をまとめています。ダウンロードはこちらから。
株式会社ハンズ様 事例全文ダウンロード
関連記事
本部や店舗間のコミュニケーション、
業務効率化のお悩みは、お気軽にご相談ください
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください。
お問い合わせください。
各詳細情報や業務改善お役立ち資料は
こちらからダウンロードできます。
こちらからダウンロードできます。
COPYRIGHT © NEXWAY CO.,LTD.