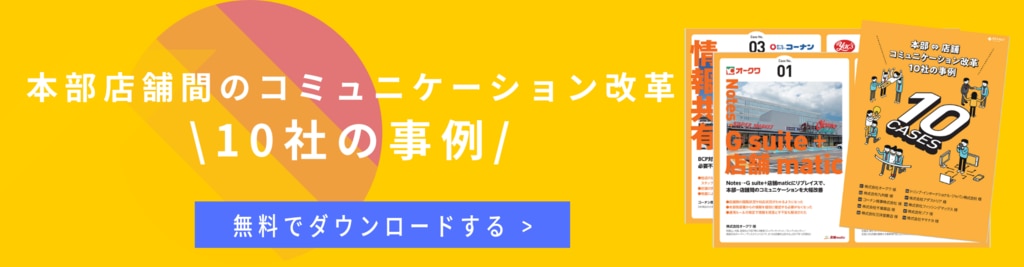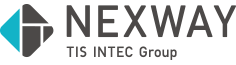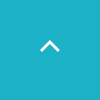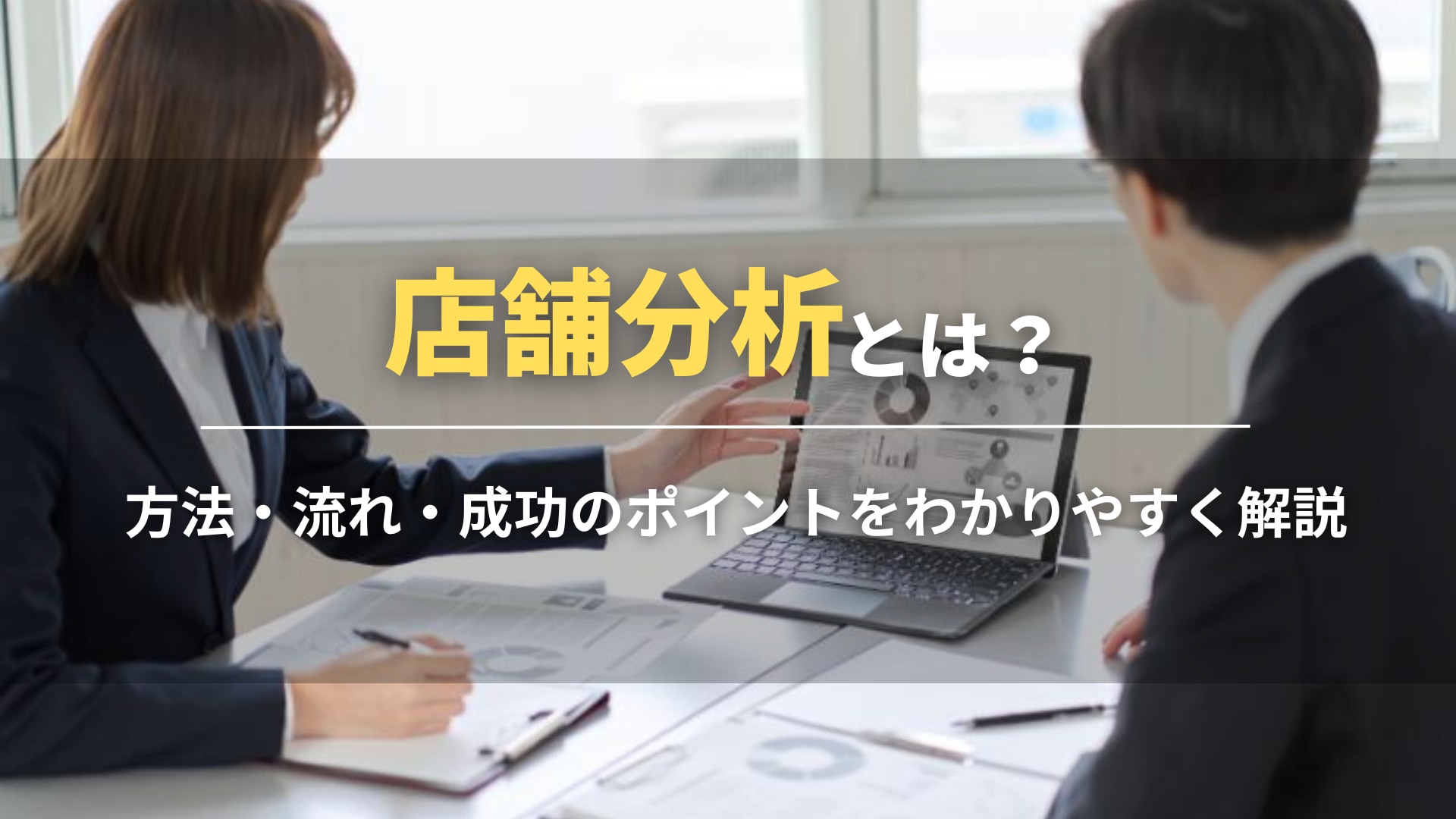
店舗分析とは?方法・流れ・成功のポイントをわかりやすく解説
目次[非表示]
- 1.店舗分析とは?
- 2.店舗分析の主な種類
- 3.店舗分析の流れと手順
- 3.1.1. 目的の明確化
- 3.2.2. 仮説立て
- 3.3.3. 分析手法の選択
- 3.4.4. 必要なデータの収集
- 3.5.5. 分析の実施と課題抽出
- 3.6.6. 改善施策の立案・実行
- 3.7.7. 振り返りとブラッシュアップ
- 4.店舗分析の代表的な手法
- 4.1.ABC分析
- 4.2.アソシエーション分析
- 4.3.クロス集計
- 4.4.メトリクス分析
- 5.効果的な店舗分析を実現するポイント
- 6.店舗分析のよくある失敗
- 7.チェーンストアに特化したコミュニケーションツールが必要
- 8.店舗maticならチェーンストアの悩みを解決
- 9.まとめ
売上や来店数、在庫の動きなど、店舗運営には日々多くのデータが蓄積されています。こうした情報をもとに分析を行い、課題を見つけて改善につなげること、それが「店舗分析」の本来の目的です。
しかし実際には、「分析して終わってしまう」「現場にうまく伝わらず、施策が実行されない」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。特にチェーンストアのように複数店舗を管理している場合、本部と現場のコミュニケーションギャップが改善の障壁となることもあります。
この記事では、店舗分析の基本的な流れや代表的な手法、よくある失敗例をふまえながら、「分析結果をいかに“改善”に落とし込むか」を軸に解説します。
店舗分析とは?
店舗分析とは、自店舗の売上や顧客データ、在庫、スタッフの稼働状況などを多角的に把握し、課題や改善の方向性を導き出す取り組みを指します。日々の営業活動で蓄積されるデータをもとに「売上の伸び悩みはどこに原因があるのか」「どのような施策を打てば改善できるのか」を見極めることが目的です。
単にデータを眺めるのではなく、現場の行動につながるヒントを得ることが重要であり、そのためには分析を継続的に行い、改善活動に落とし込む仕組みが欠かせません。
店舗分析の主な種類
店舗分析と一口にいっても、その切り口はさまざまです。ここでは、小売業やサービス業で特によく活用される代表的な分析の種類を紹介します。
顧客分析
顧客分析は、来店客や会員データをもとに「どのようなお客様が、どんな商品を、どのタイミングで購入しているのか」を明らかにする手法です。購買履歴や年代・性別などの属性データを組み合わせることで、リピーターの特徴や新規顧客の獲得につながる施策を検討できます。たとえば「平日昼間は主婦層が多い」「特定のキャンペーンで若年層の来店が増える」といった傾向をつかむことが可能です。
自店舗(自社)分析
自店舗の売上構成や在庫回転率、スタッフの稼働状況などを振り返ることで、店舗運営の強みや弱みを把握するのが自店舗分析です。売上の好調なカテゴリーや利益率の高い商品を特定すれば、重点的な販売強化が可能になります。一方で、在庫が滞留している商品や、売上の割に人件費がかかりすぎている時間帯を見つけることで、無駄を減らす改善策も導き出せます。
競合分析
競合分析は、周辺にある同業他社の動向を把握し、自店舗の立ち位置を確認するために行います。価格設定やキャンペーン内容、品揃えやサービスレベルを比較することで、自店舗が差別化すべきポイントが明確になります。とくにチェーンストアや多店舗展開をしている場合、エリアごとに競合状況を把握することで、出店戦略や販売施策の精度を高めることができます。
店舗分析の流れと手順
店舗分析は思いつきでデータを眺めるだけでは意味がなく、一定のプロセスに沿って進めることで初めて成果につながります。ここでは、店舗分析を行う際の一般的な流れと手順を紹介します。
1. 目的の明確化
まず最初に必要なのは「何のために分析するのか」という目的をはっきりさせることです。売上アップを目指すのか、在庫回転を改善したいのか、あるいは顧客満足度を高めたいのかによって、収集すべきデータや用いる手法は大きく変わります。目的が曖昧なまま分析を進めると、膨大な数字に振り回され、結局、何を改善すべきか分からなくなりがちです。だからこそ、最初にゴールを設定することが店舗分析の成功には欠かせません。
2. 仮説立て
目的が明確になったら、それを達成するための原因や要因について仮説を立てます。たとえば「売上が伸び悩んでいるのは特定の商品群の不振が理由ではないか」「リピーターが減っているのではないか」「競合店に顧客を取られているのではないか」といった形です。
仮説を立てておくことで、分析の焦点が定まり、必要なデータや手法を効率的に選択できます。逆に仮説なしで進めてしまうと、数字を追いかけるだけの「やりっぱなし分析」になり、実行につながりにくくなるため注意が必要です。
3. 分析手法の選択
立てた仮説を検証するために、最適な分析手法を選びます。たとえば「売れ筋商品を見極めたい」ならABC分析、「顧客の購買傾向を知りたい」ならアソシエーション分析、「属性ごとの違いを把握したい」ならクロス集計が有効です。
目的や仮説に合わない手法を選んでしまうと、数字を並べただけで有益な示唆が得られないこともあります。重要なのは「何を明らかにしたいのか」に合わせて手法を選び、現場でのアクションに落とし込める分析を行うことです。
4. 必要なデータの収集
分析の方向性と手法が定まったら、必要となるデータを収集します。代表的なのはPOSデータや売上データ、顧客の購買履歴、在庫情報などです。場合によってはアンケートや外部の市場データを組み合わせることもあります。
ここで重要なのは、データの精度と一貫性です。入力ミスやフォーマットの違いが多いと、分析結果が歪み、誤った判断を導くリスクが高まります。また、過去のデータだけでなく最新の情報を反映させることで、現場の状況に即した改善施策を立てやすくなります。
5. 分析の実施と課題抽出
収集したデータをもとに、選定した手法で実際に分析を行います。商品別の売上構成比を出したり、顧客層ごとの購買傾向を整理したりすることで、数字の裏にある事実が見えてきます。
ここで大切なのは、単なる数値の確認にとどまらず「改善すべき課題」を抽出することです。たとえば「売上の大半を占める商品が一部に偏っている」「リピーター率が特定の世代で低下している」「在庫が長期滞留している」といった形で、行動につながる“気づき”を得ることがゴールとなります。
6. 改善施策の立案・実行
分析で抽出した課題をもとに、具体的な改善施策を立案し、現場で実行に移します。たとえば、売れ筋商品の陳列場所を見直す、在庫が滞留している商品の販促を強化する、リピーター率が低い層に向けてキャンペーンを実施するなど、行動レベルに落とし込むことが大切です。
ここでよくある失敗は、施策を立てただけで満足してしまうことです。実際に店舗が実行しなければ、どれほど優れた施策でも成果は出ません。本部と店舗の間で方針をしっかり共有し、実行状況を確認できる仕組みをつくることが、改善を成功させる鍵となります。
7. 振り返りとブラッシュアップ
改善施策を実行したら、その結果を必ず振り返りましょう。売上や客数の変化、在庫回転率の改善度合い、顧客の反応などを検証することで、施策が有効だったかどうかを判断できます。もし効果が限定的だった場合でも、その理由を分析することで、次の改善につながります
このサイクルを繰り返すことで、店舗分析の精度は高まり、改善施策もより実効性のあるものになります。単発で終わらせず、継続的にブラッシュアップを行うことが、安定した成果を出すためのポイントです。
店舗分析の代表的な手法

店舗分析にはさまざまな方法がありますが、目的に応じて適切な手法を選ぶことで、データから具体的な改善のヒントを得られます。ここでは、下記4つの手法を紹介します。
ABC分析
アソシエーション分析
クロス集計
メトリクス分析
ABC分析
ABC分析は、売上や利益の貢献度を基準に商品をA・B・Cの3つに分類する手法です。売上上位の少数の商品(A)が全体の大部分を占めることが多く、重点的に管理すべき対象になります。Bは伸びしろが期待できる商品、Cは動きの遅い商品として、販促や在庫整理の方針を分けることが可能です。
シンプルながら「どの商品に注力するべきか」を明確にできるため、棚割りや発注、販促計画に活用される代表的な分析方法です。
アソシエーション分析
アソシエーション分析は、顧客が一緒に購入する商品同士の関係性を明らかにする手法です。たとえば「パンを買う人はバターも買う傾向がある」といった購買パターンを見つけ出すことができます。
この分析を活用すると、クロスセルの提案やセット販売、売場での陳列改善に役立ちます。顧客の実際の購買行動に基づいているため、勘や経験に頼らず「買われやすい組み合わせ」を戦略的に活かせるのが大きなメリットです。
クロス集計
クロス集計は、2つ以上のデータを掛け合わせて比較する分析手法です。たとえば「年代×購入商品」「曜日×来店時間」といった形で組み合わせることで、単一データでは見えない傾向を発見できます。
具体的には「平日昼間は30代女性の利用が多い」「週末の夕方は家族連れのまとめ買いが増える」といった顧客行動の特徴を把握できます。ターゲット層ごとに効果的な販促やサービスを考える際に有効な方法です。
メトリクス分析
メトリクス分析は、複数の指標をマトリクス(縦軸・横軸の二軸)上に配置し、商品や顧客の位置づけを可視化する手法です。たとえば「売上規模 × 利益率」で商品をプロットすれば、売上は大きいが利益が薄い商品や、利益率は高いが販売数量が少ない商品など、改善すべきポイントを直感的に把握できます。
この分析を活用することで、重点商品や改善対象を一目で把握でき、限られたリソースを効率的に配分できるのが大きなメリットです。
効果的な店舗分析を実現するポイント
店舗分析を成果につなげるためには、単にデータを集めて処理するだけでなく、活用の仕方にも工夫が必要です。ここでは効果的に取り組むための3つのポイントを紹介します。
目的に合わせて手法を選ぶ
分析にはABC分析やクロス集計など多様な方法がありますが、重要なのは「目的に合った手法を選ぶこと」です。売れ筋商品を見極めたいのか、顧客層ごとの購買傾向を知りたいのかによって、使うべき手法は異なります。目的と手段を結びつけることで、分析が具体的な改善行動へ直結します。
単発ではなく、定期的に実施する
分析は一度きりでは意味が薄く、定期的に行うことで効果が出ます。店舗の状況や顧客の動きは季節やイベントによって変化するため、継続してデータをチェックし、改善施策の結果を検証するサイクルを回すことが大切です。
スタッフと結果を共有し、現場の改善につなげる
本部や担当者だけが分析結果を理解しても、現場で行動が変わらなければ成果にはつながりません。グラフや指標をわかりやすく共有し、スタッフ全員が「自分ごと」として改善に取り組めるようにすることが重要です。結果を共有し合う文化をつくることで、改善の実行力も高まります。
店舗分析のよくある失敗

店舗分析は、売上向上や業務改善のヒントを得るうえで有効な手段ですが、実際の現場では「分析して終わり」「現場が動かない」といった落とし穴にはまりがちです。とくに本部と店舗の距離があるチェーンストアでは、分析結果が改善アクションにつながらないケースも少なくありません。
ここでは、店舗分析がうまく機能しない典型的な失敗パターンと、その背景について解説します。どれかひとつでも当てはまるようであれば、分析手法だけでなく、運用フローや伝達手段の見直しが必要かもしれません。
改善の優先度が定まらない
店舗分析を進めると、売上の落ち込みや在庫の偏り、顧客数の減少など、さまざまな課題が浮かび上がります。しかし、それらをすべて一度に改善しようとすると、現場が混乱し、どれも中途半端な結果に終わることが多いです。
とくに多店舗を抱えるチェーンでは、リソースに限りがあるため、対応の優先順位があいまいだと現場の負担が増す一方で、肝心の成果が見えにくくなります。重要なのは「影響度の高い課題」「すぐに着手できる課題」から順に、改善を段階的に進めることです。
改善テーマに優先順位をつけることで、店舗ごとの行動が明確になり、改善効果も測定しやすくなります。
データが細分化されすぎて現場で活用できない
分析に慣れてくると、ついデータを細かく切り分けて、深堀りしたくなることがあります。たとえば、「商品別×時間帯別×年代別×店舗別」など、多軸での分析を行えば、緻密なインサイトが得られるように感じるかもしれません。
しかし、現場の店長やスタッフが求めているのは「何を、いつ、どうすればいいのか」という具体的な行動指針です。情報が複雑すぎると、逆に手が止まってしまい、現場では活用されなくなってしまいます。
データの深さよりも、実際のアクションにつながる“わかりやすさ”や“即効性”を重視し、伝え方を工夫することが必要です。
数字だけを追いかけて現場に共有されない
分析は行っているが、現場とは共有されていない、というのはチェーン本部でよくあるパターンです。売上やKPIを日々確認していても、結果やその背景を店舗スタッフに伝えなければ、店舗側は何も知らず、これまで通りの業務を続けるだけです。
特に現場のスタッフは日々の接客や作業に追われており、数字の分析や報告書を読む時間が限られています。そのため、共有の仕方にも工夫が必要です。たとえば、グラフや一言コメントで要点を伝える、改善アクションを箇条書きにして示す、といった配慮があるだけで、伝わりやすさが大きく変わります。
数字を「本部だけのもの」にせず、現場と一緒に見る・考える姿勢が、改善の第一歩となります。
改善方針が伝わらず、現場が動かない
改善施策を立てて店舗に指示を出しても、現場がまったく動いてくれない──という声は本部からよく聞かれます。その原因の多くは、「何をすればいいかは伝わっていても、なぜそれをやるのか」が理解されていないことにあります。
スタッフからすれば、「なぜ急にこの商品をプッシュするのか」「レイアウトを変える意味がわからない」と思っているうちは、行動に移すモチベーションが湧きません。改善施策の背景や目的を丁寧に説明し、「現場にとっても意味のあること」だと納得してもらうことが重要です。
また、施策の実行を「やってください」で終わらせず、進捗確認やフォローの体制を整えることで、現場も安心して動きやすくなります。
チェーンストアに特化したコミュニケーションツールが必要
店舗分析で課題を見つけ、改善施策を立てたとしても、それを現場で実行してもらえなければ、意味はありません。特にチェーンストアでは、本部と店舗の距離が物理的にも心理的にも離れており、改善アクションの“浸透”が最大の課題となることが少なくありません。
Excelやメール、掲示物などで指示を出しても、情報が埋もれてしまったり、店舗ごとに理解度や実施状況に差が出てしまうケースはよくあります。また、電話や対面で確認をとるにも限界があり、店舗数が多いほど、情報伝達にかかる負荷は増大します。
だからこそ、チェーンストア運営に特化した「コミュニケーションツール」の導入が重要です。本部からの指示や資料を一元管理でき、店舗側の閲覧状況や対応進捗もリアルタイムで確認できる仕組みがあれば、改善施策を確実に“実行”へとつなげることができます。
コミュニケーションを効率化することで、分析→改善→実行→振り返りのサイクルをスムーズに回し、全店舗で統一されたアクションを取ることが可能になります。
店舗maticならチェーンストアの悩みを解決
本部の意図が店舗に伝わらない、改善施策が現場で実行されない──そんなチェーンストア特有の悩みを解決するのが、店舗maticです。
店舗maticは、店舗運営における“伝える・確認する・実行する”をシンプルかつ効率的にする、チェーン本部向けのクラウド型コミュニケーションツールです。各店舗への情報発信、資料配布、タスクの割り振りから進捗の可視化までを一元管理できるため、「伝えたのに伝わっていなかった」「誰が対応したのかわからない」といった情報の断絶をなくします。
さらに、店舗ごとの対応状況が一覧で確認できるため、未対応店舗へのリマインドやフォローも簡単。現場とのやり取りにかかっていた時間や手間を大幅に削減でき、限られた人員でも複数店舗を効率的に管理・支援することが可能です。
店舗分析の結果から見えてきた改善施策を、現場で確実に実行に移す。その“最後の一歩”を支えるのが、店舗maticの大きな価値です。
まとめ
店舗分析は、売上や顧客データを活用して店舗運営を改善するための有効な手段です。しかし、データを集めて終わりにしてしまったり、現場に伝わらず実行されないままでは、本来の目的を果たすことはできません。
分析を成功させるには、目的に合った手法を選び、継続的に実施し、店舗スタッフと結果を共有して改善アクションにつなげることが大切です。そして、施策の実行力を高めるには、本部と店舗をつなぐコミュニケーションの仕組みが欠かせません。
店舗maticは、チェーンストア運営に特化したクラウドツールとして、情報共有・タスク管理・進捗確認までを一元化し、改善の“実行”を支援します。店舗分析の成果を確実に現場で活かしたい企業にとって、心強いパートナーとなるはずです。